幸せなギタリスト ― 2012/02/01 22:08
2月1日、マイク・キャンベル62回目のお誕生日おめでとう!新譜ではどんなプレイを聞かせてくれるのでしょう?そして春からのライブでは?どんなギター、どんなプレイにしろ、きっと期待を裏切らないであろうマイク。どんな髪型、どんな衣装でも、結局格好良いマイク。最高に大好きです。
私はiPadを、あまり欲しいと思っていない。
体格からして、携帯するには大きすぎる。せいぜい、21世紀の名探偵シャーロックが、犯人をぶん殴るのにちょうど良いかも知れない程度に思っていたのだが、このたび発売になるアプリは、侮れないシロモノだそうだ。
ずばり、George Harrison Guitar Collection。ジョージのギターの詳細なデータや画像、ジョージがそれを持っている写真や、ジョージを敬愛する数々のミュージシャンたちがジョージのギターを弾いている動画などが楽しめるそうだ。彼らが弾いているギターは、本物なのだろうか…
ニュース記事はこちら。
コマーシャル映像はこちら。これを見るだけでも楽しい。
そして、その動画の中には、マイク・キャンベルが、ロッキーを弾いているものがあるらしい…!これは見たい!絶対見たい!マイク先生だけで良いから欲しい!
マイクとジョージ関連のギターと言えば、ロッキーはもちろんだが、[Damn the Torpedoes] のジャケット写真にもなった、リッケンバッカーのエピソードがいい。
マイクが中古で手に入れたリッケンバッカーは、もともと欲しかった形ではなかった。マイクは、ジョージが映画で使っていたような(そしてロジャー・マッグインも真似した)大きな形が欲しかったのだ。
しかし、この時手に入れた12弦は、ジョージが所有している同型ギターの、まさに同じラインで、ジョージのすぐ後に作られた…「同族」,もしくは兄弟だったとのこと。それを嬉々として語るマイクが可愛い。わかる、その気持ち。
私はiPadを、あまり欲しいと思っていない。
体格からして、携帯するには大きすぎる。せいぜい、21世紀の名探偵シャーロックが、犯人をぶん殴るのにちょうど良いかも知れない程度に思っていたのだが、このたび発売になるアプリは、侮れないシロモノだそうだ。
ずばり、George Harrison Guitar Collection。ジョージのギターの詳細なデータや画像、ジョージがそれを持っている写真や、ジョージを敬愛する数々のミュージシャンたちがジョージのギターを弾いている動画などが楽しめるそうだ。彼らが弾いているギターは、本物なのだろうか…
ニュース記事はこちら。
コマーシャル映像はこちら。これを見るだけでも楽しい。
そして、その動画の中には、マイク・キャンベルが、ロッキーを弾いているものがあるらしい…!これは見たい!絶対見たい!マイク先生だけで良いから欲しい!
マイクとジョージ関連のギターと言えば、ロッキーはもちろんだが、[Damn the Torpedoes] のジャケット写真にもなった、リッケンバッカーのエピソードがいい。
マイクが中古で手に入れたリッケンバッカーは、もともと欲しかった形ではなかった。マイクは、ジョージが映画で使っていたような(そしてロジャー・マッグインも真似した)大きな形が欲しかったのだ。
しかし、この時手に入れた12弦は、ジョージが所有している同型ギターの、まさに同じラインで、ジョージのすぐ後に作られた…「同族」,もしくは兄弟だったとのこと。それを嬉々として語るマイクが可愛い。わかる、その気持ち。
Sinnerman ― 2012/02/04 23:52
去年の夏、NHKで放映した英国BBCのドラマ[SHERLOCK] がとても面白かったので、先日発売になったばかりの英国版DVDでシリーズ2も手に入れた。もちろん、PALなのでPCでしか再生できないが、ありがたいことに英語の字幕はついている。
自分の理解のために、よせば良いのに「アヤシゲ翻訳」など始めたが最後。今、3話目をやっているのだが、ほぼ廃人状態である。
このドラマ、面白いのだが、音楽に関してはこれといったものはなかった。しかし、シリーズ2の3話目にして、やや音楽的なこだわりが見られて、面白かった。
その一つが、ニーナ・シモンの "Sinnerman" である。どんなシーンでどう使われているかは、ドラマを見てのお楽しみ。NHKでいつ放映するのかは分かったものではないけれど。
ジャズに関しては完全に門外漢の私だが、ニーナ・シモンはさすがに知っている。ジョージやディランの楽曲の素晴らしいカバーがあるからだ。特に、彼女のジョージに対する思い入れは強そうだ。何と言っても、壮大な "My Sweet Lord" が有名だが、私は "Isn't It A Pity" や、"Here Comes the Sun" も好きだ。
1933年ノースカロライナ州生まれ。ピアノに関してはいわゆる天才少女で、ジュリアード音楽院に進学している。彼女がただのピアノの上手い人で終わらなかったのは、あの凄まじい歌唱力と、ピアノをまるで体の一部のように、しなやかに、自由自在に ― まるでピアノという楽器が存在しないかのように ― 演奏し、ジャズというジャンルにおいてその才能を発揮したからだろう。
"Sinnerman" は、アメリカで古くから歌われているトラディショナル・スピリチュアルズの一つだそうだ。まず、歌詞が強烈。
「罪人よ、どこへゆくのだ? / そう、岩山へゆくのだ / 岩山よ私を隠しておくれ / しかし岩山は叫ぶ / それはできない / おお、岩山になにが起きたのか / 主よ、主よ / だから川へと走ってゆく / 川には血が流れ / 水は沸き立っていた / 主よどうか私の祈りをお聞き下さい / しかし主は言われた / 悪魔のとこおへゆくがいい / すると悪魔は待っていた / 私は叫んだ / 力を! 力を! 主よ、あなたが必要なのです…」
ニーナ・シモンの声は、一体それが女の声なのか、男の声なのかも分からないような、不思議な魔力を持っている。男でも、女でもない、人間ですらないような、音楽というどこか抽象的なものの、コアの部分だけが響いているようだ。
[SHERLOCK] での使われ方は、格好良くて、スタイリッシュで、それでいて歌詞の意味とも絶妙にリンクしている。このドラマはシリーズ3の制作が発表されたようだが(そりゃそうだ…)、こういうイカした選曲を期待している。
自分の理解のために、よせば良いのに「アヤシゲ翻訳」など始めたが最後。今、3話目をやっているのだが、ほぼ廃人状態である。
このドラマ、面白いのだが、音楽に関してはこれといったものはなかった。しかし、シリーズ2の3話目にして、やや音楽的なこだわりが見られて、面白かった。
その一つが、ニーナ・シモンの "Sinnerman" である。どんなシーンでどう使われているかは、ドラマを見てのお楽しみ。NHKでいつ放映するのかは分かったものではないけれど。
ジャズに関しては完全に門外漢の私だが、ニーナ・シモンはさすがに知っている。ジョージやディランの楽曲の素晴らしいカバーがあるからだ。特に、彼女のジョージに対する思い入れは強そうだ。何と言っても、壮大な "My Sweet Lord" が有名だが、私は "Isn't It A Pity" や、"Here Comes the Sun" も好きだ。
1933年ノースカロライナ州生まれ。ピアノに関してはいわゆる天才少女で、ジュリアード音楽院に進学している。彼女がただのピアノの上手い人で終わらなかったのは、あの凄まじい歌唱力と、ピアノをまるで体の一部のように、しなやかに、自由自在に ― まるでピアノという楽器が存在しないかのように ― 演奏し、ジャズというジャンルにおいてその才能を発揮したからだろう。
"Sinnerman" は、アメリカで古くから歌われているトラディショナル・スピリチュアルズの一つだそうだ。まず、歌詞が強烈。
「罪人よ、どこへゆくのだ? / そう、岩山へゆくのだ / 岩山よ私を隠しておくれ / しかし岩山は叫ぶ / それはできない / おお、岩山になにが起きたのか / 主よ、主よ / だから川へと走ってゆく / 川には血が流れ / 水は沸き立っていた / 主よどうか私の祈りをお聞き下さい / しかし主は言われた / 悪魔のとこおへゆくがいい / すると悪魔は待っていた / 私は叫んだ / 力を! 力を! 主よ、あなたが必要なのです…」
ニーナ・シモンの声は、一体それが女の声なのか、男の声なのかも分からないような、不思議な魔力を持っている。男でも、女でもない、人間ですらないような、音楽というどこか抽象的なものの、コアの部分だけが響いているようだ。
[SHERLOCK] での使われ方は、格好良くて、スタイリッシュで、それでいて歌詞の意味とも絶妙にリンクしている。このドラマはシリーズ3の制作が発表されたようだが(そりゃそうだ…)、こういうイカした選曲を期待している。
The Village Green Preservation Society ― 2012/02/08 21:51
ザ・キンクスは私にとって一つの謎かも知れない。
好きかと訊かれれば、確実に好きだと答える。ザ・フーと比べてどちらが好きかと訊かれても、確実にキンクスと答えるし、"Lola" はロックの十大名曲の一つだとさえ思う。
しかし、不思議なことにキンクスのヒストリーは殆ど知らないし、メンバーに至っては、デイヴィス兄弟しか知らない。このブログで話題にしたことも今までなかったのではないだろうか。
持っているアルバムは、1964年のデビューアルバムから、1972年の[Everybody's in Show-Biz] まで、そして1996年のライブ・コンピレーション[To the Bone] と、[The Kinks Best] - 中途半端なようで、これが妥当なような気もする。
この私の中でキンクスが占める奇妙なポジションには、幾つか理由があると思う。
まず第一にビジュアル ― いきなり第一に挙げるのは気の毒か。ビジュアルに関しては、ビートルズが図抜けているのでそう思えるだけかも知れない。
次に思いつくのが、友好関係がほかに比べて薄い ― 60年代の、特にブリット勢に顕著なのだが、その時代のロッカー達は非常に仲が良い。そういう交友の中 ― 特に私がすきな人たちの中に、デイヴィス兄弟がなかなか姿を現さない。
それから、私が「コンセプトアルバム」や、「ロックオペラ」をあまり買っていないということも考えられる。特に、「ロックオペラ」は苦手だ。
ロックという音楽は、短く、深く、突き刺すような楽曲構成であり、しかもそれぞれの独立性が高いのが特徴だと思っている。一方、オペラという音楽ジャンルは、横に長い構成を重視しているため、どうもロックには向いていない形式だと思うのだ。
そもそも、クラシック音楽でかなり完成されたものが出来ている以上、向いていないロックをあてはめようというぎこちなさに、耐えられない。
ついでに言えば、どんなに優秀なミュージシャンでも、得意不得意はあると思っている。ロックンローラーが、どういう訳か(新しい側面を見せたいとでも思うのか)、ジャズやクラシックをやろうとすると、たいていつまらない音楽になると、私は思っている。
しかも、演奏そのものはそこそこ上手だったりするから、こまる。下手でもないけど、全く面白くない、不得意分野の音楽というものは、どうも耐えがたい ―
話が逸れた。とにかく、私にとってのキンクスは謎だ。
それでも、その音楽はかなり好きで、"Lola" や "You Realy Got Me" はもちろんだが、最近ヘヴィローテーションで聴いているのが、"The Village Green Preservation Society" である。曲は美しいし、エッジも効いていて、歌詞も抜群に良い。韻の踏み方も素晴らしく、いつ、何度聞いてもいちいち感動している。この曲が、ベストに入っていないのには驚いてしまった。
演奏としては、[To The Bone]に入っているライブバージョンも素晴らしいし、スタジオ録音版も最高に格好良い。どういう訳だか知らないが、私が持っているアルバム[The Kinks are the village green preservation societ] のスリーブには、このタイトル曲の歌詞だけが載っている。
歌詞も好きだと言ったが、特に "Protecting new ways for me and for you" がお気に入り。それから、"We are the Sherlock Holmes English Speaking Vernacular / Help save Fu Manchu, Moriarty, Drucula" も吹っ飛んでいていい。
動画となると、いまいち「これ!」というものが無い。そういう所も、キンクスらしいとでも言うのだろうか。そういうわけで、スタジオ録音版でどうぞ。
好きかと訊かれれば、確実に好きだと答える。ザ・フーと比べてどちらが好きかと訊かれても、確実にキンクスと答えるし、"Lola" はロックの十大名曲の一つだとさえ思う。
しかし、不思議なことにキンクスのヒストリーは殆ど知らないし、メンバーに至っては、デイヴィス兄弟しか知らない。このブログで話題にしたことも今までなかったのではないだろうか。
持っているアルバムは、1964年のデビューアルバムから、1972年の[Everybody's in Show-Biz] まで、そして1996年のライブ・コンピレーション[To the Bone] と、[The Kinks Best] - 中途半端なようで、これが妥当なような気もする。
この私の中でキンクスが占める奇妙なポジションには、幾つか理由があると思う。
まず第一にビジュアル ― いきなり第一に挙げるのは気の毒か。ビジュアルに関しては、ビートルズが図抜けているのでそう思えるだけかも知れない。
次に思いつくのが、友好関係がほかに比べて薄い ― 60年代の、特にブリット勢に顕著なのだが、その時代のロッカー達は非常に仲が良い。そういう交友の中 ― 特に私がすきな人たちの中に、デイヴィス兄弟がなかなか姿を現さない。
それから、私が「コンセプトアルバム」や、「ロックオペラ」をあまり買っていないということも考えられる。特に、「ロックオペラ」は苦手だ。
ロックという音楽は、短く、深く、突き刺すような楽曲構成であり、しかもそれぞれの独立性が高いのが特徴だと思っている。一方、オペラという音楽ジャンルは、横に長い構成を重視しているため、どうもロックには向いていない形式だと思うのだ。
そもそも、クラシック音楽でかなり完成されたものが出来ている以上、向いていないロックをあてはめようというぎこちなさに、耐えられない。
ついでに言えば、どんなに優秀なミュージシャンでも、得意不得意はあると思っている。ロックンローラーが、どういう訳か(新しい側面を見せたいとでも思うのか)、ジャズやクラシックをやろうとすると、たいていつまらない音楽になると、私は思っている。
しかも、演奏そのものはそこそこ上手だったりするから、こまる。下手でもないけど、全く面白くない、不得意分野の音楽というものは、どうも耐えがたい ―
話が逸れた。とにかく、私にとってのキンクスは謎だ。
それでも、その音楽はかなり好きで、"Lola" や "You Realy Got Me" はもちろんだが、最近ヘヴィローテーションで聴いているのが、"The Village Green Preservation Society" である。曲は美しいし、エッジも効いていて、歌詞も抜群に良い。韻の踏み方も素晴らしく、いつ、何度聞いてもいちいち感動している。この曲が、ベストに入っていないのには驚いてしまった。
演奏としては、[To The Bone]に入っているライブバージョンも素晴らしいし、スタジオ録音版も最高に格好良い。どういう訳だか知らないが、私が持っているアルバム[The Kinks are the village green preservation societ] のスリーブには、このタイトル曲の歌詞だけが載っている。
歌詞も好きだと言ったが、特に "Protecting new ways for me and for you" がお気に入り。それから、"We are the Sherlock Holmes English Speaking Vernacular / Help save Fu Manchu, Moriarty, Drucula" も吹っ飛んでいていい。
動画となると、いまいち「これ!」というものが無い。そういう所も、キンクスらしいとでも言うのだろうか。そういうわけで、スタジオ録音版でどうぞ。
Farewell to Liverpool ― 2012/02/11 22:50
** 告知 **
コメントが書き込み不可になっていることを、すっかり忘れてました!解除しました。コメントOKです。
今日は、半年に一度のアイリッシュ・パブでのアイリッシュ・セッションだった。今回は大した準備もせず、気軽に出かけたのだが、リール・セットのリードに呼ばれてしまい、ちょっと焦った。それでもまぁ…そこそこ吹いたかな。
私がアイルランド音楽のティン・ホイッスルを習い始めた初期のころに覚えた曲のなかに、"Farewell to Liverpool" という曲がある。曲は "Danny Boy" によく似た美しい曲で、「リヴァプール」という土地への思い入れもあって、好きな曲の一つだ。
詞は、リヴァプールからアメリカへ旅立つ男の心情を歌っている。もちろん、アイルランドからの移民がイングランドのリヴァプールからさらに旅立つということ。その先にはアメリカがあり、アイルランドから持ち込まれた音楽が、やがてカントリーやロックへと発展してゆく。
曲名は、私が覚えている "Farewell to Liverpool" よりも、"Leaving of Liverpool" の方がメジャーなようだ。
私はテンポはゆっくり気味で、しっとり歌わせる演奏が好きなのだが、それに近い演奏というと、なかなか動画では見つからない。やっとみつけたのが、この謎の(?)ハーパーの演奏。別に上手くもないが、とても味わいがあって、好きだ。
むしろ主流なのは、このダブリナーズのような、威勢の良い演奏らしい。私はアイリッシュ好きのくせに、カントリーがやや苦手なので、もうすこし哀愁を強めてほしいけど…まぁ、これも悪くない。
ロック界では、ザ・ポーグズが歌っているが、こちらも威勢が良い。
誰かしっとり系でやっていないかしら…と思ったら、意外な人があがった。ほかでもない、ボブ・ディラン様である。
[The Bootleg Series Vol.9 The Witmark Demos 1962-1964] の中に、"Farewell" という曲があるが、実は曲が、アイリッシュ・トラディショナルである "Farewell to Liverpool" なのだ。歌詞はずいぶん変わっていて、Liverpoolも登場しない。ただ、故郷を離れ、恋人と別れる旅立ちの歌には違いない。
このアルバムをお持ちの方は、ぜひ確認してほしい。

コメントが書き込み不可になっていることを、すっかり忘れてました!解除しました。コメントOKです。
今日は、半年に一度のアイリッシュ・パブでのアイリッシュ・セッションだった。今回は大した準備もせず、気軽に出かけたのだが、リール・セットのリードに呼ばれてしまい、ちょっと焦った。それでもまぁ…そこそこ吹いたかな。
私がアイルランド音楽のティン・ホイッスルを習い始めた初期のころに覚えた曲のなかに、"Farewell to Liverpool" という曲がある。曲は "Danny Boy" によく似た美しい曲で、「リヴァプール」という土地への思い入れもあって、好きな曲の一つだ。
詞は、リヴァプールからアメリカへ旅立つ男の心情を歌っている。もちろん、アイルランドからの移民がイングランドのリヴァプールからさらに旅立つということ。その先にはアメリカがあり、アイルランドから持ち込まれた音楽が、やがてカントリーやロックへと発展してゆく。
曲名は、私が覚えている "Farewell to Liverpool" よりも、"Leaving of Liverpool" の方がメジャーなようだ。
私はテンポはゆっくり気味で、しっとり歌わせる演奏が好きなのだが、それに近い演奏というと、なかなか動画では見つからない。やっとみつけたのが、この謎の(?)ハーパーの演奏。別に上手くもないが、とても味わいがあって、好きだ。
むしろ主流なのは、このダブリナーズのような、威勢の良い演奏らしい。私はアイリッシュ好きのくせに、カントリーがやや苦手なので、もうすこし哀愁を強めてほしいけど…まぁ、これも悪くない。
ロック界では、ザ・ポーグズが歌っているが、こちらも威勢が良い。
誰かしっとり系でやっていないかしら…と思ったら、意外な人があがった。ほかでもない、ボブ・ディラン様である。
[The Bootleg Series Vol.9 The Witmark Demos 1962-1964] の中に、"Farewell" という曲があるが、実は曲が、アイリッシュ・トラディショナルである "Farewell to Liverpool" なのだ。歌詞はずいぶん変わっていて、Liverpoolも登場しない。ただ、故郷を離れ、恋人と別れる旅立ちの歌には違いない。
このアルバムをお持ちの方は、ぜひ確認してほしい。

Del Shannon the making of an album ― 2012/02/14 23:35
**再度告知!**
人に指摘されて、コメントが相変わらず不可になっていたことに気付きました。とほほ。今度こそ!今度こそコメント可にしました!やれやれ。
これまた人様に教えられて、デル・シャノンが結果的に最後となってしまったアルバムを作る様子がとらえられた動画を見た。これは凄い。一体、元ネタは何なのだろう?
ピアノを弾くベンモント・テンチに、コーラスをつけるハウイ・エプスタインも登場して、ハートブレイカーズ的にも魅力的…マイクはどこだ?
ベンモントがピアノを弾くシーンや、デルがギターを弾きながら歌っているシーンでもわかるのだが、アップライト・ピアノのフロントボードを外すのは、何か意味があるのだろうか?共鳴を減らすとか?ピアノは精密機械なので、ホコリとかゴミとか、はいらないように締めておいた方が良いと思うのだが。…それで、マイクはどこだ?
何と言っても、ジェフ・リンとトム・ペティ、デル・シャノンが揃っているところが面白い。膝を叩きながら…リズムを取って…そのうち馬鹿になってくる…放っておこう。
一番の突っ込みどころは、トムさんの服のひどさだ。あまりのひどさに卒倒しそうになった。なんだ、その青いスウェットは?金髪だから青が似合うのは認めるが、それにしたって、ダサい!ダサすぎる!隣りの白トレーナーもダサいが、トムさんは輪を掛けてダサい!しかも、その青スウェットの上に、オシャレのつもりなのか、ベストを羽織り…ベストさえ羽織れば許してもらえると思ったら、大間違いだ!マイクはどこだ!
そもそも、このスタジオ、もうすこし片付かないのだろうか。ロイ・オービソンの "Mystery Girl" の録音スタジオもとんでもない汚部屋だったが、このデル・シャノンのスタジオも断捨離して、整理して、すっきりした方が良いのではないだろうか。これだから男子に任せておくと…それで、マイクはどこ?
この映像はせいぜい1988年から1990年ごろのだと思うのだが、1990年2月には悲しいことに、デルが自殺してしまっている。この映像を見る限りは、想像もできない。このことを思うと、いつも浮かぶのが、トムさんがデルの死を知ったときの光景。ツアーバスが止まった駐車場で、マイクがやってきて、そのニュースを告げるシーン。二人が吐く息の白さすら目に浮かぶような印象がある。
そうか。マイクはカメラを回しているのか。きっとそうだ。そういうことにしよう。ジョージがやりそうなことは、マイクもやりそうだもんね。
人に指摘されて、コメントが相変わらず不可になっていたことに気付きました。とほほ。今度こそ!今度こそコメント可にしました!やれやれ。
これまた人様に教えられて、デル・シャノンが結果的に最後となってしまったアルバムを作る様子がとらえられた動画を見た。これは凄い。一体、元ネタは何なのだろう?
ピアノを弾くベンモント・テンチに、コーラスをつけるハウイ・エプスタインも登場して、ハートブレイカーズ的にも魅力的…マイクはどこだ?
ベンモントがピアノを弾くシーンや、デルがギターを弾きながら歌っているシーンでもわかるのだが、アップライト・ピアノのフロントボードを外すのは、何か意味があるのだろうか?共鳴を減らすとか?ピアノは精密機械なので、ホコリとかゴミとか、はいらないように締めておいた方が良いと思うのだが。…それで、マイクはどこだ?
何と言っても、ジェフ・リンとトム・ペティ、デル・シャノンが揃っているところが面白い。膝を叩きながら…リズムを取って…そのうち馬鹿になってくる…放っておこう。
一番の突っ込みどころは、トムさんの服のひどさだ。あまりのひどさに卒倒しそうになった。なんだ、その青いスウェットは?金髪だから青が似合うのは認めるが、それにしたって、ダサい!ダサすぎる!隣りの白トレーナーもダサいが、トムさんは輪を掛けてダサい!しかも、その青スウェットの上に、オシャレのつもりなのか、ベストを羽織り…ベストさえ羽織れば許してもらえると思ったら、大間違いだ!マイクはどこだ!
そもそも、このスタジオ、もうすこし片付かないのだろうか。ロイ・オービソンの "Mystery Girl" の録音スタジオもとんでもない汚部屋だったが、このデル・シャノンのスタジオも断捨離して、整理して、すっきりした方が良いのではないだろうか。これだから男子に任せておくと…それで、マイクはどこ?
この映像はせいぜい1988年から1990年ごろのだと思うのだが、1990年2月には悲しいことに、デルが自殺してしまっている。この映像を見る限りは、想像もできない。このことを思うと、いつも浮かぶのが、トムさんがデルの死を知ったときの光景。ツアーバスが止まった駐車場で、マイクがやってきて、そのニュースを告げるシーン。二人が吐く息の白さすら目に浮かぶような印象がある。
そうか。マイクはカメラを回しているのか。きっとそうだ。そういうことにしよう。ジョージがやりそうなことは、マイクもやりそうだもんね。
LITMW:ちょっと気になる ― 2012/02/17 23:26
映画「ジョージ・ハリスン:リヴィング・インザ・マテリアル・ワールド」はなんだかんだと言いながら好評で、DVD, BRもよく売れているらしい。嬉しい限りだ。
高評価で売れれば、さらに今回フォーカスされなかった面のジョージドキュメンタリーも作られるだろう。期待している。
さて、映画で少し気になっていた小さないくつかのポイント。
まず、ディケンズ。2011/12/12の記事 GH:LITMW(5回目)- ディケンズのことで言及した。
ジョージとポールの学校とチャールズ・ディケンズに関して、ポールがどう表現しているのか、確認してみると…
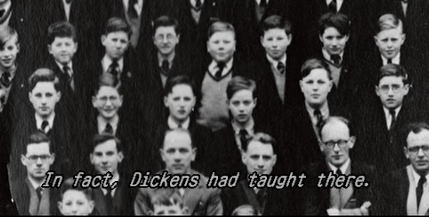
"had taught"「教えていた」と表現したのは、ポールだった。ポールもきっと、学校関係者に「ディケンズが教えていたこともあるんだぞ(どうだ、凄いだろう)」と言われていたのだろう。実際は、ディケンズが教鞭を執っていたのではなく、運営資金集めの講演したということ。
次に、ジム・ケルトナ-・ファンクラブの話。
ジョージが「ぼくが好きな人のファンクラブ」を作ると言って、アルバムのジャケットに「ジム・ケルトナー・ファンクラブに写真を送って下さい」と印字したところ、イカれた連中のイカれた写真が山と届いたという話。
その字幕について、最初はぼんやりと違和感を持っていたのだが、7回もスクリーンで見るうちに、その違和感の正体に気付いた。

「弓」って…刺さるもの?
もちろん、これは翻訳間違い ― 間違いというより、勘違い ― うっかりミスに近いだろうか。「弓矢」というまとまりのイメージで、「矢」とするべきところを、なぜか「弓」としてしまったらしい。ジム・ケルトナーはもちろん、正しく "an arrow" と言っている。
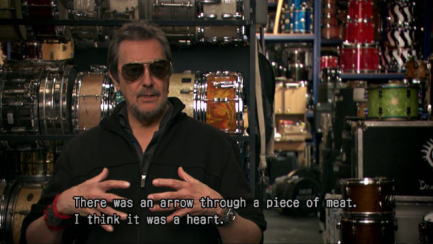
最後に、エンディング・クレジットで気になった名前。

お前か、ウォーレン・ナントカ!(相変わらず姓をどう発音すれば良いのかよく分からない)2009/06/17の記事 お前か、ウォーレン・ナントカ!でも言及したとおり、トム・ペティにジョージ・ハリスンというと、姿をあらわすちょっとイケメンな彼。

そうか…ウォーレンがインタビュアーだったのか。道理で、スコセッシのキンキン声がしないと思った。彼となら、トムさんもジョージ談義が狂い咲きし放題だったろう…
高評価で売れれば、さらに今回フォーカスされなかった面のジョージドキュメンタリーも作られるだろう。期待している。
さて、映画で少し気になっていた小さないくつかのポイント。
まず、ディケンズ。2011/12/12の記事 GH:LITMW(5回目)- ディケンズのことで言及した。
ジョージとポールの学校とチャールズ・ディケンズに関して、ポールがどう表現しているのか、確認してみると…
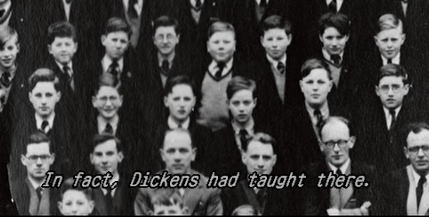
"had taught"「教えていた」と表現したのは、ポールだった。ポールもきっと、学校関係者に「ディケンズが教えていたこともあるんだぞ(どうだ、凄いだろう)」と言われていたのだろう。実際は、ディケンズが教鞭を執っていたのではなく、運営資金集めの講演したということ。
次に、ジム・ケルトナ-・ファンクラブの話。
ジョージが「ぼくが好きな人のファンクラブ」を作ると言って、アルバムのジャケットに「ジム・ケルトナー・ファンクラブに写真を送って下さい」と印字したところ、イカれた連中のイカれた写真が山と届いたという話。
その字幕について、最初はぼんやりと違和感を持っていたのだが、7回もスクリーンで見るうちに、その違和感の正体に気付いた。

「弓」って…刺さるもの?
もちろん、これは翻訳間違い ― 間違いというより、勘違い ― うっかりミスに近いだろうか。「弓矢」というまとまりのイメージで、「矢」とするべきところを、なぜか「弓」としてしまったらしい。ジム・ケルトナーはもちろん、正しく "an arrow" と言っている。
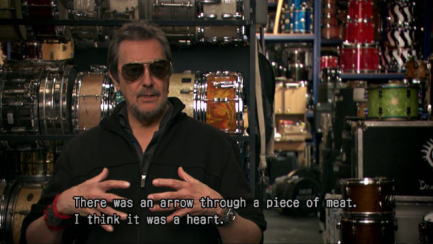
最後に、エンディング・クレジットで気になった名前。

お前か、ウォーレン・ナントカ!(相変わらず姓をどう発音すれば良いのかよく分からない)2009/06/17の記事 お前か、ウォーレン・ナントカ!でも言及したとおり、トム・ペティにジョージ・ハリスンというと、姿をあらわすちょっとイケメンな彼。

そうか…ウォーレンがインタビュアーだったのか。道理で、スコセッシのキンキン声がしないと思った。彼となら、トムさんもジョージ談義が狂い咲きし放題だったろう…
Here She Comes Again / The Stands ― 2012/02/20 23:14
ザ・スタンズ The Stands がアルバム [All Years Leaving] を発表したときは、かなり話題になったと思う。
リヴァプール出身の四人組。ビートルズやザ・バーズを彷彿とさせるサウンドは、レトロで、でも瑞々しく、キラキラと煌めいていた。それで話題にならない方がどうかしている。なんでも、ノエル・ギャラガーが絶賛したとのことだが、とにかくそのアルバムは買ったし、その評価は当然だと思った。録音は、一部アビー・ロードで行ったらしい。
もっともヒットしたシングルが、"Here She Comes Again"。まさに、狙いすましたサウンド、メロディ、コーラス、そしてプロモーション・ビデオ!ポチっとすれば、YouTubeで見られるってさ。
こうして見るとこのバンド、容姿もなかなか揃っている方では無いだろうか(基準がビートルズというべらぼうに高い所にあるので、大抵のバンドは分が悪い)。うつむいているけど、ベースの彼とかちょっと格好良いし、何と言っても、リッケンバッカーを抱えたギターが可愛い!ポイント高し!
正真正銘、バーズを狙っていて、ここまで爽やかに、鮮やかに、ど真ん中を射貫かれると、もう気持ち良いとしか言いようがない。実際、この曲は名曲だと思うし、たびたび繰り返し聞きたくなる。
ビデオのセッティングももちろんバーズの真似。ハンター・ガールズに囲まれているのは、"The times they are a changin'",踊り回る女の子達は…"I'll Feel A Whole Lot Better" かな?
残念ながら、ザ・スタンズはアルバムをもう一枚発表しただけで、解散してしまった。ある人が言うには、こういうサウンドの若いバンドが、そうそう長く稼ぎまくれるような時代ではないとのこと。その辺りはよく分からない。それでも、ザ・スタンズは [All Years Leaving] を残しただけで、十分の成功と功績だったと思うのだ。
リヴァプール出身の四人組。ビートルズやザ・バーズを彷彿とさせるサウンドは、レトロで、でも瑞々しく、キラキラと煌めいていた。それで話題にならない方がどうかしている。なんでも、ノエル・ギャラガーが絶賛したとのことだが、とにかくそのアルバムは買ったし、その評価は当然だと思った。録音は、一部アビー・ロードで行ったらしい。
もっともヒットしたシングルが、"Here She Comes Again"。まさに、狙いすましたサウンド、メロディ、コーラス、そしてプロモーション・ビデオ!ポチっとすれば、YouTubeで見られるってさ。
こうして見るとこのバンド、容姿もなかなか揃っている方では無いだろうか(基準がビートルズというべらぼうに高い所にあるので、大抵のバンドは分が悪い)。うつむいているけど、ベースの彼とかちょっと格好良いし、何と言っても、リッケンバッカーを抱えたギターが可愛い!ポイント高し!
正真正銘、バーズを狙っていて、ここまで爽やかに、鮮やかに、ど真ん中を射貫かれると、もう気持ち良いとしか言いようがない。実際、この曲は名曲だと思うし、たびたび繰り返し聞きたくなる。
ビデオのセッティングももちろんバーズの真似。ハンター・ガールズに囲まれているのは、"The times they are a changin'",踊り回る女の子達は…"I'll Feel A Whole Lot Better" かな?
残念ながら、ザ・スタンズはアルバムをもう一枚発表しただけで、解散してしまった。ある人が言うには、こういうサウンドの若いバンドが、そうそう長く稼ぎまくれるような時代ではないとのこと。その辺りはよく分からない。それでも、ザ・スタンズは [All Years Leaving] を残しただけで、十分の成功と功績だったと思うのだ。
The Good Die Young ― 2012/02/26 22:50
ジョージ・ハリスンの誕生日というのはやっかいなもので、二つの説がある。ともあれ、一応公式(?)には2月24日ということになっている。公式ページをのぞきに行ってみると、iPadアプリ,George Harrison Guitar Collection がフィーチャーされていた。
こちらのコマーシャル映像では、ばりばりリッケンバッカーを弾いているらしき、マイク・キャンベルの姿が。iPadは要らないのだが…ジョージとマイクは欲しい。
何となく動画を見ていたら。キース・リチャーズがジョージについて語っている動画あがった。…キースって何言っているか分からない(いや、キースじゃなくても分からないんだけど)。
とにかくジョージは優しくて良い奴で、キースの良い友達。ファーマー・ジョージはガーデニングに熱心で、息子は思わず「ジョージ」と呼んでしまうほどそっくり。
「いい奴に限って、早く死んでしまう。」
実際にそうなのかどうかは知らないが、ジョージのことを念頭に置くと、そう思えてしまう。
一方、同じくストーンズの同僚であるロニー・ウッドもジョージとはとても親しく、"Far East Man" は二人の共作ではなかっただろうか。
この演奏は、ゲストミュージシャンを交えてのものだが、これがなかなか格好良い。"Far East Man" はライブでしっとりと、美しく演奏すると、より映える。
こちらのコマーシャル映像では、ばりばりリッケンバッカーを弾いているらしき、マイク・キャンベルの姿が。iPadは要らないのだが…ジョージとマイクは欲しい。
何となく動画を見ていたら。キース・リチャーズがジョージについて語っている動画あがった。…キースって何言っているか分からない(いや、キースじゃなくても分からないんだけど)。
とにかくジョージは優しくて良い奴で、キースの良い友達。ファーマー・ジョージはガーデニングに熱心で、息子は思わず「ジョージ」と呼んでしまうほどそっくり。
「いい奴に限って、早く死んでしまう。」
実際にそうなのかどうかは知らないが、ジョージのことを念頭に置くと、そう思えてしまう。
一方、同じくストーンズの同僚であるロニー・ウッドもジョージとはとても親しく、"Far East Man" は二人の共作ではなかっただろうか。
この演奏は、ゲストミュージシャンを交えてのものだが、これがなかなか格好良い。"Far East Man" はライブでしっとりと、美しく演奏すると、より映える。
他人のそら似 2 / Jakob & Jimmy ― 2012/02/29 22:28
私は、テレビで日本のドラマを見ない。よほどの事情でもない限り見ない。歴史好きだが、歴史物のドラマも見ない。
一方で、UKやアメリカのクライム・ドラマや、コメディで興味があるものは見るし、好きになれば日本未発表でもDVDを取り寄せて見る。
アメリカの人気クライムドラマ[CSI]シリーズは、そういう「見る」ドラマの一つだ。もっとも、見やすいチャンネルで見やすい時間帯にやっていればだが。
先日、[CSI]オリジナル(ラス・ヴェガス)のシーズン3を見ていたら、あるエピソードの冒頭に、ザ・ウォールフラワーズ The Wallflowers が登場した。ジェイコブ・ディランのバンドだ。殺人現場になったホテルのカジノで演奏しているバンドという設定で、曲は "Everybody out of Water"。この動画は、[CSI] の動画にこの曲をかぶせたものだ。
この曲が収録されているアルバム,[Red Letter Days](2002)は、ウォールフラワーズ・ファンの友人(いや、ジェイコブ・ディラン・ファンだな)が言うには、「イカン!」なアルバムだそうだが、私は好きだ。適度にポップでロックでバンドで、曲の出来も良いと思う。むしろ、ジェイコブ・ディランのソロの方が、私には向いていない。
[CSI] にウォールフラワーズが登場したことに関して、どんな感想があるのかと思って適当にググッてみたら、質問箱に「CSIのエピソードの冒頭に出てきたアーチストと、曲を教えてください」というものがあった。ヒントとして、エピソードの番号と、アーチストの特徴が記されていたのだが…
「顔はジミー・ファロン似」
ジミー・ファロン?ジミー・ファロンッ?!もちろんジミー・ファロンは知っているが、ジェイコブと似ていると思ったことはなかった。ジェイコブは、ディラン様に似ているという認識が強すぎて、思いもよらなかったが…言われてみれば似ている!
物を投げられることを覚悟の上で言うが、確かにジミー・ファロンとジェイコブ・ディランは似ている!…ということで、短いがジミー・ファロンによる、ジェイコブ・ディランの物まね。
ごめん、笑った。似てるよ。
では、死ぬほど似ている、ジミー・ファロンによるディラン様の物まねで締めてもらいましょう!(ジェイコブはどこへ行った…)うつむき気味に歌って、時々ちらっと視線を上げるところもそっくり。大好き!
一方で、UKやアメリカのクライム・ドラマや、コメディで興味があるものは見るし、好きになれば日本未発表でもDVDを取り寄せて見る。
アメリカの人気クライムドラマ[CSI]シリーズは、そういう「見る」ドラマの一つだ。もっとも、見やすいチャンネルで見やすい時間帯にやっていればだが。
先日、[CSI]オリジナル(ラス・ヴェガス)のシーズン3を見ていたら、あるエピソードの冒頭に、ザ・ウォールフラワーズ The Wallflowers が登場した。ジェイコブ・ディランのバンドだ。殺人現場になったホテルのカジノで演奏しているバンドという設定で、曲は "Everybody out of Water"。この動画は、[CSI] の動画にこの曲をかぶせたものだ。
この曲が収録されているアルバム,[Red Letter Days](2002)は、ウォールフラワーズ・ファンの友人(いや、ジェイコブ・ディラン・ファンだな)が言うには、「イカン!」なアルバムだそうだが、私は好きだ。適度にポップでロックでバンドで、曲の出来も良いと思う。むしろ、ジェイコブ・ディランのソロの方が、私には向いていない。
[CSI] にウォールフラワーズが登場したことに関して、どんな感想があるのかと思って適当にググッてみたら、質問箱に「CSIのエピソードの冒頭に出てきたアーチストと、曲を教えてください」というものがあった。ヒントとして、エピソードの番号と、アーチストの特徴が記されていたのだが…
「顔はジミー・ファロン似」
ジミー・ファロン?ジミー・ファロンッ?!もちろんジミー・ファロンは知っているが、ジェイコブと似ていると思ったことはなかった。ジェイコブは、ディラン様に似ているという認識が強すぎて、思いもよらなかったが…言われてみれば似ている!
物を投げられることを覚悟の上で言うが、確かにジミー・ファロンとジェイコブ・ディランは似ている!…ということで、短いがジミー・ファロンによる、ジェイコブ・ディランの物まね。
ごめん、笑った。似てるよ。
では、死ぬほど似ている、ジミー・ファロンによるディラン様の物まねで締めてもらいましょう!(ジェイコブはどこへ行った…)うつむき気味に歌って、時々ちらっと視線を上げるところもそっくり。大好き!
最近のコメント