The Beatles in Netherlands ― 2025/05/17 19:05
速さは確かだが勝利に繋がらず苦戦するランド・ノリスが、たびたびセバスチャン・ベッテルからアドバイスを受けていると告白。その記事に踊るのは “メンター” の文字。セブはミックのメンタ―だともっぱら言われて「友達だ」と笑っていたが、ランドにとっては本当にメンターだろうなぁ。頑張れランド、助けてセブ…!
何なんだ、この私しか驚喜しないような話題は…
オランダといえば?
F1好きとしてはマックス・フェルスタッペンなのだろうが、いかんせん彼のファンではない。彼以外なら誰がチャンピオンになっても大歓迎。
チューリップのも風車にも興味はないが、絵画にはとても興味がある。そう、レンブラント、フェルメール、ゴッホ、ついでにブルーナ。
明日からアムステルダム5泊の旅に出る。目的はただただ、名画である。あとはボリスの夜景とナインチェのミルクメイド。クノールのシュパ―ゲル・スープ。以上!
クラシック音楽的には、オランダ黄金時代とクラシック音楽の古典派が時代的に合致していないせいか、とくに有名なものはない。ただ、中世〜ルネサンス期にはネーデルランド楽派といって、オランダやベルギーを中心に音楽が栄えたこともある。ともあれ、有名なクラシック音楽ではない。
ポピュラー・ミュージックでオランダというと、大スターが公演しに行きました!という話程度だろうか。
ビートルズはリンゴが病欠のときにアムステルダムを訪れており、運河を船で移動し、運河に面した高級ホテルの窓から手を振る様子が印象的だ。
うーん、やっぱりビートルズはリンゴがいなきゃビートルズじゃないなぁ。リンゴが行けないなら、自分も行かないとジョージが散々ごねたのもわかるというものだ。
何なんだ、この私しか驚喜しないような話題は…
オランダといえば?
F1好きとしてはマックス・フェルスタッペンなのだろうが、いかんせん彼のファンではない。彼以外なら誰がチャンピオンになっても大歓迎。
チューリップのも風車にも興味はないが、絵画にはとても興味がある。そう、レンブラント、フェルメール、ゴッホ、ついでにブルーナ。
明日からアムステルダム5泊の旅に出る。目的はただただ、名画である。あとはボリスの夜景とナインチェのミルクメイド。クノールのシュパ―ゲル・スープ。以上!
クラシック音楽的には、オランダ黄金時代とクラシック音楽の古典派が時代的に合致していないせいか、とくに有名なものはない。ただ、中世〜ルネサンス期にはネーデルランド楽派といって、オランダやベルギーを中心に音楽が栄えたこともある。ともあれ、有名なクラシック音楽ではない。
ポピュラー・ミュージックでオランダというと、大スターが公演しに行きました!という話程度だろうか。
ビートルズはリンゴが病欠のときにアムステルダムを訪れており、運河を船で移動し、運河に面した高級ホテルの窓から手を振る様子が印象的だ。
うーん、やっぱりビートルズはリンゴがいなきゃビートルズじゃないなぁ。リンゴが行けないなら、自分も行かないとジョージが散々ごねたのもわかるというものだ。
The Beginning of Folk Rock ― 2025/05/10 21:19
先週、マイク・キャンベルの自伝 [A Memoir Heartbreaker] が届いたので、まずは面白そうなところから拾い読みしている。
総じて文章は読みやすい。話がわかりやすいところもトムさんに似ているのか。そしてけっこう表現がロマンチックで胸が熱くなることがある。彼の生涯で重要な人物に出会うシーンなどは特に顕著だ。どうもマイクは一目惚れするタイプらしい。しかも的確に惚れる。トムさんとジョージに出会うシーンは本当に一目で落ちている。
だれでもその本の締めくくりがどうなっているのかは気になるところで、私もその例外ではない。やっぱりトムさんとのエピソードで締めるのかと思ったら…違った。違うんかい!と思わずツッコミを入れたくなるほど、鮮やかな違い。しかも私がキャーキャー言って喜ぶ人とのエピソードなのだから。マイク先生、最高です。
先週なんとなくピーター・バラカンさんのラジオを聞いていたら、告知で「1965年ニューポート・フォーク・フェスティバルでボブ・ディランがエレキを持ってステージに立った『出来事』をフォーク・ロックの始まりとして、その後の展開を語る」と言っていた。おお、面白そう。私も聞きたいが、どこか遠方でとっくに予約で埋まっているような話だった。
それにしても、気になったのは「フォーク・ロック」の始まりである。果たして1965年7月で良いのだろうか。
そもそもフォーク・ロックとは、ウディ・ガスリー、ピート・シーガー、そしてボブ・ディランに代表されるモダン・フォークとビートルズに代表されるロックンロール(アメリカで誕生した元祖『ロックンロール』よりもUKで洗練されたそれ)の音楽要素が融合したものだといって間違いはないだろう。
そもそも、ロックになにか別の音楽ジャンルの要素が加わると安易に「なんとかロック」と名付けすぎである。「カンタータ・ロック」とか、「ラーガ・ロック」とか。特に音大では不評だった。
ただ、フォーク・ロックだけはそのジャンルが確立され、継承され、今も続いている。ロックのジャンルのなかでも「強い」方だろう。
Wikipedia を見ると、1965年4月にリリースされたザ・バーズの “Mr. Tambourine Man” をもってフォーク・ロックの始まりとしている。私もこちらの説に同意だ。
YouTube を検索したら、ザ・ダーティ・ノブズによる “Mr. Tambourine Man” というものがあって、ちょっと怖いけどけっこう良かった。途中でコードが怪しくなるのは御愛嬌。
マイクの自伝で、ロジャー・マッグインに初めて会うところはまだ読んでいない。そもそもハートブレイカーズが初めてザ・バーズ関連の人に会うのはいつなのだろう?そろそろ拾い読みはやめて最初から読むことにするか。
総じて文章は読みやすい。話がわかりやすいところもトムさんに似ているのか。そしてけっこう表現がロマンチックで胸が熱くなることがある。彼の生涯で重要な人物に出会うシーンなどは特に顕著だ。どうもマイクは一目惚れするタイプらしい。しかも的確に惚れる。トムさんとジョージに出会うシーンは本当に一目で落ちている。
だれでもその本の締めくくりがどうなっているのかは気になるところで、私もその例外ではない。やっぱりトムさんとのエピソードで締めるのかと思ったら…違った。違うんかい!と思わずツッコミを入れたくなるほど、鮮やかな違い。しかも私がキャーキャー言って喜ぶ人とのエピソードなのだから。マイク先生、最高です。
先週なんとなくピーター・バラカンさんのラジオを聞いていたら、告知で「1965年ニューポート・フォーク・フェスティバルでボブ・ディランがエレキを持ってステージに立った『出来事』をフォーク・ロックの始まりとして、その後の展開を語る」と言っていた。おお、面白そう。私も聞きたいが、どこか遠方でとっくに予約で埋まっているような話だった。
それにしても、気になったのは「フォーク・ロック」の始まりである。果たして1965年7月で良いのだろうか。
そもそもフォーク・ロックとは、ウディ・ガスリー、ピート・シーガー、そしてボブ・ディランに代表されるモダン・フォークとビートルズに代表されるロックンロール(アメリカで誕生した元祖『ロックンロール』よりもUKで洗練されたそれ)の音楽要素が融合したものだといって間違いはないだろう。
そもそも、ロックになにか別の音楽ジャンルの要素が加わると安易に「なんとかロック」と名付けすぎである。「カンタータ・ロック」とか、「ラーガ・ロック」とか。特に音大では不評だった。
ただ、フォーク・ロックだけはそのジャンルが確立され、継承され、今も続いている。ロックのジャンルのなかでも「強い」方だろう。
Wikipedia を見ると、1965年4月にリリースされたザ・バーズの “Mr. Tambourine Man” をもってフォーク・ロックの始まりとしている。私もこちらの説に同意だ。
YouTube を検索したら、ザ・ダーティ・ノブズによる “Mr. Tambourine Man” というものがあって、ちょっと怖いけどけっこう良かった。途中でコードが怪しくなるのは御愛嬌。
マイクの自伝で、ロジャー・マッグインに初めて会うところはまだ読んでいない。そもそもハートブレイカーズが初めてザ・バーズ関連の人に会うのはいつなのだろう?そろそろ拾い読みはやめて最初から読むことにするか。
Mike Campbell Red Dog Telecaster ― 2025/04/15 20:35
フェンダーから、マイク・キャンベルのシグネチャー・モデルが発売された。マイクがキャリアのごく初期に購入し、”Refegee” のシンボリックなリードギター・サウンドを奏でたテレキャスター “Red Dog” である。
話によると、マイクがギターを教えていた生徒から買い取ったのがこのテレキャスターだったとのこと。どうやらマイクというのは良いギターを引き寄せる独特の引力を持っていたようだ。
マイクがいろいろとこのギターについて説明してくれるのだが、どうやらギミックの多いギターのようだ。それから、いくらか傷がついているのだが、マイクに言わせると「トムか誰かがやったんだろうけど、たぶんトムだ。」― ファイヤーバードのときもそうだったが、マイクのギターを壊すか傷をつける化するのは、たいていトムさんということになっている。本当にトムさんがうっかりものなのか、マイクが言いたい放題なのか…?
そもそも、どうしてマイクのギターをトムさんが傷つけるのかと言えば、マイク所有のギターをトムさんが ― さも自分のものであるかのように ― 弾くからだ。この二人のギタリスト、しかもリードギタリストと、メインヴォーカリストが同じギターを弾くということは、実は珍しいのではないだろうか。他のバンドでそういう例をきいたことがない。兄弟のバンドならともかく…売れた兄弟バンドはたいてい仲が悪いし。
ともあれ、マイクのギターは当たり前のようにトムさんも弾く。そういう二人が好きだ。
トムさんが Red Dog を弾いているシーンは、1977年ドイツのテレビ番組 Rockplastで登場する。
Heartbreaker’s Japan Party さんによると、すでにマイクの自伝が届いているとのこと?ええ?!私も注文したのに、全然来ていない!公式ホームページで申し込んだ気がしたのだが…ヤケクソになったので、あらためてアマゾンで注文してしまった。
二冊来ればそれはそれまでだ!
話によると、マイクがギターを教えていた生徒から買い取ったのがこのテレキャスターだったとのこと。どうやらマイクというのは良いギターを引き寄せる独特の引力を持っていたようだ。
マイクがいろいろとこのギターについて説明してくれるのだが、どうやらギミックの多いギターのようだ。それから、いくらか傷がついているのだが、マイクに言わせると「トムか誰かがやったんだろうけど、たぶんトムだ。」― ファイヤーバードのときもそうだったが、マイクのギターを壊すか傷をつける化するのは、たいていトムさんということになっている。本当にトムさんがうっかりものなのか、マイクが言いたい放題なのか…?
そもそも、どうしてマイクのギターをトムさんが傷つけるのかと言えば、マイク所有のギターをトムさんが ― さも自分のものであるかのように ― 弾くからだ。この二人のギタリスト、しかもリードギタリストと、メインヴォーカリストが同じギターを弾くということは、実は珍しいのではないだろうか。他のバンドでそういう例をきいたことがない。兄弟のバンドならともかく…売れた兄弟バンドはたいてい仲が悪いし。
ともあれ、マイクのギターは当たり前のようにトムさんも弾く。そういう二人が好きだ。
トムさんが Red Dog を弾いているシーンは、1977年ドイツのテレビ番組 Rockplastで登場する。
Heartbreaker’s Japan Party さんによると、すでにマイクの自伝が届いているとのこと?ええ?!私も注文したのに、全然来ていない!公式ホームページで申し込んだ気がしたのだが…ヤケクソになったので、あらためてアマゾンで注文してしまった。
二冊来ればそれはそれまでだ!
Father & Son ― 2025/04/08 21:05
トム・オデールというシンガーソングライターが好きなのだが、最近の作品はちょっと勢いがない。
デビューから3作品続けて素晴らしいアルバムを発表したのだが、4枚目、5枚目はすっかり作風が変わってしまい、心配になるくらいだ。鬱々とした曲調が続いて、平坦で起伏がなく、パンチが利いていない。具合でも悪いのかと心配になったが、どうやらインタビューを見る限り、こどもを取り巻く問題に心痛めている様子。共感は大事だが、自分は大事にしてほしい。
ライブはどうなんだろうと思って検索すると、去年の夏フェスに出演していた。元気そうで結構。トム・オデールって、ソングライティングの才能も好きだし、苦しそうな歌い方もトムさんに似ていて好きだし、そして顔立ちがセバスチャン・ベッテルに似ているところが大好きだ。サングラスをかけるとさらに似ていて、ニヤつきが止まらない。
これだったらライブを見に行ってもいいなぁ…トムさん亡き今。そしてELOも見た今。海外まで見に行きたいアーチストは、ディラン様、ストーンズ…そういえばシスター・ヘイゼルって見たことがない。あとはマイク・キャンベル&ザ・ダーティ・ノブズ。そしてトム・オデールかもしれない。
動画サイトを見ていたら、トム・オデールとキャット・スティーヴンス(ユスフ・イスラム)の共演があった。スティーヴンスのヒット曲 ”Father & Son” をデュエットしているものだ。
オリジナルは、父親と息子のパートをスティーヴンスが歌い分ける曲だが、ここでは二人が最初のうち役割分担をしている。かといってずっとスティーヴンスが父親でオデールが息子かというと、そうでもなくてだんだん絡まっていく様子がさらに良い。
もともと、トム・オデールのこの苦しそうで切なそうな雰囲気が好きなのだ。鬱情も、その構成要素のひとつで、今はそれが全面に出てくる時期なのかもしれない。彼のアルバムは聞き続けて、また威勢がよくて輝くような曲調を見せてくれるといいなと思う。
デビューから3作品続けて素晴らしいアルバムを発表したのだが、4枚目、5枚目はすっかり作風が変わってしまい、心配になるくらいだ。鬱々とした曲調が続いて、平坦で起伏がなく、パンチが利いていない。具合でも悪いのかと心配になったが、どうやらインタビューを見る限り、こどもを取り巻く問題に心痛めている様子。共感は大事だが、自分は大事にしてほしい。
ライブはどうなんだろうと思って検索すると、去年の夏フェスに出演していた。元気そうで結構。トム・オデールって、ソングライティングの才能も好きだし、苦しそうな歌い方もトムさんに似ていて好きだし、そして顔立ちがセバスチャン・ベッテルに似ているところが大好きだ。サングラスをかけるとさらに似ていて、ニヤつきが止まらない。
これだったらライブを見に行ってもいいなぁ…トムさん亡き今。そしてELOも見た今。海外まで見に行きたいアーチストは、ディラン様、ストーンズ…そういえばシスター・ヘイゼルって見たことがない。あとはマイク・キャンベル&ザ・ダーティ・ノブズ。そしてトム・オデールかもしれない。
動画サイトを見ていたら、トム・オデールとキャット・スティーヴンス(ユスフ・イスラム)の共演があった。スティーヴンスのヒット曲 ”Father & Son” をデュエットしているものだ。
オリジナルは、父親と息子のパートをスティーヴンスが歌い分ける曲だが、ここでは二人が最初のうち役割分担をしている。かといってずっとスティーヴンスが父親でオデールが息子かというと、そうでもなくてだんだん絡まっていく様子がさらに良い。
もともと、トム・オデールのこの苦しそうで切なそうな雰囲気が好きなのだ。鬱情も、その構成要素のひとつで、今はそれが全面に出てくる時期なのかもしれない。彼のアルバムは聞き続けて、また威勢がよくて輝くような曲調を見せてくれるといいなと思う。
The Beatles F1 Racing Is Comming! ― 2025/04/01 00:00
このたびビートルズ・F1 レーシングが、F1 グランプリに参戦することが発表された。2027年からフル参戦予定。シャシー、エンジンともに自ら手がけるワークスチームだ。
チーム・オーナーはビートルズのメンバーとその遺族、および管理会社のアップル。スポンサーにはギブスン、フェンダー、リッケンバッカー、グレッチ、ヘフナー、ラディック、その他多数の楽器メーカーなどが名を連ねている。
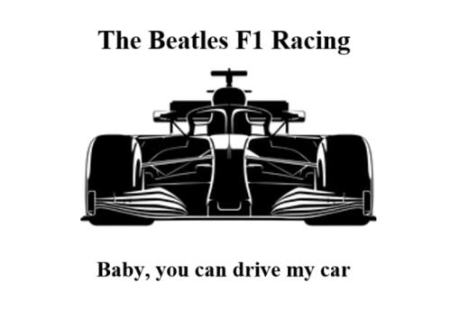
チーム代表はゲルハルト・ベルガー、顧問にデイモン・ヒル。広報にダニー・ハリスン。チーフエンジニア兼、ファースト・ドライバーとして、ゼバスティアン・フェテルの現役復帰が決定している。
当初ファクトリーはリヴァプールに新設することが検討されたが、初期設備費用投資額の評価から判断し、初年はマンチェスターに置かれる。デザイナー、エンジニア、メカニックの多くは、ジョージ・ハリスンが太いパイプを持っていたウイリアムズ、マクラーレン、ジョーダン、スチュワートなどの OBおよび研修生などが名を連ねている。
ビートルズ・F1レーシングはその豊富な資金力から、現在 F1 サーカスの中心で働いている有能なストラテジストを引き抜くのではないかと噂されている。少なくとも、適切なタイミングで適切なタイヤ交換作戦を立てることが必須だ。
ドライバーの人選に関しては経験豊富なフェテルが決まっている一方、もう一人は若手を起用すると言われている。ただし、トラック・リミットを逸脱するドライバーだけは絶対に採用しないと、パドックではもっぱらの噂だ。
ベルガーは「トラック・リミット内で走る限り、クラッシュしないから」とその理由を述べている。
また、地球温暖化とそれに伴う異常気象への関心の高いフェテルは、雨のレースがさらに増えると予想している。その上で、「雨の」タイトルの付く人材には積極的に声が掛かっているとみられる。このため、サトル・ナカジマのビートルズ・F1レーシング入りは秒読み段階だと言われている。
昨年から、F1 勢力図は大きく変わりつつある。この新しいワークスチームの参戦は、さらなる混戦激化を生むのか、パドックの人々の思惑は、早くも2027年へと向いている。
(2025年4月1日 ドイツ「 ディー・リューゲ・モーターシュポルト」誌)
チーム・オーナーはビートルズのメンバーとその遺族、および管理会社のアップル。スポンサーにはギブスン、フェンダー、リッケンバッカー、グレッチ、ヘフナー、ラディック、その他多数の楽器メーカーなどが名を連ねている。
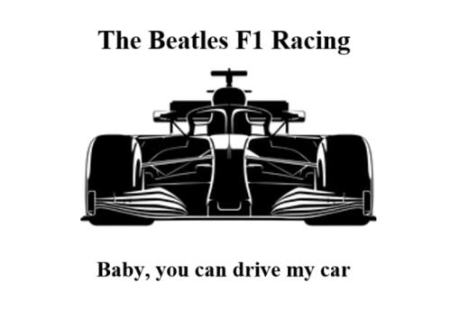
チーム代表はゲルハルト・ベルガー、顧問にデイモン・ヒル。広報にダニー・ハリスン。チーフエンジニア兼、ファースト・ドライバーとして、ゼバスティアン・フェテルの現役復帰が決定している。
当初ファクトリーはリヴァプールに新設することが検討されたが、初期設備費用投資額の評価から判断し、初年はマンチェスターに置かれる。デザイナー、エンジニア、メカニックの多くは、ジョージ・ハリスンが太いパイプを持っていたウイリアムズ、マクラーレン、ジョーダン、スチュワートなどの OBおよび研修生などが名を連ねている。
ビートルズ・F1レーシングはその豊富な資金力から、現在 F1 サーカスの中心で働いている有能なストラテジストを引き抜くのではないかと噂されている。少なくとも、適切なタイミングで適切なタイヤ交換作戦を立てることが必須だ。
ドライバーの人選に関しては経験豊富なフェテルが決まっている一方、もう一人は若手を起用すると言われている。ただし、トラック・リミットを逸脱するドライバーだけは絶対に採用しないと、パドックではもっぱらの噂だ。
ベルガーは「トラック・リミット内で走る限り、クラッシュしないから」とその理由を述べている。
また、地球温暖化とそれに伴う異常気象への関心の高いフェテルは、雨のレースがさらに増えると予想している。その上で、「雨の」タイトルの付く人材には積極的に声が掛かっているとみられる。このため、サトル・ナカジマのビートルズ・F1レーシング入りは秒読み段階だと言われている。
昨年から、F1 勢力図は大きく変わりつつある。この新しいワークスチームの参戦は、さらなる混戦激化を生むのか、パドックの人々の思惑は、早くも2027年へと向いている。
(2025年4月1日 ドイツ「 ディー・リューゲ・モーターシュポルト」誌)
Taxman with Mike Campbell (1992) ― 2025/03/29 15:34
まさかまさかと思っていたら、あれよあれよという間に、本当にレッドブルのローソンと角田がスワップされてしまった。しかも角田くんのレッドブル初戦が鈴鹿という…!これはとんでもないことになった。普段、フリー走行は見ないのだが、今度の鈴鹿ばかりはフリー走行1回目から見なければ…!
フィギュアスケートは、女子のトップ選手がショートで総崩れしてしまった。まぁ、そういうこともある。大事なのはリカバリーである。そもそも、この大会はアメリカのための大会という観がなくもない。
ジョージが最後にオーディエンスを前にしたライブを行ったのは、1992年のロイヤル・アルバート・ホールであり、バンドはクラプトンから借りた「ハイジャック・バンド」であることも有名だ。
さらに重要なのは、このときマイク・キャンベルがハートブレイカーズのツアーでロンドンにおり、ジョージに電話一本で呼び出されてクラプトンの代役を務めたことだ。マイクにとっては憧れのスターとの夢の共演である。さらに、このとき初めてマイクはスティーヴ・フェローニという超優秀なドラマーを知り、彼がハートブレイカーズに加入するきっかけにもなった。
この大事なライブの映像というのは公式には残っておらず、オーディエンス撮影の断片があるばかりだ。残念な限り。
ところがこのたび、どうやらテレビクルーが撮ったらしき、リハーサルの動画を見つけた。”Taxman” の演奏の様子だ。
まずそのクリアな映像に驚かされる。これ、もっとないのだろうか?!
リッケンバッカーを携えたマイク登場。頭髪がこれでもかと爆発している。ジョージがマイクと話すと…近い!顔が近い!ジョージ特有の距離感である。背後ではスティーヴ(若い!)がレイ・クーパーと談笑している様子も見える。この金髪のベーシストは誰だろうな?ネイサン・イーストではなかったのだろうか?
マイクのギターソロはやっぱり冴えているし、原曲よりも長い。かと言って出しゃばりもしない。[Concert for George] へのつながり思うと感慨深いものがある。
この映像があまりにも良いので、本当に他にないのかと期待してしまう。特に “While My Guitar Gently Weeps” とか。マイクがギター・ソロを聴かせてくれるのでは?ジョージとのツインリードの絡みを見せてくれるのでは?どこからか現れるのを待っている。
フィギュアスケートは、女子のトップ選手がショートで総崩れしてしまった。まぁ、そういうこともある。大事なのはリカバリーである。そもそも、この大会はアメリカのための大会という観がなくもない。
ジョージが最後にオーディエンスを前にしたライブを行ったのは、1992年のロイヤル・アルバート・ホールであり、バンドはクラプトンから借りた「ハイジャック・バンド」であることも有名だ。
さらに重要なのは、このときマイク・キャンベルがハートブレイカーズのツアーでロンドンにおり、ジョージに電話一本で呼び出されてクラプトンの代役を務めたことだ。マイクにとっては憧れのスターとの夢の共演である。さらに、このとき初めてマイクはスティーヴ・フェローニという超優秀なドラマーを知り、彼がハートブレイカーズに加入するきっかけにもなった。
この大事なライブの映像というのは公式には残っておらず、オーディエンス撮影の断片があるばかりだ。残念な限り。
ところがこのたび、どうやらテレビクルーが撮ったらしき、リハーサルの動画を見つけた。”Taxman” の演奏の様子だ。
まずそのクリアな映像に驚かされる。これ、もっとないのだろうか?!
リッケンバッカーを携えたマイク登場。頭髪がこれでもかと爆発している。ジョージがマイクと話すと…近い!顔が近い!ジョージ特有の距離感である。背後ではスティーヴ(若い!)がレイ・クーパーと談笑している様子も見える。この金髪のベーシストは誰だろうな?ネイサン・イーストではなかったのだろうか?
マイクのギターソロはやっぱり冴えているし、原曲よりも長い。かと言って出しゃばりもしない。[Concert for George] へのつながり思うと感慨深いものがある。
この映像があまりにも良いので、本当に他にないのかと期待してしまう。特に “While My Guitar Gently Weeps” とか。マイクがギター・ソロを聴かせてくれるのでは?ジョージとのツインリードの絡みを見せてくれるのでは?どこからか現れるのを待っている。
Eddie Jordan ― 2025/03/23 21:54
ついこの間シーズンが終わったと思ったのも束の間、早くもF1 の2025年シーズンが始まった。アマチュアとプロの野球(日米)、そしてフィギュアスケートと、スポーツ観戦的に最も忙しくなる時期だ。
開幕早々、 Back to Back で、しかもスプリント・フォーマット、雨も相まって早くもドラマが頻発している。どうしてルイスのお父さんはハジャーを慰めるに至ったのかなぁ?通りすがり?なにか関係があるのだろうか。
レッドブルのセカンド・ドライバーについては、早くも意見が噴出しているようだが、角田くんにはレッドブルみたいな難しいチームでプレッシャーに潰されるよりは、伸び伸びと走ってほしいと思う。でも万が一、本当に乗せててみたらもしかして…?という、複雑な心境だ。私個人としてはレーシング・ブルズで優勝して、セバスチャンが会長を務める「トロロッソ優勝者の会」に加入してほしいなぁ。もう一人のメンバーは親友のガスリーだし。
ともあれ、去年からマックスしか勝てないマシンを作ってしまっているチームには、必ず何等かの問題がある。フォーミュラカーなのだから、ドライバーによってあそこまで大きな差が出るのはおかしいだろう。ローソンだって去年11戦走っているのだから、彼だけを責めらないだろう。
ルーキーの多い年だが、気になるのは多くの人と同じく、アントネッリ。まだキャラクターは掴めていないが(なにせラジオが聞けない)、とても長い目で見て、将来的にイタリア人ドライバーがフェラーリでチャンピオンに…?なんて楽しい想像が膨らんでいる。
そんな中、訃報が届いた。エディ・ジョーダンが亡くなったという。私にとっては、ジョーダン・グランプリの人で、好きなドライバーも何人か走っていた。1998年、雨のスパ・フランコルシャンでのワン・トゥー・フィニッシュは忘れられない。あれがデイモン・ヒルにとって最後の優勝レースとなった。
川井ちゃんも言っていたが、エディは明るくて楽しい人だった。私がF1 を見始めた頃に、英国流(もっとも彼はダブリン出身のアイルランド人。アイルランドも紅茶の消費量が多い)の紅茶の入れ方講座をやっていて、大好きになった。イタリア人のアンドレア・デ・チェザリス(故人。通称走る障害物)を従えて、「沸騰したお湯が重要です!あくまでも完全に沸騰したお湯です!イタリア人はそこを理解していません!」
これまた川井ちゃん情報で、ドラマーでもあり、Pit Stop Boys なるバンドを組んで演奏を披露することもあったそうだ。ちなみにその名前で今検索すると、マックスの追っかけおじさんたちがヒットする。
何を演奏するのか…?そりゃぁ、ストーンズで決まりでしょ!どうやらマクラーレンのヴィジター・ルームらしい。ルイスやバトンが乗っていた頃のマシンが置いてあるのかな?天国から今年のレースの安全と良い勝負を見守っていてほしい。
開幕早々、 Back to Back で、しかもスプリント・フォーマット、雨も相まって早くもドラマが頻発している。どうしてルイスのお父さんはハジャーを慰めるに至ったのかなぁ?通りすがり?なにか関係があるのだろうか。
レッドブルのセカンド・ドライバーについては、早くも意見が噴出しているようだが、角田くんにはレッドブルみたいな難しいチームでプレッシャーに潰されるよりは、伸び伸びと走ってほしいと思う。でも万が一、本当に乗せててみたらもしかして…?という、複雑な心境だ。私個人としてはレーシング・ブルズで優勝して、セバスチャンが会長を務める「トロロッソ優勝者の会」に加入してほしいなぁ。もう一人のメンバーは親友のガスリーだし。
ともあれ、去年からマックスしか勝てないマシンを作ってしまっているチームには、必ず何等かの問題がある。フォーミュラカーなのだから、ドライバーによってあそこまで大きな差が出るのはおかしいだろう。ローソンだって去年11戦走っているのだから、彼だけを責めらないだろう。
ルーキーの多い年だが、気になるのは多くの人と同じく、アントネッリ。まだキャラクターは掴めていないが(なにせラジオが聞けない)、とても長い目で見て、将来的にイタリア人ドライバーがフェラーリでチャンピオンに…?なんて楽しい想像が膨らんでいる。
そんな中、訃報が届いた。エディ・ジョーダンが亡くなったという。私にとっては、ジョーダン・グランプリの人で、好きなドライバーも何人か走っていた。1998年、雨のスパ・フランコルシャンでのワン・トゥー・フィニッシュは忘れられない。あれがデイモン・ヒルにとって最後の優勝レースとなった。
川井ちゃんも言っていたが、エディは明るくて楽しい人だった。私がF1 を見始めた頃に、英国流(もっとも彼はダブリン出身のアイルランド人。アイルランドも紅茶の消費量が多い)の紅茶の入れ方講座をやっていて、大好きになった。イタリア人のアンドレア・デ・チェザリス(故人。通称走る障害物)を従えて、「沸騰したお湯が重要です!あくまでも完全に沸騰したお湯です!イタリア人はそこを理解していません!」
これまた川井ちゃん情報で、ドラマーでもあり、Pit Stop Boys なるバンドを組んで演奏を披露することもあったそうだ。ちなみにその名前で今検索すると、マックスの追っかけおじさんたちがヒットする。
何を演奏するのか…?そりゃぁ、ストーンズで決まりでしょ!どうやらマクラーレンのヴィジター・ルームらしい。ルイスやバトンが乗っていた頃のマシンが置いてあるのかな?天国から今年のレースの安全と良い勝負を見守っていてほしい。
Written by Benmont Tench ― 2025/03/16 21:32
いつもお世話になっている Heatbreaker’s Japan Party さんのメール・マガジンによると、いよいよベンモント・テンチの二枚目のソロ・アルバムが発表されたそうだ。
CD がほしいので、アメリカのサイトから購入。届くのを待っている。
メルマガによると、ベンモントはここ10年ほどガンとの闘病が続いているとのこと。2023年には顎に転移して去年、大きな手術を受けたとのこと。たしかに最近のベンモントの映像は痩せて、元気のない感じで心配していたのだ。やはり大病をしていたのか…とても心配だが、ゆっくりと自分のペースで養生して、好きに音楽活動を続けてほしい。
ベンモントのソロ・アルバムとなると彼のソングライティングを堪能することができるわけだ。
あらためて確認してみたのだが、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの楽曲でソングライティングにベンモントの名前がある曲はほとんどない。やはりトムさんか、トムさんとマイクのソングライティングがこのバンドのレパートリーだったということだ。
だれか他の人にベンモントが提供している曲はないかを探してみると、これまたあまり多くはない。
こちらはアイルランドの Feargal Sharkey という人に提供した “You Little Thief” という曲とのこと。どうやらベンモントはプロデュースにも関わっているそうだ。80年代大爆発。肩の関節が抜けそうなくらいの力のは入りようで、ついでに血管も切れそうだ。もう少しリラックスしても良いのでは…?
ベンモントは彼の1枚目のアルバムの印象では、大人しく優しい感じが似合うと思う。その点、80年代のバッキバキな気合はやや空振りではないだろうか。
その点、こちらの Hal Ketchumという人に提供した”Stay Forever“ という曲は終始穏やかで良いではないか。
それにしても、どうしてベンモントは曲を提供したこの二人は揃いも揃って顔が大きめ、かつ四角いのだろうか…?
ベンモントのソロ・アルバムは2014年以来、11年ぶりだ。その間いろいろなことがあった。悲しいこと、嬉しいこと、苦しいこと、心癒されること。それらを経て、彼のソングライティングがどうなっているのか、ピアノプレイや歌声はどうなっているのか。ディスクが届くのがとても楽しみだ。
CD がほしいので、アメリカのサイトから購入。届くのを待っている。
メルマガによると、ベンモントはここ10年ほどガンとの闘病が続いているとのこと。2023年には顎に転移して去年、大きな手術を受けたとのこと。たしかに最近のベンモントの映像は痩せて、元気のない感じで心配していたのだ。やはり大病をしていたのか…とても心配だが、ゆっくりと自分のペースで養生して、好きに音楽活動を続けてほしい。
ベンモントのソロ・アルバムとなると彼のソングライティングを堪能することができるわけだ。
あらためて確認してみたのだが、トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの楽曲でソングライティングにベンモントの名前がある曲はほとんどない。やはりトムさんか、トムさんとマイクのソングライティングがこのバンドのレパートリーだったということだ。
だれか他の人にベンモントが提供している曲はないかを探してみると、これまたあまり多くはない。
こちらはアイルランドの Feargal Sharkey という人に提供した “You Little Thief” という曲とのこと。どうやらベンモントはプロデュースにも関わっているそうだ。80年代大爆発。肩の関節が抜けそうなくらいの力のは入りようで、ついでに血管も切れそうだ。もう少しリラックスしても良いのでは…?
ベンモントは彼の1枚目のアルバムの印象では、大人しく優しい感じが似合うと思う。その点、80年代のバッキバキな気合はやや空振りではないだろうか。
その点、こちらの Hal Ketchumという人に提供した”Stay Forever“ という曲は終始穏やかで良いではないか。
それにしても、どうしてベンモントは曲を提供したこの二人は揃いも揃って顔が大きめ、かつ四角いのだろうか…?
ベンモントのソロ・アルバムは2014年以来、11年ぶりだ。その間いろいろなことがあった。悲しいこと、嬉しいこと、苦しいこと、心癒されること。それらを経て、彼のソングライティングがどうなっているのか、ピアノプレイや歌声はどうなっているのか。ディスクが届くのがとても楽しみだ。
1964 Concert at Philharmonic Hall ― 2025/03/10 20:04
ボブ・ディランの伝記映画 [A COMPLETE UNKNOWN] を見る気はないし、サントラも聞く気がなかったのだが、ラジオで流れたため、はからずも聞くことになった。
大まかに言って、ティモシー・シャラメは上手いと思う。歌そのものが上手いし、ディランの真似としても上手い。ギターはどこまで彼が弾いた音なのかはわからないが。ともあれ、ディランを演じる歌唱としては、十分なクオリティだと思う。
ただ、似ているだけに、微妙に「かゆい」。気持ち悪いというか、不完全さに苛ついてしまう。やはり私はボブ・ディラン当人のファンであり、彼の容姿も声も、彼自身だからこその、大ファンということを再度認識するに至った。
「かゆみ」を鎮めるには、ディラン様本人のパフォーマンスを耳から叩き込むに限る。
「かゆみ」を発症したのはだいたい1964年頃のディランの真似だったので、ブートレグ・シリーズ Vol. 6 [Concert at Philharmonic Hall] がちょうどいい。
このコンサートと一番好きな場面は、” I Don't Believe You” の歌いだしの歌詞を忘れてしまい、イントロを長々と弾き続け、ああでもない、こうでもない。しまいには観客に「歌詞分かる人?」と呼びかけ、客先から教えてもらい、「そうだ、I can’t understand …」と歌い出すところだ。
トラックの切れ目の関係で、このやり取りはその前の曲 ”It's alright ma (I'm Only Bleeding)” の最後に聞くことができる。ところが、YouTube(静止画だが)だと、観客とのやりとりがまるっきり切り取られているのだ。つまり、あの面白いやりとりを聞くには、CDを買うしかない…のか?配信やダウンロードではこういうものは、どうなっているのかよくわからない。もしオミットされているのだとしたら、とんでもなくつまらない話だ。やはり私は CD を買い続けるだろう。
ラジオで流れた例の映画のサウンドトラックの中には、ジョーン・バエズとのデュエットもも含まれていた。彼女を演じた女優の歌もうまいし、ジョーン・バエズの真似もうまい。しかし、これまた「かゆい」。シャラメと合わせて二倍「かゆい」ので、やはりこれも特効薬は本物を聞くことだ。
このデュエットでも歌詞に怪しいところがあって、二人でボソボソ相談しているのが面白い。幸い演奏中のやりとりなので、オミットされていない。「そっちの番なんだけど」、「なんだっけ?」「when」とバエズがいった途端に間髪入れずに歌い出すディランのタイミングも最高だ。
ディランの長いキャリアの中で、60年代こそが最重要で映画にする価値があるというのが一般の認識だろうか。しかし、私にとっては長い長い彼のキャリア全般が素晴らしい音楽であり、性格に難のある「若気の至り」ではなくなってからの彼も、十分魅力的だ。
私がプロデューサーだったら、ディラン様とジョージの友情物語の映画を作るなぁ。そりゃぁ、もちろん漏れなくトムさんも重要人物になるわけだけど。ラストシーンはディンによる “Something” で間違いないだろう。
本人じゃないから気持ちが悪いと言いつつも、こういうことを想像するのは、この手の映画に一定の「布教活動」的な目論見があるからだろう。私にしてみれば60年代のディランにも、ビートルズにもいまさら布教活動は無用だが、ウイルベリー兄弟の物語や、ハートブレイカーズをたくさんの人に知ってもらうには、「モノマネ大会映画」も一つの手段かもしれないと思う。
大まかに言って、ティモシー・シャラメは上手いと思う。歌そのものが上手いし、ディランの真似としても上手い。ギターはどこまで彼が弾いた音なのかはわからないが。ともあれ、ディランを演じる歌唱としては、十分なクオリティだと思う。
ただ、似ているだけに、微妙に「かゆい」。気持ち悪いというか、不完全さに苛ついてしまう。やはり私はボブ・ディラン当人のファンであり、彼の容姿も声も、彼自身だからこその、大ファンということを再度認識するに至った。
「かゆみ」を鎮めるには、ディラン様本人のパフォーマンスを耳から叩き込むに限る。
「かゆみ」を発症したのはだいたい1964年頃のディランの真似だったので、ブートレグ・シリーズ Vol. 6 [Concert at Philharmonic Hall] がちょうどいい。
このコンサートと一番好きな場面は、” I Don't Believe You” の歌いだしの歌詞を忘れてしまい、イントロを長々と弾き続け、ああでもない、こうでもない。しまいには観客に「歌詞分かる人?」と呼びかけ、客先から教えてもらい、「そうだ、I can’t understand …」と歌い出すところだ。
トラックの切れ目の関係で、このやり取りはその前の曲 ”It's alright ma (I'm Only Bleeding)” の最後に聞くことができる。ところが、YouTube(静止画だが)だと、観客とのやりとりがまるっきり切り取られているのだ。つまり、あの面白いやりとりを聞くには、CDを買うしかない…のか?配信やダウンロードではこういうものは、どうなっているのかよくわからない。もしオミットされているのだとしたら、とんでもなくつまらない話だ。やはり私は CD を買い続けるだろう。
ラジオで流れた例の映画のサウンドトラックの中には、ジョーン・バエズとのデュエットもも含まれていた。彼女を演じた女優の歌もうまいし、ジョーン・バエズの真似もうまい。しかし、これまた「かゆい」。シャラメと合わせて二倍「かゆい」ので、やはりこれも特効薬は本物を聞くことだ。
このデュエットでも歌詞に怪しいところがあって、二人でボソボソ相談しているのが面白い。幸い演奏中のやりとりなので、オミットされていない。「そっちの番なんだけど」、「なんだっけ?」「when」とバエズがいった途端に間髪入れずに歌い出すディランのタイミングも最高だ。
ディランの長いキャリアの中で、60年代こそが最重要で映画にする価値があるというのが一般の認識だろうか。しかし、私にとっては長い長い彼のキャリア全般が素晴らしい音楽であり、性格に難のある「若気の至り」ではなくなってからの彼も、十分魅力的だ。
私がプロデューサーだったら、ディラン様とジョージの友情物語の映画を作るなぁ。そりゃぁ、もちろん漏れなくトムさんも重要人物になるわけだけど。ラストシーンはディンによる “Something” で間違いないだろう。
本人じゃないから気持ちが悪いと言いつつも、こういうことを想像するのは、この手の映画に一定の「布教活動」的な目論見があるからだろう。私にしてみれば60年代のディランにも、ビートルズにもいまさら布教活動は無用だが、ウイルベリー兄弟の物語や、ハートブレイカーズをたくさんの人に知ってもらうには、「モノマネ大会映画」も一つの手段かもしれないと思う。
Grand Valse (Chopin’s Valse, No.5) ― 2025/03/07 22:51
年末に予定されているピアノの発表会では、バッハを弾くことにしている。人前で弾くときは、バッハと決めているのだ。
夏頃からバッハの準備を始めるので、その前にショパンでも弾こうと思い、ワルツの5番、Op. 42 の練習を始めた。
ワルツの5番は、通称 “Grand Valse” , 「大円舞曲」でと呼ばれ、華やかで壮大な曲想をもつ。そのため、演奏会やコンクールでも頻繁に登場する人気曲だ。ショパンのワルツのうち、最高傑作と言われることも多い。
作曲年代は1830年というから、ショパンが20歳のときの作品というころで、彼がいかに早熟の天才だったかがよく分かる。
早速だれかの演奏を参考にしようと思っったのだが、手元にワルツ集のアルバムがないので、動画で聞く。ここはやはり、前回のショパン・コンクールでの、小林愛実さんにご登場願おう。
端正で軽やか、優雅で力強い。これはまさにお手本というべき演奏だ。右手のパッセージが印象的な第二テーマが、出てくるたびに表情が違うのだが、速さの自在さが開放的。特にコーダでの力強さと説得力が良い。
到底手の届かない演奏だが、まずこれを目指したいと思う。
実は、同じく前回のショパン・コンクールで、最終的に優勝したブルース・リウの演奏のうち、一番印象的だったのは、このワルツ5番だった。
久しぶりに聞いてみた。
小林さんの演奏が端正なのに対して、ブルースの演奏はものすごく…良くいえば個性的、はっきりいうとかなりクセのある演奏で、人によっては酷評される。ショパンのワルツをそのように弾くべきではないということを、ことごとくやらかしているのだ。
ウィンナ・ワルツのような拍子の揺れや、極端にシンコペーションを強調した表現。身体的にも、足をバタバタさせて、ピアノと踊っているようだ。品がないとか、冒涜的とか言われることもあるだろうだ。
ところが、この演奏、鬼神のように上手い。難癖をつけるには、上手すぎるのだ。私は好き嫌いはともかく、この演奏で非常に心が突き動かされたし、彼の冒険心に感服した。なにせまだ最終ステージではないのだ。ここで敗退するわけにはいかないが、自分の演奏をやりきる勇気も感じ取ることができる。
だからこそ、私はブルースはこのワルツで勝ったな、という印象を持ったのだ。
ワルツの5番をYouTubeで探すと、のきなみ若手の演奏があがってくる。もしくは素人。大御所の演奏は少なくて、ショパンにおけるワルツの立ち位置というものが見えてくる。
最後に、ルービンシュタインの演奏を聞いてみた。
若者たちにくらべて、テンポは断然ゆるく、しかもかなりタッチが硬い。言うなれば、やや優雅さにかけるだろうっか。愛想もなにもないというか。機嫌でも悪いのだろうかという印象さえ与える。
三人を聴き比べて、まったく異なる表現方法に感動するとともに、まぁ、私の演奏にはあまり関係がないけれどね…とも思ったりする。
夏頃からバッハの準備を始めるので、その前にショパンでも弾こうと思い、ワルツの5番、Op. 42 の練習を始めた。
ワルツの5番は、通称 “Grand Valse” , 「大円舞曲」でと呼ばれ、華やかで壮大な曲想をもつ。そのため、演奏会やコンクールでも頻繁に登場する人気曲だ。ショパンのワルツのうち、最高傑作と言われることも多い。
作曲年代は1830年というから、ショパンが20歳のときの作品というころで、彼がいかに早熟の天才だったかがよく分かる。
早速だれかの演奏を参考にしようと思っったのだが、手元にワルツ集のアルバムがないので、動画で聞く。ここはやはり、前回のショパン・コンクールでの、小林愛実さんにご登場願おう。
端正で軽やか、優雅で力強い。これはまさにお手本というべき演奏だ。右手のパッセージが印象的な第二テーマが、出てくるたびに表情が違うのだが、速さの自在さが開放的。特にコーダでの力強さと説得力が良い。
到底手の届かない演奏だが、まずこれを目指したいと思う。
実は、同じく前回のショパン・コンクールで、最終的に優勝したブルース・リウの演奏のうち、一番印象的だったのは、このワルツ5番だった。
久しぶりに聞いてみた。
小林さんの演奏が端正なのに対して、ブルースの演奏はものすごく…良くいえば個性的、はっきりいうとかなりクセのある演奏で、人によっては酷評される。ショパンのワルツをそのように弾くべきではないということを、ことごとくやらかしているのだ。
ウィンナ・ワルツのような拍子の揺れや、極端にシンコペーションを強調した表現。身体的にも、足をバタバタさせて、ピアノと踊っているようだ。品がないとか、冒涜的とか言われることもあるだろうだ。
ところが、この演奏、鬼神のように上手い。難癖をつけるには、上手すぎるのだ。私は好き嫌いはともかく、この演奏で非常に心が突き動かされたし、彼の冒険心に感服した。なにせまだ最終ステージではないのだ。ここで敗退するわけにはいかないが、自分の演奏をやりきる勇気も感じ取ることができる。
だからこそ、私はブルースはこのワルツで勝ったな、という印象を持ったのだ。
ワルツの5番をYouTubeで探すと、のきなみ若手の演奏があがってくる。もしくは素人。大御所の演奏は少なくて、ショパンにおけるワルツの立ち位置というものが見えてくる。
最後に、ルービンシュタインの演奏を聞いてみた。
若者たちにくらべて、テンポは断然ゆるく、しかもかなりタッチが硬い。言うなれば、やや優雅さにかけるだろうっか。愛想もなにもないというか。機嫌でも悪いのだろうかという印象さえ与える。
三人を聴き比べて、まったく異なる表現方法に感動するとともに、まぁ、私の演奏にはあまり関係がないけれどね…とも思ったりする。
最近のコメント