伶倫楽遊@紀尾井ホール ― 2009/07/05 23:01
紀尾井ホールでの、伶楽舎の雅楽演奏会に行った。第25回「東京の夏」音楽祭2009参加公演,伶倫楽遊。
今回のプログラムは、前半が舞楽を含む古典作品,後半は池辺晋一郎作品の初演という構成だった。
クラシックの演奏会には、すっかり縁遠い生活になってしまったが、伶楽舎の演奏会だけは、極力行くようにしている。
伶楽舎は1985年に音楽監督・芝祐靖先生を中心に結成された、雅楽合奏団体。古典や、復曲もの、そして現代音楽の演奏などで、国内外広く活躍している。
芝祐靖先生をはじめ、学生時代や、その後もお世話になった先生がたが、揃って活躍している。さらに、学生時代からの友人の一人も所属している。
この友人というのが、実は私と一緒に卒業旅行でロンドンに行った人物で、私につきあってアビーロード(2回)はもちろん、遠くリヴァプールや、ふつう行かないヘンリー・オン・テムズまでつき合わされ、「変わったところに行けて面白かった」とコメントしたツワモノである。
雅楽演奏会の宿命だが、客席の至るとことに撃沈(熟睡)している姿がみられた。
私のように雅楽の演奏経験者でも眠いし、演奏している本人も眠いのだから、仕方がない。
学生時代だが、笙を演奏中の同級生が半分寝ていて、よだれを垂らしながら吹いていたということもある。
舞台にはあらかじめ、打楽器が置いてある。やがて開演直前、調弦した琵琶と箏(「琴」。雅楽では「箏」を用いる)が持ち込まれるのだが、その作業の最中に「ガツン!」という音がホールに響いた。なんと、長い箏の一方を舞台背後の壁にぶち当てたらしい。思わず笑ってしまったが、ぶつけた本人は青くなっただろう。
トラブルはここまで。古典曲ではいつものとおり、手堅い演奏を聞かせてくれていた。ただ一つだけ惜しいことに、舞楽の退場曲で、篳篥が音を止めるをタイミングを逃してしまった。
後半は、池辺晋一郎作曲の現代曲。
いつも思うのだが、雅楽の現代曲は、古典の引き立て役になってしまう。どれほど世界的名声を得ている現代作曲家の大作でも、結局はいつも「古典って良いな」で、私の感想は落ち着いてしまう。
学生時代、「陪臚(ばいろ)」という曲が好きだった。吹きやすいので好きなのだと思っていたのだ。
後年、伶楽舎の演奏会で「陪臚」と現代曲を聞く機会があった。そのとき、私は「陪臚」が好きなのは、名曲だからだということを思い知った。現代曲との差は、それほど大きかった。
今回の池辺晋一郎作品も、残念ながら私の現代雅楽曲に対する評価を、大きく覆すことにはならなかった。
多くの雅楽現代曲は、妙な衣装や、珍しすぎて使いづらい楽器などを入れることが多い。そして、ほぼすべての曲が静謐で幻想的な笙を静かに挿入するところから始まる。別に悪くはないが、どれも同じような作りで、どれ一つとして印象的に「良かった」と思わせる曲がないのだ。
その点、今回の池辺作品は、衣装も普通どおり、楽器もおなじみで、しかも幻想的な笙で入らなかった所までは良かった。いきなり打・弦楽器で始まったときは少し期待したが、その後はピンとこない展開だった。
会場もすこし集中力を欠いたようで、物音も多く、音楽がしっかり聴衆の心をつかんでいるとは言い難かった。
演奏終了後、作曲者,池辺晋一郎が舞台に登場。さすがにこの曲では消化不良なので、また何か作って欲しい。
いかにもという感じの、ありきたりな雅楽現代曲ではなく、「こうくるか!」と驚かすような名曲の登場はあるのだろうか。
もしくは、古典雅楽の良さ ― たとえば、楽器ごとにはユニゾンで、ばく進する傍若無人なノリとか、笙の幻想性に依存しない、芯の強い作品などが、聞いてみたい。
最後に、会場の事を。
その名の通り、紀尾井町にある、紀尾井ホール。新日鐵が創立20周年のメセナ事業の一つとして作った。収容人数は中ホールで800人程度。少人数編成のコンサートに最適。
伶楽舎のような雅楽にもぴったり来る。以前、伶楽舎がサントリー・ホールで演奏したことがあったが、若干大きすぎるような気がした。
これは、開演前に二階席から撮った写真。携帯カメラのシャッター音が凄まじく良く響いて焦った。
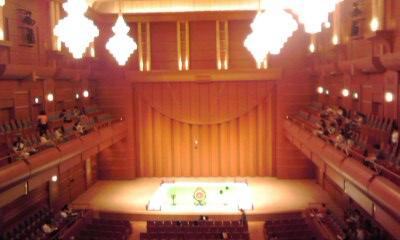
シャンデリアが美しい。これを見て、「ザ・ラスト・ワルツ」を思い出す私は、結局ロック・ファン。
紀尾井ホール程度の規模の、美しくて雰囲気のある会場が好きだ。ごくたまにだが、少しだけドレスアップして、すてきなコンサート・ホールに行くのも悪くない。あとは、眠気を払うだけ。
今回のプログラムは、前半が舞楽を含む古典作品,後半は池辺晋一郎作品の初演という構成だった。
クラシックの演奏会には、すっかり縁遠い生活になってしまったが、伶楽舎の演奏会だけは、極力行くようにしている。
伶楽舎は1985年に音楽監督・芝祐靖先生を中心に結成された、雅楽合奏団体。古典や、復曲もの、そして現代音楽の演奏などで、国内外広く活躍している。
芝祐靖先生をはじめ、学生時代や、その後もお世話になった先生がたが、揃って活躍している。さらに、学生時代からの友人の一人も所属している。
この友人というのが、実は私と一緒に卒業旅行でロンドンに行った人物で、私につきあってアビーロード(2回)はもちろん、遠くリヴァプールや、ふつう行かないヘンリー・オン・テムズまでつき合わされ、「変わったところに行けて面白かった」とコメントしたツワモノである。
雅楽演奏会の宿命だが、客席の至るとことに撃沈(熟睡)している姿がみられた。
私のように雅楽の演奏経験者でも眠いし、演奏している本人も眠いのだから、仕方がない。
学生時代だが、笙を演奏中の同級生が半分寝ていて、よだれを垂らしながら吹いていたということもある。
舞台にはあらかじめ、打楽器が置いてある。やがて開演直前、調弦した琵琶と箏(「琴」。雅楽では「箏」を用いる)が持ち込まれるのだが、その作業の最中に「ガツン!」という音がホールに響いた。なんと、長い箏の一方を舞台背後の壁にぶち当てたらしい。思わず笑ってしまったが、ぶつけた本人は青くなっただろう。
トラブルはここまで。古典曲ではいつものとおり、手堅い演奏を聞かせてくれていた。ただ一つだけ惜しいことに、舞楽の退場曲で、篳篥が音を止めるをタイミングを逃してしまった。
後半は、池辺晋一郎作曲の現代曲。
いつも思うのだが、雅楽の現代曲は、古典の引き立て役になってしまう。どれほど世界的名声を得ている現代作曲家の大作でも、結局はいつも「古典って良いな」で、私の感想は落ち着いてしまう。
学生時代、「陪臚(ばいろ)」という曲が好きだった。吹きやすいので好きなのだと思っていたのだ。
後年、伶楽舎の演奏会で「陪臚」と現代曲を聞く機会があった。そのとき、私は「陪臚」が好きなのは、名曲だからだということを思い知った。現代曲との差は、それほど大きかった。
今回の池辺晋一郎作品も、残念ながら私の現代雅楽曲に対する評価を、大きく覆すことにはならなかった。
多くの雅楽現代曲は、妙な衣装や、珍しすぎて使いづらい楽器などを入れることが多い。そして、ほぼすべての曲が静謐で幻想的な笙を静かに挿入するところから始まる。別に悪くはないが、どれも同じような作りで、どれ一つとして印象的に「良かった」と思わせる曲がないのだ。
その点、今回の池辺作品は、衣装も普通どおり、楽器もおなじみで、しかも幻想的な笙で入らなかった所までは良かった。いきなり打・弦楽器で始まったときは少し期待したが、その後はピンとこない展開だった。
会場もすこし集中力を欠いたようで、物音も多く、音楽がしっかり聴衆の心をつかんでいるとは言い難かった。
演奏終了後、作曲者,池辺晋一郎が舞台に登場。さすがにこの曲では消化不良なので、また何か作って欲しい。
いかにもという感じの、ありきたりな雅楽現代曲ではなく、「こうくるか!」と驚かすような名曲の登場はあるのだろうか。
もしくは、古典雅楽の良さ ― たとえば、楽器ごとにはユニゾンで、ばく進する傍若無人なノリとか、笙の幻想性に依存しない、芯の強い作品などが、聞いてみたい。
最後に、会場の事を。
その名の通り、紀尾井町にある、紀尾井ホール。新日鐵が創立20周年のメセナ事業の一つとして作った。収容人数は中ホールで800人程度。少人数編成のコンサートに最適。
伶楽舎のような雅楽にもぴったり来る。以前、伶楽舎がサントリー・ホールで演奏したことがあったが、若干大きすぎるような気がした。
これは、開演前に二階席から撮った写真。携帯カメラのシャッター音が凄まじく良く響いて焦った。
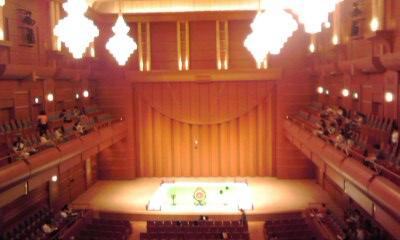
シャンデリアが美しい。これを見て、「ザ・ラスト・ワルツ」を思い出す私は、結局ロック・ファン。
紀尾井ホール程度の規模の、美しくて雰囲気のある会場が好きだ。ごくたまにだが、少しだけドレスアップして、すてきなコンサート・ホールに行くのも悪くない。あとは、眠気を払うだけ。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。