ユリアンナ・アヴデーエワ ― 2011/01/07 23:59
第16回国際ショパン・ピアノ・コンクールの優勝者,ユリアンナ・アヴデーエワが来日し、シャルル・デュトワ指揮のN響とショパンのピアノ・コンチェルト1番で共演し、その模様がテレビで放映された。

この写真は、コンクールの時のもの。エレガントなパンツスタイルで、格好よかった。
アヴデーエワは1985年生まれのロシア人。すでにジュネーヴ国際音楽コンクールや、パデレフスキー・コンクールで名をはせていたらしく、今回のショパン・コンクールでも有望視されていたようだ。
彼女の優勝で喜ばしいことと言えば、まずマルタ・アルゲリッチ以来45年ぶりの女性優勝者であること。芸術家に性別も国籍もあったものではないはずだが、ピアノというのは圧倒的に男性の方が有利な楽器なので(ピアノに限ったことではないが)、やはり女性の勝利は嬉しい。アルゲリッチも今回審査員を務め、アヴデーエワを激賞しており、今回も一緒に来日している。ちなみに、N響でタクトを振ったデュトワとアルゲリッチは、元夫婦である。
ショパン・コンクールの優勝者には、賞金30000ユーロと、金メダルが授与される。賞金はそれほど高くはないのだが、その名誉は計り知れない。そして、さらに副賞がつく。ニューヨークフィルとの共演で、ワルシャワと、ニューヨークでのコンサート。そして、日本でのN響とのコンサートだ。
NHK交響楽団は世界に誇れる一流オーケストラだし、シャルル・デュトワもまた超一流の指揮者(デュトワはN響を気に入っている)。彼らとの共演もまた、名誉なことだろう。
もう一つ、アヴデーエワの優勝で私が嬉しかったのは、彼女が弾いたピアノ。今回、初めて日本製のピアノが勝ったのである。ヤマハが渾身の力作として送り込んだ、CFX。小売希望価格1990万円なり。これはヤマハのピアノとしては例外的に凄まじい高額になっている。ヤマハがどれだけこの楽器に情熱を注ぎ、それをショパン・コンクールに送り込んだか、その意気込みが伝わってくる。
本来、ヤマハやカワイと言った日本製のピアノはヨーロッパ系の有名ブランドピアノにくらべて安価なわりに、性能が良いという特徴を持っている。その日本メーカーがここ一番で資金と技術をつぎ込んで作り上げた楽器が、獲得した成果は天晴れと言うほかない。これまで、スタインウェイの独壇場だっただけに、私は優勝決定の翌日、日経の一面に「ヤマハ、ショパン・コンクールを制する」の文字が躍るかと思った。最近、私はヤマハ音楽教室の方針に疑問を持っているし、製造工場を海外に移すことにも懐疑的だった。今回のことで、ややその評価が持ち直したと言って良い。
ベンモント・テンチとハートブレイカーズは最近、ピアノをヤマハからスタインウェイに変えて、ミーハーな喜びを隠し切れないような印象だが…どうよ!ヤマハに戻さない?!
肝心の、アヴデーエワのN響との共演はどうだったのか。
私は好きだ。「マルカート万歳!」…という感じの、実にはきはきしたタッチで、断言口調とでも言うべきか。ショパンならもっと柔らかく弾くべきという意見もあるかも知れないが、私はバリバリしたエッジの立った音が好きなのだ。
私が小学生のころ、私のあまりの手の小ささに(今でも小さいが)、師は半ば頭を抱える思いだったらしい。それでも私は習いに来る。そこで、ひたすらマルカートで弾くことを鍛錬させられた。即ち、指を高い位置からストンと落とす癖をつけたのである。落とすのであって、決してキーを力で叩くのではない。この「ストンと落とすマルカート」を徹底することによって、音量を確保するのに、私の小学生時代は費やされた。おかげで、私の体格の貧弱さのわりに、音量や音の強さで苦労したことはない。
そういうわけで、私はマルカートでピアノを弾く人が好きらしい。
さらにアヴデーエワの堂々とした雰囲気も良かった。彼女が25歳と、最近のショパン・コンクール優勝者に比べて少し大人であることもある。とにかく、彼女は無駄に顔の表情が豊かすぎたり、音楽に酔いしれるようなところがない。あくまでもオーケストラとの共演であるという自分の立場をよくわきまえている辺りも好感だ。
まだ、アヴデーエワの演奏はほとんど聞けていない。しばらくはショパンばかり弾くことになるだろう。その後、彼女がどんな勉強をして、どんなピアニストになるのか、楽しみだ。あのマルカートっぷりを聞くと、バッハなんて探究してくれると面白そうだが。

この写真は、コンクールの時のもの。エレガントなパンツスタイルで、格好よかった。
アヴデーエワは1985年生まれのロシア人。すでにジュネーヴ国際音楽コンクールや、パデレフスキー・コンクールで名をはせていたらしく、今回のショパン・コンクールでも有望視されていたようだ。
彼女の優勝で喜ばしいことと言えば、まずマルタ・アルゲリッチ以来45年ぶりの女性優勝者であること。芸術家に性別も国籍もあったものではないはずだが、ピアノというのは圧倒的に男性の方が有利な楽器なので(ピアノに限ったことではないが)、やはり女性の勝利は嬉しい。アルゲリッチも今回審査員を務め、アヴデーエワを激賞しており、今回も一緒に来日している。ちなみに、N響でタクトを振ったデュトワとアルゲリッチは、元夫婦である。
ショパン・コンクールの優勝者には、賞金30000ユーロと、金メダルが授与される。賞金はそれほど高くはないのだが、その名誉は計り知れない。そして、さらに副賞がつく。ニューヨークフィルとの共演で、ワルシャワと、ニューヨークでのコンサート。そして、日本でのN響とのコンサートだ。
NHK交響楽団は世界に誇れる一流オーケストラだし、シャルル・デュトワもまた超一流の指揮者(デュトワはN響を気に入っている)。彼らとの共演もまた、名誉なことだろう。
もう一つ、アヴデーエワの優勝で私が嬉しかったのは、彼女が弾いたピアノ。今回、初めて日本製のピアノが勝ったのである。ヤマハが渾身の力作として送り込んだ、CFX。小売希望価格1990万円なり。これはヤマハのピアノとしては例外的に凄まじい高額になっている。ヤマハがどれだけこの楽器に情熱を注ぎ、それをショパン・コンクールに送り込んだか、その意気込みが伝わってくる。
本来、ヤマハやカワイと言った日本製のピアノはヨーロッパ系の有名ブランドピアノにくらべて安価なわりに、性能が良いという特徴を持っている。その日本メーカーがここ一番で資金と技術をつぎ込んで作り上げた楽器が、獲得した成果は天晴れと言うほかない。これまで、スタインウェイの独壇場だっただけに、私は優勝決定の翌日、日経の一面に「ヤマハ、ショパン・コンクールを制する」の文字が躍るかと思った。最近、私はヤマハ音楽教室の方針に疑問を持っているし、製造工場を海外に移すことにも懐疑的だった。今回のことで、ややその評価が持ち直したと言って良い。
ベンモント・テンチとハートブレイカーズは最近、ピアノをヤマハからスタインウェイに変えて、ミーハーな喜びを隠し切れないような印象だが…どうよ!ヤマハに戻さない?!
肝心の、アヴデーエワのN響との共演はどうだったのか。
私は好きだ。「マルカート万歳!」…という感じの、実にはきはきしたタッチで、断言口調とでも言うべきか。ショパンならもっと柔らかく弾くべきという意見もあるかも知れないが、私はバリバリしたエッジの立った音が好きなのだ。
私が小学生のころ、私のあまりの手の小ささに(今でも小さいが)、師は半ば頭を抱える思いだったらしい。それでも私は習いに来る。そこで、ひたすらマルカートで弾くことを鍛錬させられた。即ち、指を高い位置からストンと落とす癖をつけたのである。落とすのであって、決してキーを力で叩くのではない。この「ストンと落とすマルカート」を徹底することによって、音量を確保するのに、私の小学生時代は費やされた。おかげで、私の体格の貧弱さのわりに、音量や音の強さで苦労したことはない。
そういうわけで、私はマルカートでピアノを弾く人が好きらしい。
さらにアヴデーエワの堂々とした雰囲気も良かった。彼女が25歳と、最近のショパン・コンクール優勝者に比べて少し大人であることもある。とにかく、彼女は無駄に顔の表情が豊かすぎたり、音楽に酔いしれるようなところがない。あくまでもオーケストラとの共演であるという自分の立場をよくわきまえている辺りも好感だ。
まだ、アヴデーエワの演奏はほとんど聞けていない。しばらくはショパンばかり弾くことになるだろう。その後、彼女がどんな勉強をして、どんなピアニストになるのか、楽しみだ。あのマルカートっぷりを聞くと、バッハなんて探究してくれると面白そうだが。
ショパン・コンクール ― 2010/10/18 21:20
ポーランドの首都ワルシャワで開催されている、第16回ショパン国際ピアノコンクール(The 16th Internatinal Fryderyk Chopin Piano Competiton 通称「ショパン・コンクール」もしくは「ショパコン」)は、いよいよ最終(四次)審査が始まり、現地時間10月20日には、結果が発表される。
音楽はスポーツではない。順位をつけて競うべきものではないかも知れない。それに、ピアノはショパンだけではない。ショパンだけでピアニストとしての実力は測れないし、これまでショパン・コンクールとは無縁の超一流ピアニストたちも、多く世界で活躍してきた。
そもそも、ショパン・コンクールは「ピアニストとしての登竜門」の一つであって、これに優勝したからと言って、まるで「世界で一番のピアニスト」のように持て囃すのは、間違っている。高校野球のヒーローだって、プロ野球で一流選手になれるかどうかは分からないし、ましてやメジャー・リーグはもっと分からない。ショパン・コンクールで華々しく優勝したものの、その後は伸び悩み、「超一流」の称号は得ずに居る人もあるだろう。
その一方で、ショパン・コンクールに盛り上がる気持ちも分かる。何せ、現役最高のピアニストと言うべきポリーニや、アルゲリッチ、それに次ぐ世代としてのツィメルマン(美形)らは、このコンクールの優勝者なのだ。
それに、ピアノにとって、ショパンというジャンルの存在感は、巨大であることも確かだ。もしショパンとその作品が存在しなかったら、ピアノという楽器の魅力は半減していたかもしれない。ピアノに興味のない人、ピアノを弾かない人には決して分からない、ショパンの凄まじさは厳然たるものである。
ともあれ、基本的にクラシックにはあまり興味のない私でも、ショパン・コンクールは少し気になる。
本選進出者の名簿を見ると、日本人の名前も多い。アジア人の活躍が目覚ましいのは最近の傾向だ。芸術家の国籍にこだわるのも愚かな話だが、やはり同郷人としては日本人にも頑張ってほしい。
しかし、二次選考まではかなり残っていた日本勢は、一人も三次選考には残れなかった。そしてファイナルには、アジア人が一人も残らなかった。ファイナリストは、以下の通り。括弧内は国籍。その後は使用楽器メーカー。
Yulianna Avdeeva (Russia) Yamaha
Evgeni Bozhanov (Bulgaria) Yamaha
François Dumont (France) Fazioli
Lukas Geniušas (Russia/Lithuania) Steinway
Nikolay Khozyainov (Russia) Yamaha
Miroslav Kultyshev (Russia) Steinway
Daniil Trifonov (Russia) Fazioli
Hélene Tysman (France) Yamaha
Paweł Wakarecy (Poland) Steinway
Ingolf Wunder (Austria) Steinway
ロシア勢強し!なんと半数がロシア勢!誰が勝っても構わないのだが、アルゲリッチ以来45年ぶりに、女性の優勝者も良いと思う。ピアノは特に男性の方が有利なのは確かなのだが。
ピアノは、スタインウェイ4人,ヤマハ4人,ファツィオーリ2人。ショパコンでの使用楽器は、スタインウェイ,ヤマハ,カワイ,ファツィオーリ(イタリア)から選ぶことになっている。スタインウェイが圧倒的かと思ったら、ヤマハ使用者も多い(ベンモーン!聞いてるぅ?)。個人的には、カワイにもっと頑張ってほしいのだが。どうしてこの4社に限られているのかは、よく分からない。
ショパン・コンクールは、優勝者該当者無しということもある(実際、第12,13回は該当者無し。何かに懲りたのだろうか…)。最終審査に残ったピアニストたちの中で一番上手に弾いても、優勝するには審査員たち、そして聴衆たちを文句なしに感嘆させるパワーと輝きを必要とされる。それを発揮する人が、あらわれるだろうか?日本人が残っていないだけに、あまり大きなニュースにはしてもらえそうにないが、注目したいところだ。
音楽はスポーツではない。順位をつけて競うべきものではないかも知れない。それに、ピアノはショパンだけではない。ショパンだけでピアニストとしての実力は測れないし、これまでショパン・コンクールとは無縁の超一流ピアニストたちも、多く世界で活躍してきた。
そもそも、ショパン・コンクールは「ピアニストとしての登竜門」の一つであって、これに優勝したからと言って、まるで「世界で一番のピアニスト」のように持て囃すのは、間違っている。高校野球のヒーローだって、プロ野球で一流選手になれるかどうかは分からないし、ましてやメジャー・リーグはもっと分からない。ショパン・コンクールで華々しく優勝したものの、その後は伸び悩み、「超一流」の称号は得ずに居る人もあるだろう。
その一方で、ショパン・コンクールに盛り上がる気持ちも分かる。何せ、現役最高のピアニストと言うべきポリーニや、アルゲリッチ、それに次ぐ世代としてのツィメルマン(美形)らは、このコンクールの優勝者なのだ。
それに、ピアノにとって、ショパンというジャンルの存在感は、巨大であることも確かだ。もしショパンとその作品が存在しなかったら、ピアノという楽器の魅力は半減していたかもしれない。ピアノに興味のない人、ピアノを弾かない人には決して分からない、ショパンの凄まじさは厳然たるものである。
ともあれ、基本的にクラシックにはあまり興味のない私でも、ショパン・コンクールは少し気になる。
本選進出者の名簿を見ると、日本人の名前も多い。アジア人の活躍が目覚ましいのは最近の傾向だ。芸術家の国籍にこだわるのも愚かな話だが、やはり同郷人としては日本人にも頑張ってほしい。
しかし、二次選考まではかなり残っていた日本勢は、一人も三次選考には残れなかった。そしてファイナルには、アジア人が一人も残らなかった。ファイナリストは、以下の通り。括弧内は国籍。その後は使用楽器メーカー。
Yulianna Avdeeva (Russia) Yamaha
Evgeni Bozhanov (Bulgaria) Yamaha
François Dumont (France) Fazioli
Lukas Geniušas (Russia/Lithuania) Steinway
Nikolay Khozyainov (Russia) Yamaha
Miroslav Kultyshev (Russia) Steinway
Daniil Trifonov (Russia) Fazioli
Hélene Tysman (France) Yamaha
Paweł Wakarecy (Poland) Steinway
Ingolf Wunder (Austria) Steinway
ロシア勢強し!なんと半数がロシア勢!誰が勝っても構わないのだが、アルゲリッチ以来45年ぶりに、女性の優勝者も良いと思う。ピアノは特に男性の方が有利なのは確かなのだが。
ピアノは、スタインウェイ4人,ヤマハ4人,ファツィオーリ2人。ショパコンでの使用楽器は、スタインウェイ,ヤマハ,カワイ,ファツィオーリ(イタリア)から選ぶことになっている。スタインウェイが圧倒的かと思ったら、ヤマハ使用者も多い(ベンモーン!聞いてるぅ?)。個人的には、カワイにもっと頑張ってほしいのだが。どうしてこの4社に限られているのかは、よく分からない。
ショパン・コンクールは、優勝者該当者無しということもある(実際、第12,13回は該当者無し。何かに懲りたのだろうか…)。最終審査に残ったピアニストたちの中で一番上手に弾いても、優勝するには審査員たち、そして聴衆たちを文句なしに感嘆させるパワーと輝きを必要とされる。それを発揮する人が、あらわれるだろうか?日本人が残っていないだけに、あまり大きなニュースにはしてもらえそうにないが、注目したいところだ。
スタインウェイ&サンズ ― 2010/10/02 22:00
どうやらトム・ペティの喉の調子も戻ったらしく、10月1日ハリウッド・ボウルからツアーが再開と言う運びになっているようだ。
トム・ペティ&ザ・ハートレブレイカーズの公式ホームページには最近、トムやマイクのギター・テクニシャンの映像がアップされている。最新動画は、ベンモントのキーボード・テクニシャン,ウェイン・ウィリアムズによる楽器紹介。
Wayne's World
私にはエレクトリックな楽器が全く分からないため、やはり最初に紹介されるピアノに目が行く。
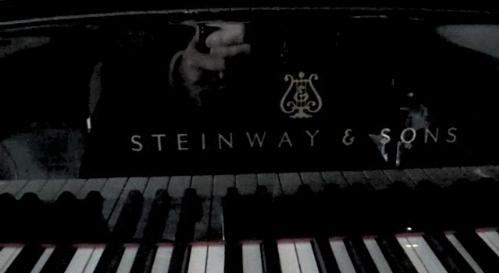
アルバム [MOJO] のクレジットでも気になっていたのだが、最近ベンモントの愛器はスタインウェイだそうだ。モデルB。カタログはこちら。
一番大きなコンサート・グランドは、モデルD。モデルBは、それに次ぐランク。スタジオ録音や、小さいサロン向けのタイプとのこと。ロック・バンドの一角としては、ちょうど良いタイプだろうか。
ベンモント、つい最近までヤマハ愛用者だったのだが、スタインウェイに行ったか…。まぁ、気持ちは分からないでもない。私も2年前のニューヨーク遠征では、スタインウェイのショールームに乗り込んで、一番高いものを選んで弾いた。スタインウェイは、やや鍵盤が軽く、音がスカスカと抜けるような印象を持っているのは、私だけだろうか?
ベンモントには、ヤマハの次にカワイを試して欲しかった。私はカワイ贔屓。確かに、ポップス向きではないのだが…。
ところで、ウェインはどうやらベンモントの楽器を「ドイツ製」と説明しているようだが、本当だろうか?スタインウェイはドイツ・ベルリンと、アメリカ・ニューヨークの二本立ての製造拠点を持っている。私が訪れたニューヨークのショールームも、もちろんアメリカ,スタインウェイ。北米在住のロックバンドが、わざわざドイツからピアノを取り寄せるだろうか?品質は双方とも最高級。意外だが、伝統的な製法を取っているのは、アメリカの方。
スタインウェイの創業の地はドイツだったことで、ウェインが思い違いしているのかも知れない。
スタインウェイのホームページを見ると、冒頭でスタインウェイ愛用の世界的ピアニストたちのコメントが紹介されていた。ブレンデルの次に登場したのが、日本が誇るピアニスト,内田光子。実は彼女、私の恩師とは姉妹弟子だった。レッスン中に、この世界的なピアニストの話題が、よく出てきたものだった。
内田光子と言えば、やはりモーツァルト!ピアノ・ソナタ第5番(K283, G-Dur)第三楽章。いいな、やっぱり。
トム・ペティ&ザ・ハートレブレイカーズの公式ホームページには最近、トムやマイクのギター・テクニシャンの映像がアップされている。最新動画は、ベンモントのキーボード・テクニシャン,ウェイン・ウィリアムズによる楽器紹介。
Wayne's World
私にはエレクトリックな楽器が全く分からないため、やはり最初に紹介されるピアノに目が行く。
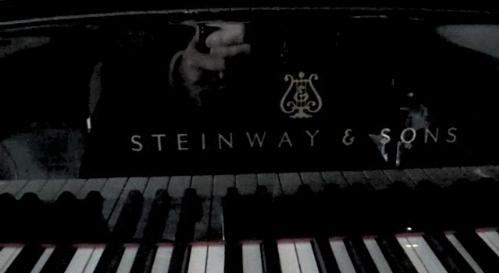
アルバム [MOJO] のクレジットでも気になっていたのだが、最近ベンモントの愛器はスタインウェイだそうだ。モデルB。カタログはこちら。
一番大きなコンサート・グランドは、モデルD。モデルBは、それに次ぐランク。スタジオ録音や、小さいサロン向けのタイプとのこと。ロック・バンドの一角としては、ちょうど良いタイプだろうか。
ベンモント、つい最近までヤマハ愛用者だったのだが、スタインウェイに行ったか…。まぁ、気持ちは分からないでもない。私も2年前のニューヨーク遠征では、スタインウェイのショールームに乗り込んで、一番高いものを選んで弾いた。スタインウェイは、やや鍵盤が軽く、音がスカスカと抜けるような印象を持っているのは、私だけだろうか?
ベンモントには、ヤマハの次にカワイを試して欲しかった。私はカワイ贔屓。確かに、ポップス向きではないのだが…。
ところで、ウェインはどうやらベンモントの楽器を「ドイツ製」と説明しているようだが、本当だろうか?スタインウェイはドイツ・ベルリンと、アメリカ・ニューヨークの二本立ての製造拠点を持っている。私が訪れたニューヨークのショールームも、もちろんアメリカ,スタインウェイ。北米在住のロックバンドが、わざわざドイツからピアノを取り寄せるだろうか?品質は双方とも最高級。意外だが、伝統的な製法を取っているのは、アメリカの方。
スタインウェイの創業の地はドイツだったことで、ウェインが思い違いしているのかも知れない。
スタインウェイのホームページを見ると、冒頭でスタインウェイ愛用の世界的ピアニストたちのコメントが紹介されていた。ブレンデルの次に登場したのが、日本が誇るピアニスト,内田光子。実は彼女、私の恩師とは姉妹弟子だった。レッスン中に、この世界的なピアニストの話題が、よく出てきたものだった。
内田光子と言えば、やはりモーツァルト!ピアノ・ソナタ第5番(K283, G-Dur)第三楽章。いいな、やっぱり。
それぞれの"Here Comes the Sun" ― 2010/07/19 22:16
TP&HBツアーは順調に進んでいる。公式ページにはカンザス・シティでの写真がアップされていたのだが、トムさんの赤いサテンっぽい素材を取り入れたジャケットが、なかなか格好良い。
一応、"with" という表現になっているが、有り体に言えば「前座」。ツアーの最初はジョー・コッカーや、ZZトップ ― やがてバディ・ガイに、8月11日からは、クロスビー・スティルス&ナッシュが登場する。私だったら、このCS&Nが一番見てみたい。
ふと我に帰ってみる。私はどの程度CS&Nについて知っているだろうか。あまり知らない。デイヴィッド・クロスビーは元ザ・バーズの人(ちょっとした ― 容姿イメージ的な ― 詐欺師),スティーヴン・スティルスはモンキーズに入り損ねた人,そしてグラハム・ナッシュは、元ホリーズの人。…確かにほとんど知らない状態だ。
ホリーズの映像をYouTubeで探そうとしたら、ナッシュが居ない(と、思われる)ホリーズばかりが引っかかる。どうやらホリーズ史から学習する必要がありそうだ。
そうこうしているうちに、ロックンロール・ホール・オブ・フェイム25周年記念コンサートの映像が引っかかった。ポール・サイモンがクロスビーとナッシュを迎えて、親友ジョージ・ハリスンの曲を歌う。
クロスビーの図体がでかすぎるのだろうが、それにしてもポール・サイモンは小さい。そのうち携帯電話みたいに落し物の常連になってしまいそうだ。ナッシュは自分の周りの空気を掻きまわさないと歌えないのだろうか?サイモンとクロスビーが淡々と美しさを表現しているだけに、あの悶えっぷりが可笑しい。
"Here Comes the Sun" つながりで、ジェイムズ・テイラーとヨーヨー・マのコラボレーション映像を見る。
ヨーヨー・マは、クラシックに留まらない幅広い活躍で、非常に人気が高い。このテイラーとのコラボレーションも、それなりに良いものだろう。
それはそれだが、ヨーヨー・マについて、私には少し「クラシックに集中すれば良いのに」という思いがある。別に多ジャンルと交流したり、コラボレーションをしたりする事自体は悪いことではない。ただ、出来あがってくるものが、物足りない。この "Here Comes the Sun" にしても、奇麗な演奏ではあるが、オリジナル・レコーディングが持っているような、「ロックの勝利 」を燦然と知らしめる輝きには程遠い(このことは、他の誰のカバーでも同様だが)。
チェロは音色の美しい楽器だ。確かにコラボもしてみたくなる。しかし、クラシックの技術力を知っている者の耳には、どうしても物足りなくなってしまう。その物足りなさが、もったいない。マほどの才能の持ち主なら、カザルスにも肉迫出来るのではないかとという評判さえあったのに。
それとも、マはどこかで自分に見切りをつけているのだろうか?彼は単なる演奏馬鹿ではなく、非常に研究熱心で視野も広い。カザルスにはなれない以上、自分がなるべきものを別の方向に見出してしまっているのだろうか?
私は基本的にクラシックには興味がない。そんな私にも、ちょっとそんなような事を考えさせる "Here Comes the Sun" だった。
一応、"with" という表現になっているが、有り体に言えば「前座」。ツアーの最初はジョー・コッカーや、ZZトップ ― やがてバディ・ガイに、8月11日からは、クロスビー・スティルス&ナッシュが登場する。私だったら、このCS&Nが一番見てみたい。
ふと我に帰ってみる。私はどの程度CS&Nについて知っているだろうか。あまり知らない。デイヴィッド・クロスビーは元ザ・バーズの人(ちょっとした ― 容姿イメージ的な ― 詐欺師),スティーヴン・スティルスはモンキーズに入り損ねた人,そしてグラハム・ナッシュは、元ホリーズの人。…確かにほとんど知らない状態だ。
ホリーズの映像をYouTubeで探そうとしたら、ナッシュが居ない(と、思われる)ホリーズばかりが引っかかる。どうやらホリーズ史から学習する必要がありそうだ。
そうこうしているうちに、ロックンロール・ホール・オブ・フェイム25周年記念コンサートの映像が引っかかった。ポール・サイモンがクロスビーとナッシュを迎えて、親友ジョージ・ハリスンの曲を歌う。
クロスビーの図体がでかすぎるのだろうが、それにしてもポール・サイモンは小さい。そのうち携帯電話みたいに落し物の常連になってしまいそうだ。ナッシュは自分の周りの空気を掻きまわさないと歌えないのだろうか?サイモンとクロスビーが淡々と美しさを表現しているだけに、あの悶えっぷりが可笑しい。
"Here Comes the Sun" つながりで、ジェイムズ・テイラーとヨーヨー・マのコラボレーション映像を見る。
ヨーヨー・マは、クラシックに留まらない幅広い活躍で、非常に人気が高い。このテイラーとのコラボレーションも、それなりに良いものだろう。
それはそれだが、ヨーヨー・マについて、私には少し「クラシックに集中すれば良いのに」という思いがある。別に多ジャンルと交流したり、コラボレーションをしたりする事自体は悪いことではない。ただ、出来あがってくるものが、物足りない。この "Here Comes the Sun" にしても、奇麗な演奏ではあるが、オリジナル・レコーディングが持っているような、「ロックの勝利 」を燦然と知らしめる輝きには程遠い(このことは、他の誰のカバーでも同様だが)。
チェロは音色の美しい楽器だ。確かにコラボもしてみたくなる。しかし、クラシックの技術力を知っている者の耳には、どうしても物足りなくなってしまう。その物足りなさが、もったいない。マほどの才能の持ち主なら、カザルスにも肉迫出来るのではないかとという評判さえあったのに。
それとも、マはどこかで自分に見切りをつけているのだろうか?彼は単なる演奏馬鹿ではなく、非常に研究熱心で視野も広い。カザルスにはなれない以上、自分がなるべきものを別の方向に見出してしまっているのだろうか?
私は基本的にクラシックには興味がない。そんな私にも、ちょっとそんなような事を考えさせる "Here Comes the Sun" だった。
机上の放置CD ― 2010/07/06 22:03
梅棹忠夫氏が亡くなった。音大に入った時、一番最初に先生に読めと命じられたのが、 『知的生産の技術』だった。PC全盛の今、その手法がそのまま使えるわけではないが、興味を持ったら、調べ、記録し、考え、構築していく ― そういう知的生産作業の魅力に、眼を開かされる思いだった。もう一度読みたい本かも知れない。
CDはその名の通りコンパクトなため、棚にしまわず、机上やステレオ上に重ねて放置しているものが多数ある。思いつきで、何が放置されているのかを見てみることにした。
MOJO (Tom Petty & The Heartbreakers) これはあって当然。
グレン・グールド集 (グレン・グールド)
グールドのバッハ「イタリア協奏曲」第三楽章はよく聞きたくなるもんだ。
ショパン,ノクターン集 (ダニエル・バレンモイム) 現在、学習中のため参考用。
Evil Urges (My Morning Jacket)
TP&HBの前座だからと思って買ったけど全く聞いていない。
Live in Chicago (TP&HB)
最近はこういうブートが堂々と普通のCDショップで売っている…
シベリウス ヴァイオリン協奏曲 (ヤッシャ・ハイフェッツ&シカゴ交響楽団)
なんでこんなものが…?思い出した。マイク・キャンベルが、「エレキのストラディバリウスと呼ばれる、レスポールを入手した」という表現を読んで、はて、この例えは適切なのかどうかを考えているうちに、ストラディバリウス所有者の事を考えて、確かハイフェッツは持っていたよな…という連想で引っ張り出したんだ。
Knockin' On Heaven's Door (サウンドトラック)
映画が好き過ぎて、何故かサウンドトラックが2枚ある!
ベートーヴェン ピアノソナタ集 (ウラディーミル・アシュケナージ)
これも自分の演奏参考用だろうな。収録曲は「月光」「告別」「テンペスト」「悲愴」「熱情」「田園」「ワルトシュタイン」かなりお買い得な取り合わせ。
Woman + Country (Jakob Dylan) ごめん、1回しか聞いてない。
タモリ2 (タモリ) 中洲産業大学森田教授の音楽講座!
シューマン ピアノ曲集 (中村紘子) g-moll ソナタの参考用だと思われる。
Lunasa (Lunasa)
何回か前のセッションでやる曲を聴くために、引っ張り出したような記憶が…
Nicely Out Of Tune (Lindisfarne)
超お勧めなブリティッシュ・フォーク・ロック。彼らの記事を書こう、書こうと思いつつ後回しになっている。
Fog on the Tye (Lindisfarne) 以下同文
Live at Royal Albert Hall 1971 (The Byrds)
これは買って良かった名盤!でも、「霧の8マイル」は長すぎるよ!
Thunder Byrd (Roger McGuinn)
このアルバムのタイトル、ずっと [Thunder Bird] だと思ってた…!
Early Tracks Volume I (Howie Epstein) 2枚目ってどうなったの?
An Anthology (Duane Allman)
伝記本の参考用に手元に出していたのだと思われる。レーイラー!とか出てくるのでびっくりする。
BOSEを買った時についてきたサンプルCD さっさとしまえ。
The ARC Gospel Choir ~Thank You Lord~
DVDとセットになっていて、お買い得だったセット。これも記事にしようと思いつつ、後回しになっていた。
Elizabethtown (サウンドトラック)
TP&HB目当てで買ったのは確かだが、なぜ出してあるのかは不明。
A's B's & EP's (Manfred Mann) クラウスが居るのかどうか分からない。
Afterhours (The Bothy Band)
たぶん、セッションで "Farewell to Erin" をやるので、聴いたのだと思う。
Out of the Wind into the Sun (The Bothy Band)
間違いなく "Rip the Calico" 目当て。いつかフルで吹いてみたい。
タモリ (タモリ) ソバヤソバーヤ!!
Down in the Groove (Bob Dylan)
ローリングストーン誌の「偉大なアーチストの残念アルバム」に挙げられていると聞いて、「そんなはずは無かろう!名作だぞ!」と思って、引っ張り出した。
Let It Roll (George Harrison) しかも2枚。美男子ダブルで!
Christmas In The Heart (Bob Dylan) クリスマスはとっくに過ぎましたよ。
Byrds (G. Clark, C. Hillman, D. Crosby, R. McGuinn, M. Clarke)
閉店した新宿のHMVから、売れ残りを私が引き取ったもの。
ゴールドベルグ変奏曲 (グレン・グールド) もちろん、55年録音。
Y Not (Ringo Starr) もちろんベンモント目当て。
名古屋の歌だがね(名古屋開府400年記念CD)
いただきものです。燃~え~よドラゴンズ~♪
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ (グレン・グールド)
げげッ!グールドでベートーヴェン?!私はいったい何を考えていたのだろう…?
Forest (ハウゴー&ホイロップ)
北欧ケルティック・ミュージック。なかなかチャーミングで良い。アーチスト後者の名前はHoirupなのだが、"o" に斜線が入るので、出せないでいる。
Ritual ブルガリアン・ヴォイス (ブルガリア国立放送合唱団)
学生時代、ブルガリアン・チャントにはまったため、それを思い出して買ったのだが、イメージとはちょっと違った。学校で聴いたCDが欲しい。
Etnico ma non troppo (ヘヴィア)
F1番組で使われた曲が聞きたかったので買ったもの。イベリア半島のバグパイプ…の、電子版なのだが…うーん、私はもっと土臭い音楽が好きなので、ちょっと却下。
Goin' Home -A Tribute to Fats Domino-
もちろん、TP&HB目当て。そのほかも錚々たる面々なので、ちゃんと聞いてみよう。
Alone, ballads for solo piano (アンドレ・プレヴィン)
プレヴィンがN響の客員指揮者になった時に購入。ジャズなので、良く分からないけど流しておくと良い感じ。
The Best of the Bothy Band
ボシーのアルバムが手に入りにくいという状況を受けて、購入したもの。結局全アルバムを入手したので、開封しないまま。
合計39枚。…そんなに放置しているのか。しまわなきゃ。
さらに驚いたのは、そのうち8枚がクラシック(プレヴィンを含む)。意外と聞いている…というより、ロックはiPodに入っているので通勤時に聞くが、クラシックはそれをしないので、普通にステレオで聴くことになるのだろう。
CDはその名の通りコンパクトなため、棚にしまわず、机上やステレオ上に重ねて放置しているものが多数ある。思いつきで、何が放置されているのかを見てみることにした。
MOJO (Tom Petty & The Heartbreakers) これはあって当然。
グレン・グールド集 (グレン・グールド)
グールドのバッハ「イタリア協奏曲」第三楽章はよく聞きたくなるもんだ。
ショパン,ノクターン集 (ダニエル・バレンモイム) 現在、学習中のため参考用。
Evil Urges (My Morning Jacket)
TP&HBの前座だからと思って買ったけど全く聞いていない。
Live in Chicago (TP&HB)
最近はこういうブートが堂々と普通のCDショップで売っている…
シベリウス ヴァイオリン協奏曲 (ヤッシャ・ハイフェッツ&シカゴ交響楽団)
なんでこんなものが…?思い出した。マイク・キャンベルが、「エレキのストラディバリウスと呼ばれる、レスポールを入手した」という表現を読んで、はて、この例えは適切なのかどうかを考えているうちに、ストラディバリウス所有者の事を考えて、確かハイフェッツは持っていたよな…という連想で引っ張り出したんだ。
Knockin' On Heaven's Door (サウンドトラック)
映画が好き過ぎて、何故かサウンドトラックが2枚ある!
ベートーヴェン ピアノソナタ集 (ウラディーミル・アシュケナージ)
これも自分の演奏参考用だろうな。収録曲は「月光」「告別」「テンペスト」「悲愴」「熱情」「田園」「ワルトシュタイン」かなりお買い得な取り合わせ。
Woman + Country (Jakob Dylan) ごめん、1回しか聞いてない。
タモリ2 (タモリ) 中洲産業大学森田教授の音楽講座!
シューマン ピアノ曲集 (中村紘子) g-moll ソナタの参考用だと思われる。
Lunasa (Lunasa)
何回か前のセッションでやる曲を聴くために、引っ張り出したような記憶が…
Nicely Out Of Tune (Lindisfarne)
超お勧めなブリティッシュ・フォーク・ロック。彼らの記事を書こう、書こうと思いつつ後回しになっている。
Fog on the Tye (Lindisfarne) 以下同文
Live at Royal Albert Hall 1971 (The Byrds)
これは買って良かった名盤!でも、「霧の8マイル」は長すぎるよ!
Thunder Byrd (Roger McGuinn)
このアルバムのタイトル、ずっと [Thunder Bird] だと思ってた…!
Early Tracks Volume I (Howie Epstein) 2枚目ってどうなったの?
An Anthology (Duane Allman)
伝記本の参考用に手元に出していたのだと思われる。レーイラー!とか出てくるのでびっくりする。
BOSEを買った時についてきたサンプルCD さっさとしまえ。
The ARC Gospel Choir ~Thank You Lord~
DVDとセットになっていて、お買い得だったセット。これも記事にしようと思いつつ、後回しになっていた。
Elizabethtown (サウンドトラック)
TP&HB目当てで買ったのは確かだが、なぜ出してあるのかは不明。
A's B's & EP's (Manfred Mann) クラウスが居るのかどうか分からない。
Afterhours (The Bothy Band)
たぶん、セッションで "Farewell to Erin" をやるので、聴いたのだと思う。
Out of the Wind into the Sun (The Bothy Band)
間違いなく "Rip the Calico" 目当て。いつかフルで吹いてみたい。
タモリ (タモリ) ソバヤソバーヤ!!
Down in the Groove (Bob Dylan)
ローリングストーン誌の「偉大なアーチストの残念アルバム」に挙げられていると聞いて、「そんなはずは無かろう!名作だぞ!」と思って、引っ張り出した。
Let It Roll (George Harrison) しかも2枚。美男子ダブルで!
Christmas In The Heart (Bob Dylan) クリスマスはとっくに過ぎましたよ。
Byrds (G. Clark, C. Hillman, D. Crosby, R. McGuinn, M. Clarke)
閉店した新宿のHMVから、売れ残りを私が引き取ったもの。
ゴールドベルグ変奏曲 (グレン・グールド) もちろん、55年録音。
Y Not (Ringo Starr) もちろんベンモント目当て。
名古屋の歌だがね(名古屋開府400年記念CD)
いただきものです。燃~え~よドラゴンズ~♪
ベートーヴェン ピアノ・ソナタ (グレン・グールド)
げげッ!グールドでベートーヴェン?!私はいったい何を考えていたのだろう…?
Forest (ハウゴー&ホイロップ)
北欧ケルティック・ミュージック。なかなかチャーミングで良い。アーチスト後者の名前はHoirupなのだが、"o" に斜線が入るので、出せないでいる。
Ritual ブルガリアン・ヴォイス (ブルガリア国立放送合唱団)
学生時代、ブルガリアン・チャントにはまったため、それを思い出して買ったのだが、イメージとはちょっと違った。学校で聴いたCDが欲しい。
Etnico ma non troppo (ヘヴィア)
F1番組で使われた曲が聞きたかったので買ったもの。イベリア半島のバグパイプ…の、電子版なのだが…うーん、私はもっと土臭い音楽が好きなので、ちょっと却下。
Goin' Home -A Tribute to Fats Domino-
もちろん、TP&HB目当て。そのほかも錚々たる面々なので、ちゃんと聞いてみよう。
Alone, ballads for solo piano (アンドレ・プレヴィン)
プレヴィンがN響の客員指揮者になった時に購入。ジャズなので、良く分からないけど流しておくと良い感じ。
The Best of the Bothy Band
ボシーのアルバムが手に入りにくいという状況を受けて、購入したもの。結局全アルバムを入手したので、開封しないまま。
合計39枚。…そんなに放置しているのか。しまわなきゃ。
さらに驚いたのは、そのうち8枚がクラシック(プレヴィンを含む)。意外と聞いている…というより、ロックはiPodに入っているので通勤時に聞くが、クラシックはそれをしないので、普通にステレオで聴くことになるのだろう。
お風呂で海戦 ― 2010/07/03 22:54
ビートルズの映画 [A Hard Day's Night] で好きなシーンと言えば、ジョンとジョージのお風呂シーン。
演奏シーンじゃないのかと指摘を受けそうだが…演奏シーンなら、"If I fell" だろうか。
とにかく、お風呂(もしくは髭剃りシーン)はいつ見てもうれしい。帽子をかぶってお風呂に入るジョン。これをモンティ・パイソン以前にやったのだから、大英帝国恐るべし。
ジョンは、どうやら英独海戦を想定しているらしい。バスルームに入ってきたジョージに、ドイツ語で話しかけている。(それにしても、バンツと帽子をかぶっているとは言え、人がお風呂中に、普通に入ってくるものなのだろうか?)
ジョンが鼻歌で歌っているのは、まず "Rule Britannia" 。英国にとっては、国歌に準ずるような扱いを受けている。
映像は、2009年のプロムス・ザ・ラスト・ナイト。エラい盛り上がりようである。独唱歌手の成りはナポレオン戦争時期をイメージしているのだろうか。ユニオン・フラッグや、イングランド,スコットランド,ウェールズ,アイルランドの旗にまじって、他国の旗もゆれているのがご愛敬。
もう一曲は、ドイツ国歌である。映像は、ドイツ国歌 2008年の欧州杯…らしい(私はサッカーに疎い)。
この曲の作曲者は、パパ・ハイドン。オリジナルは皇帝フランツ二世を称える歌だったが、その後歌詞を変えてドイツ国歌となった。さすがに、パパ・ハイドン。良い曲である。
演奏シーンじゃないのかと指摘を受けそうだが…演奏シーンなら、"If I fell" だろうか。
とにかく、お風呂(もしくは髭剃りシーン)はいつ見てもうれしい。帽子をかぶってお風呂に入るジョン。これをモンティ・パイソン以前にやったのだから、大英帝国恐るべし。
ジョンは、どうやら英独海戦を想定しているらしい。バスルームに入ってきたジョージに、ドイツ語で話しかけている。(それにしても、バンツと帽子をかぶっているとは言え、人がお風呂中に、普通に入ってくるものなのだろうか?)
ジョンが鼻歌で歌っているのは、まず "Rule Britannia" 。英国にとっては、国歌に準ずるような扱いを受けている。
映像は、2009年のプロムス・ザ・ラスト・ナイト。エラい盛り上がりようである。独唱歌手の成りはナポレオン戦争時期をイメージしているのだろうか。ユニオン・フラッグや、イングランド,スコットランド,ウェールズ,アイルランドの旗にまじって、他国の旗もゆれているのがご愛敬。
もう一曲は、ドイツ国歌である。映像は、ドイツ国歌 2008年の欧州杯…らしい(私はサッカーに疎い)。
この曲の作曲者は、パパ・ハイドン。オリジナルは皇帝フランツ二世を称える歌だったが、その後歌詞を変えてドイツ国歌となった。さすがに、パパ・ハイドン。良い曲である。
天使を見たかい ― 2010/05/30 00:44
ピアノの話。シューマンの後、またバッハを弾こうと思っていた。私はすぐにバッハに逃げる。べつに得意というわけではなく、多少の安心感があるのだ。ところが、なぜか謎のの克己心が沸き起こり、ショパンを弾くことになった。
ショパンはこれまでにワルツ,即興曲,スケルツォ,エチュードを弾いているので、今回はノクターンに挑戦。まず、「遺作」で通っている cis moll(嬰ハ短調)。映画「戦場のピアニスト」で有名になったし、バンクーバー・オリンピックのフィギュア・スケートでも複数の選手が使っていた、超メジャー曲である。
幸いにして、ショパンにしては技術的にはそれほど難しくなく、曲の長さも短いので、私としては助かる。無論、ショパン特有の臨時記号の多さと、独特の左手の動きには苦労するが。
以前、NHKでシプリアン・カツァリス(1951~ フランス)の公開レッスン番組が放映されたことがある。この番組はショパンの特集だったので、この「遺作」のノクターンも取り上げられ、当時発売されたカツァリスのコメントつきの楽譜がある。
ある個所に、こう書いてある。「天使が舞い降りてくるように」

天使が舞い降りてくるように…?
私は天使を見たことがない。
ましてや、それが舞い降りてくるところなど、見るはずがない。画家のクールベが、「天使を描いてほしかったら、天使を連れて来い」と言ったエピソードがあったような気がする。
せいぜい「木の葉が舞い散るように」くらいだったら、何となくわかるのだが。世間一般的には、天使が舞い降りる様というのは、さほど珍しくない光景なのだろうか。
それとも、私が非クリスチャンの、日本人であるせいだろうか。そういえば、能「羽衣」のラストシーンだって、「天つ御空の 霞に紛れて 失せにけり」などと言いつつも、当の天女はスベスベと橋掛を歩いて、引っこむだけである。
ある人が、「パトラッシュが死んじゃうところに出てくる、天使だよ!」と言うのだが、あいにく私は「パトラッシュが死んじゃうところ」とやらも見たことがない。困ったものだ。
コメントしたカツァリス当人の演奏で確認してみる。1分14秒から始まる個所が、カツァリスが言うところの「天使が舞い降りる」ところ。
ブレーキの具合が良くない自転車が坂をころげおちる様に聞こえなくもないが、とにかくこれが「天使が舞い降りる」というやつということで、参考にしよう。
ショパンはこれまでにワルツ,即興曲,スケルツォ,エチュードを弾いているので、今回はノクターンに挑戦。まず、「遺作」で通っている cis moll(嬰ハ短調)。映画「戦場のピアニスト」で有名になったし、バンクーバー・オリンピックのフィギュア・スケートでも複数の選手が使っていた、超メジャー曲である。
幸いにして、ショパンにしては技術的にはそれほど難しくなく、曲の長さも短いので、私としては助かる。無論、ショパン特有の臨時記号の多さと、独特の左手の動きには苦労するが。
以前、NHKでシプリアン・カツァリス(1951~ フランス)の公開レッスン番組が放映されたことがある。この番組はショパンの特集だったので、この「遺作」のノクターンも取り上げられ、当時発売されたカツァリスのコメントつきの楽譜がある。
ある個所に、こう書いてある。「天使が舞い降りてくるように」
天使が舞い降りてくるように…?
私は天使を見たことがない。
ましてや、それが舞い降りてくるところなど、見るはずがない。画家のクールベが、「天使を描いてほしかったら、天使を連れて来い」と言ったエピソードがあったような気がする。
せいぜい「木の葉が舞い散るように」くらいだったら、何となくわかるのだが。世間一般的には、天使が舞い降りる様というのは、さほど珍しくない光景なのだろうか。
それとも、私が非クリスチャンの、日本人であるせいだろうか。そういえば、能「羽衣」のラストシーンだって、「天つ御空の 霞に紛れて 失せにけり」などと言いつつも、当の天女はスベスベと橋掛を歩いて、引っこむだけである。
ある人が、「パトラッシュが死んじゃうところに出てくる、天使だよ!」と言うのだが、あいにく私は「パトラッシュが死んじゃうところ」とやらも見たことがない。困ったものだ。
コメントしたカツァリス当人の演奏で確認してみる。1分14秒から始まる個所が、カツァリスが言うところの「天使が舞い降りる」ところ。
ブレーキの具合が良くない自転車が坂をころげおちる様に聞こえなくもないが、とにかくこれが「天使が舞い降りる」というやつということで、参考にしよう。
チャイコフスキーの生涯 ― 2010/04/25 22:08
コメディ記事続き。
ブーシュが並んだ店の棚には、関連作品として、ブリティッシュ・コメディが並んでおり、その中でもやはりモンティ・パイソンは外せない存在になっている。
パイソンと音楽と言うネタはいくらでもあるが、私が好きなのは「チャイコフスキーの生涯」と言うドキュメンタリー。このドキュメンタリーは、「明るい農村」という番組の特集トピックという謎の扱いを受けており、悲愴をバックに羊がひたすら群れていたりする。
さらに、映画評論家が間違って紛れ込み(ジョン・クリーズ)、チャイコフスキーを大きさでのみ分析し(グレアム・チャップマン)、分解できる人形でチャイコフスキーを語る(テリー・ジョーンズ)。一番まともな解説をしていた奴も、なぜか美容師(マイケル・ペイリン)。パイソンにおいて、美容師は十中八九オカマである。
一番面白かったコメントは、司会者(エリック・アイドル)の「チャイコフスキー。彼は悩める魂の発露を音楽に求めた偉大なる存在か。もしくは、ただの音楽好きなオカマか。」…チャイコフスキー・ファンが聞いたら卒倒しそうだが、私は大好きだ。確かに、チャイコフスキーには同性愛説がある。
そして、最後に「世界的に有名なスヴァトスラフ・リヒテルによる、協奏曲第一番の演奏。演奏しながら、三つの南京錠を外し、麻袋から脱出します!」
最初に見たときは、死ぬほど笑った。あまりのバカバカしさに。
ちなみに、本物のリヒテルはこちら(1915~1997)。20世紀最大のピアニストの一人で、晩年はヤマハのピアノを愛用したことでも知られている。

さらに、このスケッチを再現した人が居る。どこかの学校の、ハロウィーンの出し物らしい。なかなかの力作で、これまた結構。
ブーシュが並んだ店の棚には、関連作品として、ブリティッシュ・コメディが並んでおり、その中でもやはりモンティ・パイソンは外せない存在になっている。
パイソンと音楽と言うネタはいくらでもあるが、私が好きなのは「チャイコフスキーの生涯」と言うドキュメンタリー。このドキュメンタリーは、「明るい農村」という番組の特集トピックという謎の扱いを受けており、悲愴をバックに羊がひたすら群れていたりする。
さらに、映画評論家が間違って紛れ込み(ジョン・クリーズ)、チャイコフスキーを大きさでのみ分析し(グレアム・チャップマン)、分解できる人形でチャイコフスキーを語る(テリー・ジョーンズ)。一番まともな解説をしていた奴も、なぜか美容師(マイケル・ペイリン)。パイソンにおいて、美容師は十中八九オカマである。
一番面白かったコメントは、司会者(エリック・アイドル)の「チャイコフスキー。彼は悩める魂の発露を音楽に求めた偉大なる存在か。もしくは、ただの音楽好きなオカマか。」…チャイコフスキー・ファンが聞いたら卒倒しそうだが、私は大好きだ。確かに、チャイコフスキーには同性愛説がある。
そして、最後に「世界的に有名なスヴァトスラフ・リヒテルによる、協奏曲第一番の演奏。演奏しながら、三つの南京錠を外し、麻袋から脱出します!」
最初に見たときは、死ぬほど笑った。あまりのバカバカしさに。
ちなみに、本物のリヒテルはこちら(1915~1997)。20世紀最大のピアニストの一人で、晩年はヤマハのピアノを愛用したことでも知られている。

さらに、このスケッチを再現した人が居る。どこかの学校の、ハロウィーンの出し物らしい。なかなかの力作で、これまた結構。
幻想即興曲 ― 2010/03/01 22:59
生年月日には異説もあるが、2010年3月1日は、フレデリック・フランソワ・ショパン(1810-1848)、200回目の誕生日ということになっている。まさにショパン・イヤー。秋には、5年に一度のショパン国際ピアノコンクールが開かれる。
私もピアノを弾く人間なので、必然的にショパンの曲は好きだ。初めてショパンを弾いた時、衝撃的なほどに自分が「大人になった」と実感した。
しかし、そのキャラクターはやや物足りない。同時代人であり、友人でもあったメンデルスゾーンやシューマン、リストなどに比べると、ショパンはややバイタリティに欠ける。友人たちが「音楽家という職業」について考え、積極的,発展的に行動したのに対し、ショパンは生涯、小さなサロンに収まった一ピアニスト・作曲家に留まった。彼自身が、性格的(そして体力的)にそれを望んだともいえる。
さらに、ピアノ曲以外にはこれといった作品が無い(もっと言えば、ピアノ曲である協奏曲もイマイチ。オーケストレーションがイマイチなので)。その代りに、ピアノ曲は凄まじい名曲揃いで、その美しさは恐ろしささえ感じる。パガニーニがそう噂されたように、私はショパンの凄みには悪魔的な何かがあると思っている。
ショパンの楽曲で人気投票をすると、「幻想即興曲」がいつもトップに来る。四つの即興曲の中で、ショパンが生前発表せずに終わったこの曲。一説には、ベートーヴェンのピアノソナタ「月光」の第三楽章に酷似していたため、ショパンが発表をためらったとのこと。確かに似ているが、後世の我々にとっては、ショパンの凄まじさが強烈で、「月光」との類似には頭が回らない。
「幻想即興曲」の人気は、「この曲が存在しなかったら、音楽大学の半数は潰れている」と言われているほどである。この説には大賛成だ。
この曲の更に良いところは、憧れの楽曲である割りに、実はそれほどの難曲ではないということ。まともに練習すれば、10年で弾けるようになる。
「ピアノに向かない3条件」(練習嫌い,譜読みが遅い,手が小さい)を全て完璧にクリアする私でさえ、14歳くらいで弾けるようになったのだから、これは間違いない。所謂「天才少年少女」が、よく小学生の身で弾いていたりする。
YouTubeで幾つか演奏を拾ってみる
まずは、ウラジミール・アシュケナージ。楽譜がついていて面白い。ちょっとメロウで、スタンダードな演奏。
次にサンソン・フランソワ。わぁ~!なんだこりゃ!凄いぞ、ほとんどノン・レガートだ!ガッツンガッツン、バッキンバッキン!「真似しないように」と言われそうだが、どだい無理である。
伝説のショパン弾き,コルトーの演奏もあったのだが、あまりにもミスタッチが多すぎて却下(笑)。まぁ、そういう事もあるよね。
最後に、20世紀の伝説,ウラジーミル・ホロヴィッツ。かなり速い。それでいて繊細。で、時々ガツン!メリハリの利いた演奏が良い。
久しぶりに聴いてみると、やはり良い曲だ。よく色々な楽器を織り交ぜた編曲を聴くことがあるが、やはりピアノ独奏で聴くのが一番イカしている。
私もピアノを弾く人間なので、必然的にショパンの曲は好きだ。初めてショパンを弾いた時、衝撃的なほどに自分が「大人になった」と実感した。
しかし、そのキャラクターはやや物足りない。同時代人であり、友人でもあったメンデルスゾーンやシューマン、リストなどに比べると、ショパンはややバイタリティに欠ける。友人たちが「音楽家という職業」について考え、積極的,発展的に行動したのに対し、ショパンは生涯、小さなサロンに収まった一ピアニスト・作曲家に留まった。彼自身が、性格的(そして体力的)にそれを望んだともいえる。
さらに、ピアノ曲以外にはこれといった作品が無い(もっと言えば、ピアノ曲である協奏曲もイマイチ。オーケストレーションがイマイチなので)。その代りに、ピアノ曲は凄まじい名曲揃いで、その美しさは恐ろしささえ感じる。パガニーニがそう噂されたように、私はショパンの凄みには悪魔的な何かがあると思っている。
ショパンの楽曲で人気投票をすると、「幻想即興曲」がいつもトップに来る。四つの即興曲の中で、ショパンが生前発表せずに終わったこの曲。一説には、ベートーヴェンのピアノソナタ「月光」の第三楽章に酷似していたため、ショパンが発表をためらったとのこと。確かに似ているが、後世の我々にとっては、ショパンの凄まじさが強烈で、「月光」との類似には頭が回らない。
「幻想即興曲」の人気は、「この曲が存在しなかったら、音楽大学の半数は潰れている」と言われているほどである。この説には大賛成だ。
この曲の更に良いところは、憧れの楽曲である割りに、実はそれほどの難曲ではないということ。まともに練習すれば、10年で弾けるようになる。
「ピアノに向かない3条件」(練習嫌い,譜読みが遅い,手が小さい)を全て完璧にクリアする私でさえ、14歳くらいで弾けるようになったのだから、これは間違いない。所謂「天才少年少女」が、よく小学生の身で弾いていたりする。
YouTubeで幾つか演奏を拾ってみる
まずは、ウラジミール・アシュケナージ。楽譜がついていて面白い。ちょっとメロウで、スタンダードな演奏。
次にサンソン・フランソワ。わぁ~!なんだこりゃ!凄いぞ、ほとんどノン・レガートだ!ガッツンガッツン、バッキンバッキン!「真似しないように」と言われそうだが、どだい無理である。
伝説のショパン弾き,コルトーの演奏もあったのだが、あまりにもミスタッチが多すぎて却下(笑)。まぁ、そういう事もあるよね。
最後に、20世紀の伝説,ウラジーミル・ホロヴィッツ。かなり速い。それでいて繊細。で、時々ガツン!メリハリの利いた演奏が良い。
久しぶりに聴いてみると、やはり良い曲だ。よく色々な楽器を織り交ぜた編曲を聴くことがあるが、やはりピアノ独奏で聴くのが一番イカしている。
眩しいリンクと、暗澹たる話 ― 2009/12/27 23:38
リンクに、いつも素敵なコメントを下さる、Scottieさんのブログ、トムさんに恋してを追加しました。
タイトルでも分かる通り、TP&HBへの愛にあふれた、眩しい記事のオンパレード。拝見していてうれしくなってしまいます。これからもよろしくお願いします。
年末である。友達と会う機会も多いし、見たいテレビ番組も多い。小さいが、様々な音楽に関する話題がチョロチョロと徘徊している。
フィギュアスケートで気になる音楽。一番趣味が悪いと思うのは、安藤美姫のショート,「レクイエム」(モーツァルト)。あそこまで変な編曲をすると、さすがのモーツァルトも形無しである。
アイリッシュ・ダンス・ショー,「リバーダンス」を使っている人が複数。日本人の趣味に合う音楽だと思われる。
小塚崇彦はショート、フリーともにエレキ・ギターの曲。ショートは、ジミ・ヘンドリックス。長さはともかく、音はオリジナルを使っている。フリーは、「布袋の」と紹介されるギター・コンチェルトだが、実はこの曲、マイケル・ケイマンの曲なのだ。ケイマンと言えば、CFGでのストリングス・コンダクターだし、トムさんも [Wildflowers] で非常にお世話になった、名作曲家,アレンジャー,プロデューサーである(合掌)。
たしか、フランスの選手に、ストーンズ・メドレーを使っている選手が居たような気がする。面白いプログラムだったので、オリンピックでも見てみたい。
五輪選手ではないが、日本の男子で、フリーの曲が「ゲティスバーグ」の人が居た。おそらく、映画のサントラだろう。衣装も肋骨服っぽい。色はシルバーなので…南軍なのかな?。
新宿タカシマヤタイムズスクェアの、HMVが来年1月6日をもって閉店する。閉店前に一度行ってみた。
小規模のHMVに行くと、ほとんど私が買うようなものは無いに等しい。その点、新宿はまだ使える大規模ショップだったし、アクセス,買い物などの面などでも便利だったので、閉店は残念だ。
昨日行ってみると、そこは空襲に遭った町の焼け野原のようだった。商品は売れるに任せて、棚に黒い空白が多数みられる。ブラインド・ボーイ・フラーのCDが欲しかったのだが、ブルースの棚はほぼ空だった。ジョージのところにもベストが1枚ある切り。
ザ・バーズのところには、1973年の再結成アルバム [Byrds] がポツンと残っていたので、私が引き取ることにした。
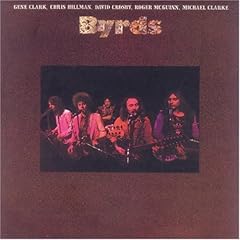
このアルバム、厳密にはザ・バーズというバンドのアルバムではなく、G.クラーク,ヒルマン,クロスビー,マッグイン,M.クラークによる、[Byrds] というタイトルのアルバムだそうだ。まだ聞き込んでいないが、1曲目だけでもコーラスワークの美しさにうれしくなってしまう。
先週のピアノの発表会。いつも、本番は練習の70%が出れば良いと思っているのだが、今回は40%程度の悲惨な結果だった。本番に弱いにもほどがある。ピアノは練習がほぼ全てだとは言え、いい加減この勝負弱さをどうにかせねば。
ピアノを習うことについて、暗澹たる気持ちになる話を聞いた。
とある、男子高校生の話である。彼は、小学生まで私の知人にピアノを習っていた。中学3年間は休み、高校生になってレッスンを再開することにした。そこで、彼は某大手音楽教室の門を叩いた。この音楽教室でついた先生は、発表会向けとして、彼にショパンのエチュード3曲を課した。
まず、これが仰天すべきことだった。この高校生のレベルはせいぜい小学校卒業程度であり、バッハの複旋律や、ソナタの類、ましてやショパンの初歩であるワルツさえ弾いたことがない。一方、課されたショパンのエチュードと言えば、音大生レベルの曲だ。しかも3曲というのは、やや狂気じみている。
無理だと判断した高校生は、かつて師事していた私の知人に助けを求め、そのレッスンで補うことにした。そこで、知人は高校生が音楽教室に払っているレッスン料を聞いて、また驚いた。1回30分のレッスンが月に3回、月謝が16000円と言うのだ。まず、高い。1時間換算にすると、10000円強。これは音楽大学受験の面倒を見てくれる偉い先生なら相場だ。しかし、その場合は課題が重いので、絶対に30分では無理で、普通1時間かける。
私はこの話を聞いて、何かの間違いじゃないかと思った。しかし、理由はすぐにわかった。この音楽教室のシステムだと、生徒が弾く曲のレベルが上がると、レッスン料も上がるのだと言う。つまり、音楽教室としては難しいレベル設定の曲をやらせて、高額の報酬を得たいがために、彼の実力に不相応な曲をむりやり弾かせているのだ。
私はこの話を、音大仲間にもしたのだが、全員が憤慨の大合唱だった。
そもそも、曲のレベルによってレッスン料が違うというところが気に入らない。生徒が4歳の初心者だろうが、18歳の音大ピアノ科受験生だろうが、教師は同レベルの技術と情熱を傾けて指導するべきであり、その内容のレッスン・クォリティに差などあってはならない。実際、私は7歳から18歳まで同じ先生についていたのだが、指一本の下し方から教わり直した7歳の時と、大学受験のために泣きながらベートーヴェンのソナタを弾いていた18歳の時で、師のレッスンには何の差もなく、同じレッスン料を払って当然だった。
実力が伴っていないのに、高い料金を取りたいがために無理やりショパンをやらせるなどという詐欺じみたことを、大手の音楽教室がやっていることに、私は絶望してしまった。おそらく、その無茶な曲を課した先生も(某一流音大ピアノ科出身だそうだ)、間違っていると分かっているが、音楽教室組織からの圧力があるのだろう。
こんな事が、長くまかり通るはずがない。某音楽教室は、いずれその報いを受けるだろう。大手でもあるので、早く過ちに気付いて、高い志を取り戻してほしい。
タイトルでも分かる通り、TP&HBへの愛にあふれた、眩しい記事のオンパレード。拝見していてうれしくなってしまいます。これからもよろしくお願いします。
年末である。友達と会う機会も多いし、見たいテレビ番組も多い。小さいが、様々な音楽に関する話題がチョロチョロと徘徊している。
フィギュアスケートで気になる音楽。一番趣味が悪いと思うのは、安藤美姫のショート,「レクイエム」(モーツァルト)。あそこまで変な編曲をすると、さすがのモーツァルトも形無しである。
アイリッシュ・ダンス・ショー,「リバーダンス」を使っている人が複数。日本人の趣味に合う音楽だと思われる。
小塚崇彦はショート、フリーともにエレキ・ギターの曲。ショートは、ジミ・ヘンドリックス。長さはともかく、音はオリジナルを使っている。フリーは、「布袋の」と紹介されるギター・コンチェルトだが、実はこの曲、マイケル・ケイマンの曲なのだ。ケイマンと言えば、CFGでのストリングス・コンダクターだし、トムさんも [Wildflowers] で非常にお世話になった、名作曲家,アレンジャー,プロデューサーである(合掌)。
たしか、フランスの選手に、ストーンズ・メドレーを使っている選手が居たような気がする。面白いプログラムだったので、オリンピックでも見てみたい。
五輪選手ではないが、日本の男子で、フリーの曲が「ゲティスバーグ」の人が居た。おそらく、映画のサントラだろう。衣装も肋骨服っぽい。色はシルバーなので…南軍なのかな?。
新宿タカシマヤタイムズスクェアの、HMVが来年1月6日をもって閉店する。閉店前に一度行ってみた。
小規模のHMVに行くと、ほとんど私が買うようなものは無いに等しい。その点、新宿はまだ使える大規模ショップだったし、アクセス,買い物などの面などでも便利だったので、閉店は残念だ。
昨日行ってみると、そこは空襲に遭った町の焼け野原のようだった。商品は売れるに任せて、棚に黒い空白が多数みられる。ブラインド・ボーイ・フラーのCDが欲しかったのだが、ブルースの棚はほぼ空だった。ジョージのところにもベストが1枚ある切り。
ザ・バーズのところには、1973年の再結成アルバム [Byrds] がポツンと残っていたので、私が引き取ることにした。
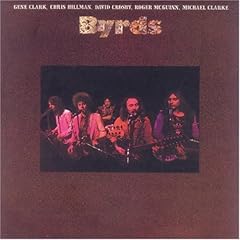
このアルバム、厳密にはザ・バーズというバンドのアルバムではなく、G.クラーク,ヒルマン,クロスビー,マッグイン,M.クラークによる、[Byrds] というタイトルのアルバムだそうだ。まだ聞き込んでいないが、1曲目だけでもコーラスワークの美しさにうれしくなってしまう。
先週のピアノの発表会。いつも、本番は練習の70%が出れば良いと思っているのだが、今回は40%程度の悲惨な結果だった。本番に弱いにもほどがある。ピアノは練習がほぼ全てだとは言え、いい加減この勝負弱さをどうにかせねば。
ピアノを習うことについて、暗澹たる気持ちになる話を聞いた。
とある、男子高校生の話である。彼は、小学生まで私の知人にピアノを習っていた。中学3年間は休み、高校生になってレッスンを再開することにした。そこで、彼は某大手音楽教室の門を叩いた。この音楽教室でついた先生は、発表会向けとして、彼にショパンのエチュード3曲を課した。
まず、これが仰天すべきことだった。この高校生のレベルはせいぜい小学校卒業程度であり、バッハの複旋律や、ソナタの類、ましてやショパンの初歩であるワルツさえ弾いたことがない。一方、課されたショパンのエチュードと言えば、音大生レベルの曲だ。しかも3曲というのは、やや狂気じみている。
無理だと判断した高校生は、かつて師事していた私の知人に助けを求め、そのレッスンで補うことにした。そこで、知人は高校生が音楽教室に払っているレッスン料を聞いて、また驚いた。1回30分のレッスンが月に3回、月謝が16000円と言うのだ。まず、高い。1時間換算にすると、10000円強。これは音楽大学受験の面倒を見てくれる偉い先生なら相場だ。しかし、その場合は課題が重いので、絶対に30分では無理で、普通1時間かける。
私はこの話を聞いて、何かの間違いじゃないかと思った。しかし、理由はすぐにわかった。この音楽教室のシステムだと、生徒が弾く曲のレベルが上がると、レッスン料も上がるのだと言う。つまり、音楽教室としては難しいレベル設定の曲をやらせて、高額の報酬を得たいがために、彼の実力に不相応な曲をむりやり弾かせているのだ。
私はこの話を、音大仲間にもしたのだが、全員が憤慨の大合唱だった。
そもそも、曲のレベルによってレッスン料が違うというところが気に入らない。生徒が4歳の初心者だろうが、18歳の音大ピアノ科受験生だろうが、教師は同レベルの技術と情熱を傾けて指導するべきであり、その内容のレッスン・クォリティに差などあってはならない。実際、私は7歳から18歳まで同じ先生についていたのだが、指一本の下し方から教わり直した7歳の時と、大学受験のために泣きながらベートーヴェンのソナタを弾いていた18歳の時で、師のレッスンには何の差もなく、同じレッスン料を払って当然だった。
実力が伴っていないのに、高い料金を取りたいがために無理やりショパンをやらせるなどという詐欺じみたことを、大手の音楽教室がやっていることに、私は絶望してしまった。おそらく、その無茶な曲を課した先生も(某一流音大ピアノ科出身だそうだ)、間違っていると分かっているが、音楽教室組織からの圧力があるのだろう。
こんな事が、長くまかり通るはずがない。某音楽教室は、いずれその報いを受けるだろう。大手でもあるので、早く過ちに気付いて、高い志を取り戻してほしい。
最近のコメント