CFGの客席と楽屋 ― 2011/05/03 22:31
楽しい [Concer For George] は、何もかもが素敵だが、客席もまたすてきだ。
アングルによっては、こんな人も見られる。

拡大すると、こう。

スティーヴ・ウィンウッドの姿は、楽屋でも見られる。

楽屋ついでに、楽屋でのショットを二つ。


クラプトンと話すダーニ。手つきが近所のおばさんっぽい。
「ですってよぉ~おくさん・・・」
右の写真で、ダーニとツーショットを撮っている、カミーユ・リチャーズって誰だろう?
[CFG] の客席に居る人と言えば、ビル・ワイマンが居たという話を聞いたことがある。どうやら、"While my guitar gently weeps" の直後に映る客席に彼が居るというのだが…

これはどうかな…。微妙だ。確かにビル・ワイマンだと言われれば、ビル・ワイマンに見えるし、違うと言われれば違うような気もする。良い席と言えば良い席にも見えるし…。真相は、当人に聞いてみるしかないか。
アングルによっては、こんな人も見られる。

拡大すると、こう。

スティーヴ・ウィンウッドの姿は、楽屋でも見られる。

楽屋ついでに、楽屋でのショットを二つ。


クラプトンと話すダーニ。手つきが近所のおばさんっぽい。
「ですってよぉ~おくさん・・・」
右の写真で、ダーニとツーショットを撮っている、カミーユ・リチャーズって誰だろう?
[CFG] の客席に居る人と言えば、ビル・ワイマンが居たという話を聞いたことがある。どうやら、"While my guitar gently weeps" の直後に映る客席に彼が居るというのだが…

これはどうかな…。微妙だ。確かにビル・ワイマンだと言われれば、ビル・ワイマンに見えるし、違うと言われれば違うような気もする。良い席と言えば良い席にも見えるし…。真相は、当人に聞いてみるしかないか。
A Brief History of Rock 'n' Roll Hall of Fame ― 2011/05/06 23:02
ロックが生まれてからそれなりの年月が過ぎ、いくつかのブームと、確固たるジャンルを築いてきた。ロックの殿堂 (Rock and Roll Hall of Fame)入りするには、デビュー25周年以上が条件のひとつのようだが、昨今の殿堂入りメンバーを見ると、それほど博物館級の顔ぶれでも、必ずしもなくなっているかもしれない。TP&HBなどは、私にとっては若い方のバンドで、殿堂入りした伝説のバンドとなると、何となく変な気分すらする。
1995年、私はまだまだお金に不自由する学生で、当然インターネットなどない時代だから、自宅のテレビのかじりついて、洋楽情報をキャッチしようとしていた。当時のMTV Japanはほぼ洋楽一辺倒で、実にありがたい存在だった。この年、10周年を迎えたロックの殿堂セレモニーの模様がMTVで放映されたとき、それを3倍設定のVHSで録画した。まだ、クリーブランドに殿堂の建物が出来る前のことだ。この番組では、冒頭に10年間のセレモニーにおける名場面を編集した、"A Brief History"(おいしいとこダイジェスト) が10分ほどついており、私はこの映像がたまらなく好きだった。
後年、YouTubeなどでセレモニーにおける歴代のジャムセッションなどを観賞 する機会を得たが、どれも練習不足,打ち合わせ不足,リハ不足が否めず、演奏クォリティはお世辞にも良いとは言えない(私はクラシック畑出身のため、「練習さえすればもっと良い演奏ができるはず」という欲求が強い。自分にも、他人にも)。
その点、このダイジェストは、粗が見えない程度に、格好良いところだけを切り出し、笑えるスピーチ、感動的なスピーチ、そして50年代から60年代という、まさに殿堂入りにふさわしいロック史へと私たちを誘うのに格好の映像だった。
3倍VHSをすり切れるほど見たため、映像も音も劣悪だが、もったいないので、YouTubeにアップした。こうでもしないと、テープを断捨離できない。
ごくごく短いジョージのアップショットが見たくて、繰り返し観賞したことは、正直に認める。このキラキラしたジョージの格好良さに参っていた。しかも、"I saw her standing there" の "Ooooooh!" で首を振ったジョージが、隣りのディラン(どう見ても楽屋からジョージに引きずり出されたようにしか見えない)に、ニコっと笑いかけるのは、決して見逃さない。ブルースとミックは、どちらがいつ、相手の顔に噛みついてもおかしくない。
ポールがジョンのプレゼンターを務めているが、この時ポールが小野洋子と話しているうちに、後に "Free as a bird" になるデモテープの存在が浮上したとのこと。
全体的に、エリック・クラプトンがおいしいところを持って行っている。ザ・バンドしかり、クリームしかり。でも、ザ・バンドには入れてやりませんよ。
クラプトンも50年代の大御所に比べるとひよっこに見える。"Soul Man" のバックに、ジョニー・キャッシュって凄いな。スティーヴ・ウィンウッドに至っては、さながらどこかの元気な小僧っ子。大御所連中の中には、フィル・スペクターの顔も見られる。
レイ・デイヴィスのスピーチはさすが。キースは…ええ、支離滅裂ですね。ポール・サイモンは性格が良いのか、悪いのか分からない。ボノ(ボブ・マーリーのプレゼンター)も上手い。
小さな男の子が、「いつかボクももらえると思います」とスピーチしているが、この子は誰の息子なんだろう?故人のはずがだが…?CCRのトム・フォガティの息子はもっと大きいし…
殿堂入りメンバーと、そのプレゼンターがどこかにリストになっていると良いのだが、今のところ見つけられないでいる。
なんだかんだと言っても、やはり一番面白かったのは、ジェフ・ベックのスピーチだ。この人、あんな顔をしているが、喋らせると面白い。
手始めに、ヤードバーズはクビになったんだから、喜べないというスピーチ。声が一部カットされているが、実はFワードをかましている。背後で、アンパンマン ジミー・ペイジが大爆笑。
そして、ロッドのプレゼンターとしては、彼との「愛憎関係」を素直に(?)認めている。やっぱり、ロックンローラーとはいえ、大英帝国人たるもの、この程度のスピーチはできなきゃイカンのだなぁと、妙に納得してしまった。
1995年、私はまだまだお金に不自由する学生で、当然インターネットなどない時代だから、自宅のテレビのかじりついて、洋楽情報をキャッチしようとしていた。当時のMTV Japanはほぼ洋楽一辺倒で、実にありがたい存在だった。この年、10周年を迎えたロックの殿堂セレモニーの模様がMTVで放映されたとき、それを3倍設定のVHSで録画した。まだ、クリーブランドに殿堂の建物が出来る前のことだ。この番組では、冒頭に10年間のセレモニーにおける名場面を編集した、"A Brief History"(おいしいとこダイジェスト) が10分ほどついており、私はこの映像がたまらなく好きだった。
後年、YouTubeなどでセレモニーにおける歴代のジャムセッションなどを観賞 する機会を得たが、どれも練習不足,打ち合わせ不足,リハ不足が否めず、演奏クォリティはお世辞にも良いとは言えない(私はクラシック畑出身のため、「練習さえすればもっと良い演奏ができるはず」という欲求が強い。自分にも、他人にも)。
その点、このダイジェストは、粗が見えない程度に、格好良いところだけを切り出し、笑えるスピーチ、感動的なスピーチ、そして50年代から60年代という、まさに殿堂入りにふさわしいロック史へと私たちを誘うのに格好の映像だった。
3倍VHSをすり切れるほど見たため、映像も音も劣悪だが、もったいないので、YouTubeにアップした。こうでもしないと、テープを断捨離できない。
ごくごく短いジョージのアップショットが見たくて、繰り返し観賞したことは、正直に認める。このキラキラしたジョージの格好良さに参っていた。しかも、"I saw her standing there" の "Ooooooh!" で首を振ったジョージが、隣りのディラン(どう見ても楽屋からジョージに引きずり出されたようにしか見えない)に、ニコっと笑いかけるのは、決して見逃さない。ブルースとミックは、どちらがいつ、相手の顔に噛みついてもおかしくない。
ポールがジョンのプレゼンターを務めているが、この時ポールが小野洋子と話しているうちに、後に "Free as a bird" になるデモテープの存在が浮上したとのこと。
全体的に、エリック・クラプトンがおいしいところを持って行っている。ザ・バンドしかり、クリームしかり。でも、ザ・バンドには入れてやりませんよ。
クラプトンも50年代の大御所に比べるとひよっこに見える。"Soul Man" のバックに、ジョニー・キャッシュって凄いな。スティーヴ・ウィンウッドに至っては、さながらどこかの元気な小僧っ子。大御所連中の中には、フィル・スペクターの顔も見られる。
レイ・デイヴィスのスピーチはさすが。キースは…ええ、支離滅裂ですね。ポール・サイモンは性格が良いのか、悪いのか分からない。ボノ(ボブ・マーリーのプレゼンター)も上手い。
小さな男の子が、「いつかボクももらえると思います」とスピーチしているが、この子は誰の息子なんだろう?故人のはずがだが…?CCRのトム・フォガティの息子はもっと大きいし…
殿堂入りメンバーと、そのプレゼンターがどこかにリストになっていると良いのだが、今のところ見つけられないでいる。
なんだかんだと言っても、やはり一番面白かったのは、ジェフ・ベックのスピーチだ。この人、あんな顔をしているが、喋らせると面白い。
手始めに、ヤードバーズはクビになったんだから、喜べないというスピーチ。声が一部カットされているが、実はFワードをかましている。背後で、
そして、ロッドのプレゼンターとしては、彼との「愛憎関係」を素直に(?)認めている。やっぱり、ロックンローラーとはいえ、大英帝国人たるもの、この程度のスピーチはできなきゃイカンのだなぁと、妙に納得してしまった。
音大社長の訃報 ― 2011/05/09 22:14
まったく迂闊なことだが、大賀典雄さんが亡くなったことを、つい先日まで知らなかった。4月23日東京で、多臓器不全のため81歳で亡くなったそうだ。
正直なところ、ソニーというブランドに関して、個人的には強い信頼感を持っていない。高品質,コンセプトとデザインの良さ、使いやすさ、そしてブランド戦略の巧妙さは買っている。が、いかんせん骨太な信頼性がない。壊れる。変なところで異常に使いにくい。内向きにアレコレとアイディアを出して自己満足に陥る。ウォークマンの栄光に縋りすぎる。新しいPCを購入するに当たっても、国内メジャーに限定したが、ソニーは最初から除外していた。
ともあれ、ソニーは日本を代表する、そして典型的な日本クォリティのメーカーである。その繁栄を築いた人物として、大賀さんは欠かすことの出来ない人だった。そして、CDというある時代を作り上げた媒体の完成に、大きく貢献した人物でもある。私は正に、彼に感謝すべき世代だ。
大賀さんは、その異色の経歴がよく知られている。静岡県出身。音楽が盛んな土地柄だ。戦後まもなく、東京芸術大学の声楽家に進学した(バリトン)。在校中に、当時東京通信工業と呼ばれていたソニーのテープレコーダーにクレームをしたのがきっかけになり、ソニーに入社した。そうは言ってもミュンヘン国立高等音楽大学、ベルリン国立芸術学部へ留学,卒業したので、音楽の方は中途半端なレベルではなかったようだ。
新進の会社ではあり得ることだったのだろう、大賀さんは34歳でソニーの取締役に就任。その後、社長,CEOを歴任した。その間、CBSやコロンビアを買収したり、MDを作ったり、ゲームジャンルに打って出たり。経営者としてはやり手という印象が強く、その世間での印象や評価については、あまり知らない。
私にとって印象深いのは、なんと言ってもCDの普及に貢献したことであり、そのことについて、友人カラヤンと何度も意見交換をしていたということだ。カラヤンが亡くなったときも、身近に居た。
もう一つ印象的なのは、退職金16億円(!高いのか?安いのか?)を軽井沢町に寄付し、これでもって軽井沢大賀ホールが作られたことだ。私は去年、初めて大賀ホールに行き、その音響の良さに仰天した。正直言って、プログラム的にはあの音響を活かし切っていないのではないかという感想すら持った。
ほかにも、東京国際オーボエ・コンクール(現:軽井沢国際オーボエ・コンクール)を創設したり、指揮者として活動したりと、音楽に寄与し続けた。
私が訃報をまったく知らなかったくらいだから、あまり報道されなかったのだろうか。確かに昨今の日本は他にニュースが多すぎるのだろう。
正直なところ、ソニーというブランドに関して、個人的には強い信頼感を持っていない。高品質,コンセプトとデザインの良さ、使いやすさ、そしてブランド戦略の巧妙さは買っている。が、いかんせん骨太な信頼性がない。壊れる。変なところで異常に使いにくい。内向きにアレコレとアイディアを出して自己満足に陥る。ウォークマンの栄光に縋りすぎる。新しいPCを購入するに当たっても、国内メジャーに限定したが、ソニーは最初から除外していた。
ともあれ、ソニーは日本を代表する、そして典型的な日本クォリティのメーカーである。その繁栄を築いた人物として、大賀さんは欠かすことの出来ない人だった。そして、CDというある時代を作り上げた媒体の完成に、大きく貢献した人物でもある。私は正に、彼に感謝すべき世代だ。
大賀さんは、その異色の経歴がよく知られている。静岡県出身。音楽が盛んな土地柄だ。戦後まもなく、東京芸術大学の声楽家に進学した(バリトン)。在校中に、当時東京通信工業と呼ばれていたソニーのテープレコーダーにクレームをしたのがきっかけになり、ソニーに入社した。そうは言ってもミュンヘン国立高等音楽大学、ベルリン国立芸術学部へ留学,卒業したので、音楽の方は中途半端なレベルではなかったようだ。
新進の会社ではあり得ることだったのだろう、大賀さんは34歳でソニーの取締役に就任。その後、社長,CEOを歴任した。その間、CBSやコロンビアを買収したり、MDを作ったり、ゲームジャンルに打って出たり。経営者としてはやり手という印象が強く、その世間での印象や評価については、あまり知らない。
私にとって印象深いのは、なんと言ってもCDの普及に貢献したことであり、そのことについて、友人カラヤンと何度も意見交換をしていたということだ。カラヤンが亡くなったときも、身近に居た。
もう一つ印象的なのは、退職金16億円(!高いのか?安いのか?)を軽井沢町に寄付し、これでもって軽井沢大賀ホールが作られたことだ。私は去年、初めて大賀ホールに行き、その音響の良さに仰天した。正直言って、プログラム的にはあの音響を活かし切っていないのではないかという感想すら持った。
ほかにも、東京国際オーボエ・コンクール(現:軽井沢国際オーボエ・コンクール)を創設したり、指揮者として活動したりと、音楽に寄与し続けた。
私が訃報をまったく知らなかったくらいだから、あまり報道されなかったのだろうか。確かに昨今の日本は他にニュースが多すぎるのだろう。
忘れがたき The Last Waltz ― 2011/05/11 21:03
最近ずっと通勤音楽のiPodは、アーチストを選び、その全アルバムをランダムに聴き通すというスタイルでいる。ディラン,TP&HB,ジョージ,ストーンズ,シスター・ヘイゼル,イーグルアイ・チェリー,バーズ,ビートルズと来て、昨日ザ・バンドを聞き終わった。
ザ・バンドに関しては、かなり好きなバンドの一つではあるが、[The Last Waltz] までに限定している。逆に言えば、[LW] が最高。バンドの内情にも、再結成にもあまり興味がない。
iPodはアルバム再生順をランダムにしていたのだが、偶然にも最後に来たのが、[The Last Waltz](完全版)の、Disc3, つまりコンサートの最後の部分になった。完璧な終わり方だと思いながらしみじみと浸っていると、これまでほとんど気にしなかった最後のアナウンスに興味をひかれた。出演したアーチストたちの名前を挙げて感謝を述べているのだが、その中に「スティーヴン・スティルス」の名があった。
ハタと思った。私の記憶の[LW] には、スティーヴン・スティルスの姿が無い。一体どこに出てきただろうか?
どうやら、"I Shall Be Released" 後のジャムに出ているらしい。映画のDVD完全版にはジャムも収録されていたのだが、それでも思い出せない。仕方が無いので、久しぶりに映像を確認することにした。
とは言っても、私はスティルスにそれほど詳しくない。あの大勢がステージにひしめいていたら、見つけることが出来ないかも知れない。スティルスの外見と言えば…薄頭。よし、薄頭を目印にすれば良いんだな!(女ってのは本当に無神経なものだ)
すぐ見つかった。しかも目立つ登場の仕方だった。ジャムもたけなわの中、ロビーと一緒にノコノコ手ぶらで出てくる。しばしエアギター。

ロビーがストラトを貸してくれた。

ちょっと…微妙な空気なのか、ニール・ヤングが背を向けて、どんどん遠ざかる。

なんてね♪笑いながら来てくれた!

でも、この直後にカメラが耐えられなくなり、映像が切れちゃうのでありました。
スティルスがエアギターを始めた瞬間に、私は思い出した。完全版DVD を見た青山陽一が、日記であのエアギターに突っ込みが入れていたのだ。どうしてきれいサッパリ忘れていたのだろうか。
完全版が発売されたとき、ロビーは来日してトークショーをやったのだが、その場に青山陽一も、そして私も、他198名と一緒に居た。そしてサインをもらい、握手をした。その時のサインをどこにしまったのかも、ついでに忘れていたのだが、今回完全版のCDボックスを久しぶりに開いたら、そこに挟まっていた。
ごめんね、ロビー。大事にするよ。
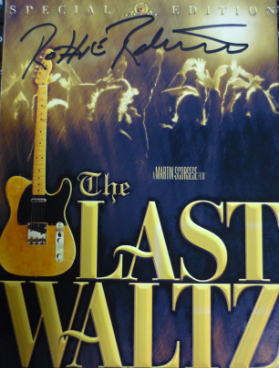
ザ・バンドに関しては、かなり好きなバンドの一つではあるが、[The Last Waltz] までに限定している。逆に言えば、[LW] が最高。バンドの内情にも、再結成にもあまり興味がない。
iPodはアルバム再生順をランダムにしていたのだが、偶然にも最後に来たのが、[The Last Waltz](完全版)の、Disc3, つまりコンサートの最後の部分になった。完璧な終わり方だと思いながらしみじみと浸っていると、これまでほとんど気にしなかった最後のアナウンスに興味をひかれた。出演したアーチストたちの名前を挙げて感謝を述べているのだが、その中に「スティーヴン・スティルス」の名があった。
ハタと思った。私の記憶の[LW] には、スティーヴン・スティルスの姿が無い。一体どこに出てきただろうか?
どうやら、"I Shall Be Released" 後のジャムに出ているらしい。映画のDVD完全版にはジャムも収録されていたのだが、それでも思い出せない。仕方が無いので、久しぶりに映像を確認することにした。
とは言っても、私はスティルスにそれほど詳しくない。あの大勢がステージにひしめいていたら、見つけることが出来ないかも知れない。スティルスの外見と言えば…薄頭。よし、薄頭を目印にすれば良いんだな!(女ってのは本当に無神経なものだ)
すぐ見つかった。しかも目立つ登場の仕方だった。ジャムもたけなわの中、ロビーと一緒にノコノコ手ぶらで出てくる。しばしエアギター。

ロビーがストラトを貸してくれた。

ちょっと…微妙な空気なのか、ニール・ヤングが背を向けて、どんどん遠ざかる。

なんてね♪笑いながら来てくれた!

でも、この直後にカメラが耐えられなくなり、映像が切れちゃうのでありました。
スティルスがエアギターを始めた瞬間に、私は思い出した。完全版DVD を見た青山陽一が、日記であのエアギターに突っ込みが入れていたのだ。どうしてきれいサッパリ忘れていたのだろうか。
完全版が発売されたとき、ロビーは来日してトークショーをやったのだが、その場に青山陽一も、そして私も、他198名と一緒に居た。そしてサインをもらい、握手をした。その時のサインをどこにしまったのかも、ついでに忘れていたのだが、今回完全版のCDボックスを久しぶりに開いたら、そこに挟まっていた。
ごめんね、ロビー。大事にするよ。
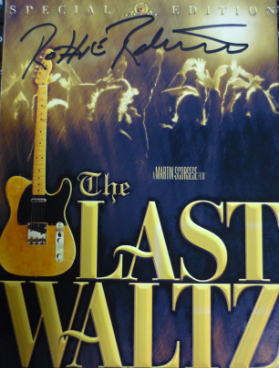
Morning Has Broken ― 2011/05/14 23:28
テレビを点けたら偶然、とある飲料メーカーのCMが流れており、その音楽がキャット・スティーヴンスの "Morning Has Broken" だった。
ただし、歌が入っているわけでは無く、インストゥルメンタルのカバーと言った方が適当のようだ。この曲はもともとスティーヴンスのオリジナルではなく、賛美歌のようなものらしいので、スティーヴンスのカバーという表現は正確ではなさそうだが、ともあれ彼の録音が非常に有名なので、そうとらえるのが自然だろう。
私が最初に "Morning Has Broken" を聞いたのは、ずいぶん昔だ。学生時代、生まれて初めて飛行機に乗ったとき、機内エンターテインメント・チャンネルで「AOR 特集」というものがあり、そこでこの曲を聴いた。アダルト・オリエンテッド・ロックという日本独特のカテゴライズに、スティーヴンスが当てはまるのかどうかは知らない。その場で曲名とアーチスト名をメモし、かなり長い間 - おそらく6, 7年は手帳の間にそのメモを挟んでおり、就職してCDが自由に帰るようになった頃、やっと収録アルバム [Teaser and the Firecat] を購入したという次第だ。
ともあれ、"Morning Has Broken" のライブ動画をどうぞ。
アルバムレコーディングの時、あの印象的なピアノを弾いていたのは、リック・ウェイクマン(イエス)だったそうだが、ライブ映像では、巨漢。…しかも巨大アフロ。ピアニストでこんな巨漢って、なかなか見たことが無い。ピアノとどっちがでかいだろうか。
感動的なのは、キャット・スティーヴンスが録音そのままの美しい声の持ち主であるところ。容姿もかなりグっと来る。
アルバムそのものも名作で、ほかにも "Moonshadow" や "Peace Train" などと言った名曲が含まれ、ビルボードで最高2位を記録している。プロデューサーは、元ヤードバーズのポール・サムウェル-スミス。ちなみに、同時期にジョン・レノンの "Imagine" や、ロッド・スチュワートの "Every Picture Tells A Story" などが発表されており、このことは、1971年という時期は60年代マジックが続いている、ロックの黄金期であることをまざまざと語っている。
キャット・スティーヴンスは、その後イスラムに改宗し、名前もユスフ・イスラムと改め、音楽活動から身を引いた。1985年のライブエイドの折には、久しぶりに公衆の面前に登場する予定だったが、前のエルトン・ジョンのセットが長引き、結局彼は登場できなかったという、酷い話がウィキペディアに載っていた。
実は、彼のアルバムは1枚しか持っていない。久しぶりに、初めて飛行機に乗って聞いたときの感動がよみがえったので、他のアルバムの買ってみようと思う。
ただし、歌が入っているわけでは無く、インストゥルメンタルのカバーと言った方が適当のようだ。この曲はもともとスティーヴンスのオリジナルではなく、賛美歌のようなものらしいので、スティーヴンスのカバーという表現は正確ではなさそうだが、ともあれ彼の録音が非常に有名なので、そうとらえるのが自然だろう。
私が最初に "Morning Has Broken" を聞いたのは、ずいぶん昔だ。学生時代、生まれて初めて飛行機に乗ったとき、機内エンターテインメント・チャンネルで「AOR 特集」というものがあり、そこでこの曲を聴いた。アダルト・オリエンテッド・ロックという日本独特のカテゴライズに、スティーヴンスが当てはまるのかどうかは知らない。その場で曲名とアーチスト名をメモし、かなり長い間 - おそらく6, 7年は手帳の間にそのメモを挟んでおり、就職してCDが自由に帰るようになった頃、やっと収録アルバム [Teaser and the Firecat] を購入したという次第だ。
ともあれ、"Morning Has Broken" のライブ動画をどうぞ。
アルバムレコーディングの時、あの印象的なピアノを弾いていたのは、リック・ウェイクマン(イエス)だったそうだが、ライブ映像では、巨漢。…しかも巨大アフロ。ピアニストでこんな巨漢って、なかなか見たことが無い。ピアノとどっちがでかいだろうか。
感動的なのは、キャット・スティーヴンスが録音そのままの美しい声の持ち主であるところ。容姿もかなりグっと来る。
アルバムそのものも名作で、ほかにも "Moonshadow" や "Peace Train" などと言った名曲が含まれ、ビルボードで最高2位を記録している。プロデューサーは、元ヤードバーズのポール・サムウェル-スミス。ちなみに、同時期にジョン・レノンの "Imagine" や、ロッド・スチュワートの "Every Picture Tells A Story" などが発表されており、このことは、1971年という時期は60年代マジックが続いている、ロックの黄金期であることをまざまざと語っている。
キャット・スティーヴンスは、その後イスラムに改宗し、名前もユスフ・イスラムと改め、音楽活動から身を引いた。1985年のライブエイドの折には、久しぶりに公衆の面前に登場する予定だったが、前のエルトン・ジョンのセットが長引き、結局彼は登場できなかったという、酷い話がウィキペディアに載っていた。
実は、彼のアルバムは1枚しか持っていない。久しぶりに、初めて飛行機に乗って聞いたときの感動がよみがえったので、他のアルバムの買ってみようと思う。
ボブ・ディランの反論 ― 2011/05/17 22:04
4月にボブ・ディランが、初めて中国でコンサートを行った。このニュースは無論キャッチしていたし、セットリストもチェック済みだった。批評家にしてみれば、彼らが期待するような反戦歌や、人権歌が含まれていなかったと、いくらか不満口調が見られたことも知っている。
この件に関しては特にこれといった興味もなかったのだが、どうやらディランは厳しい批判にさらされていたらしい。代表的なところでは、ニューヨーク・タイムズ紙が、「愚か(idiot)な風に吹かれて」と題して、「独裁国家で検閲された曲だけを歌うとは(中略)いかさま」と評した。人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチは、「恥知らず」と断言しているとのこと。私前者を読んでみたが、なるほどかなり厳しい。ほかにも、空席が多かった、外国人(中国人以外)ばかりだったなどなどと言われているそうだ。
そんな声など軽く受け流すのかと思いきや、なんとディラン自身が公式ホームページで、「ファンと、フォロワーのみなさんへ」というコメントを発表したというのだから、驚いた。
→ To my fans and followers / by Bob Dylan
要約してみる。
○ 去年、中国でコンサートをしようとして、中国当局に許可されなかったという事実はない。コンサート開催に失敗した中国のプロモーターが勝手にそうコメントしただけ。
○今回のシートはほぼ埋まっていたし、観客はほとんど中国の若者だった。
○中国のプレスは自分をさかんにジョーン・バエスやチェ・ゲバラ、ジャック・ケロアク,アレン・ギンズバーグの写真とともに60年代の象徴にしようとしていたが、会場の若者たちは彼らのことなんて知らないだろう。
○盛り上がったのは最近の曲で、観客たちは昔の曲は知らなかっただろう。
○コンサートの3ヶ月前にセットリストを当局に提出したが、その内容に関しては、何も言われなかった。
○自分の事を書いた本がやたらとあるものだが、その中には、良いことが書いてるのもあるかもね。
全体的に、「まぁ、そうなんだろうな」というのが、私の感想。ただし、「最近の曲の方が盛り上がり、古い曲は知らないだろう」というのは、どうかな。
おそらく最も重要な点だと思うが、当局が許可した曲のみ(つまり、検閲済み)のセットリストだったのかという点。ディランは明確に否定している。
確かに、3ヶ月前にセットリストを出すというのは異例だと思うが、かと言って検閲済みかと言えば - 実際の曲目を見ると、そういう印象は受けない。
北京のセットリスト
Gonna Change My Way of Thinking
It's All Over Now, Baby Blue
Beyond Here Lies Nothin'
Tangled Up in Blue
Honest With Me
Simple Twist of Fate
Tweedle Dee and Tweedle Dum
Love Sick
Rollin' and Tumblin'
A Hard Rain's A-Gonna Fall
Highway 61 Revisited
Spirit on the Water
Thunder on the Mountain
Ballad of a Thin Man
Like a Rolling Stone
All Along the Watchtower
Forever Young
上海のセットリスト
Gonna Change My Way Of Thinking
Don't Think Twice, It's All Right
Things Have Changed
Tangled Up In Blue
Honest With Me
Simple Twist Of Fate
Tweedle Dee & Tweedle Dum
Blind Willie McTell
The Levee's Gonna Break
Desolation Row
Highway 61 Revisited
Spirit On The Water
Thunder On The Mountain
Ballad Of A Thin Man
Like A Rolling Stone
Forever Young
人権団体やコラムニストたちが期待した、「風に吹かれて」や、「時代は変わる」が検閲で禁止されたとしたら、「激しい雨が降る」や、「デソレーション・ロウ」が許可されるのは納得できない。他にも解釈によっては反戦や人権問題を歌った物ととらえることの曲もある。
もっと直感的に言えば、日本公演でのセットリストと大差が無いのだ。ディランも言っているとおり、歌いたい曲を歌っただけと、私には感じられる。
人によっては、どうしても「ボブ・ディランは、こういうボブ・ディランであってほしい」という欲求から抜けきれないのだろう。自分たちが望んだとおりの行動をしないディランに失望し、裏切られたと感じるのだろうが、ディランにしてみれば迷惑な話だろう。
実際、彼は60年代すでにその迷惑を被り、それに立ち向かったり、逃げたり、だんまりを決め込んだり、さんざんやり合ってきている。いまや21世紀。それでもなお、ディランに夢と理想を託し、その通りに行動することを望んでいる人も、少なからず居るのだという事実に、60,70年代を知らない私は、あらためて驚いてしまった。
それほどまでに、ディランは偉大であり、影響力があるのだと言うこともまた、真実だ。ディランがディランとして歌い続ける以上、同様のやりとりは、繰り返されるのかも知れない。
私にとっては、正直言って今回の論争はどうでも良いし、特に誰がどうしなきゃいけなかったという意見を持っていない。ただただ、ディランとその音楽が好きなだけで、論争とは距離をとって、こんな曲に浸っていたいと思うのだ。
この件に関しては特にこれといった興味もなかったのだが、どうやらディランは厳しい批判にさらされていたらしい。代表的なところでは、ニューヨーク・タイムズ紙が、「愚か(idiot)な風に吹かれて」と題して、「独裁国家で検閲された曲だけを歌うとは(中略)いかさま」と評した。人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチは、「恥知らず」と断言しているとのこと。私前者を読んでみたが、なるほどかなり厳しい。ほかにも、空席が多かった、外国人(中国人以外)ばかりだったなどなどと言われているそうだ。
そんな声など軽く受け流すのかと思いきや、なんとディラン自身が公式ホームページで、「ファンと、フォロワーのみなさんへ」というコメントを発表したというのだから、驚いた。
→ To my fans and followers / by Bob Dylan
要約してみる。
○ 去年、中国でコンサートをしようとして、中国当局に許可されなかったという事実はない。コンサート開催に失敗した中国のプロモーターが勝手にそうコメントしただけ。
○今回のシートはほぼ埋まっていたし、観客はほとんど中国の若者だった。
○中国のプレスは自分をさかんにジョーン・バエスやチェ・ゲバラ、ジャック・ケロアク,アレン・ギンズバーグの写真とともに60年代の象徴にしようとしていたが、会場の若者たちは彼らのことなんて知らないだろう。
○盛り上がったのは最近の曲で、観客たちは昔の曲は知らなかっただろう。
○コンサートの3ヶ月前にセットリストを当局に提出したが、その内容に関しては、何も言われなかった。
○自分の事を書いた本がやたらとあるものだが、その中には、良いことが書いてるのもあるかもね。
全体的に、「まぁ、そうなんだろうな」というのが、私の感想。ただし、「最近の曲の方が盛り上がり、古い曲は知らないだろう」というのは、どうかな。
おそらく最も重要な点だと思うが、当局が許可した曲のみ(つまり、検閲済み)のセットリストだったのかという点。ディランは明確に否定している。
確かに、3ヶ月前にセットリストを出すというのは異例だと思うが、かと言って検閲済みかと言えば - 実際の曲目を見ると、そういう印象は受けない。
北京のセットリスト
Gonna Change My Way of Thinking
It's All Over Now, Baby Blue
Beyond Here Lies Nothin'
Tangled Up in Blue
Honest With Me
Simple Twist of Fate
Tweedle Dee and Tweedle Dum
Love Sick
Rollin' and Tumblin'
A Hard Rain's A-Gonna Fall
Highway 61 Revisited
Spirit on the Water
Thunder on the Mountain
Ballad of a Thin Man
Like a Rolling Stone
All Along the Watchtower
Forever Young
上海のセットリスト
Gonna Change My Way Of Thinking
Don't Think Twice, It's All Right
Things Have Changed
Tangled Up In Blue
Honest With Me
Simple Twist Of Fate
Tweedle Dee & Tweedle Dum
Blind Willie McTell
The Levee's Gonna Break
Desolation Row
Highway 61 Revisited
Spirit On The Water
Thunder On The Mountain
Ballad Of A Thin Man
Like A Rolling Stone
Forever Young
人権団体やコラムニストたちが期待した、「風に吹かれて」や、「時代は変わる」が検閲で禁止されたとしたら、「激しい雨が降る」や、「デソレーション・ロウ」が許可されるのは納得できない。他にも解釈によっては反戦や人権問題を歌った物ととらえることの曲もある。
もっと直感的に言えば、日本公演でのセットリストと大差が無いのだ。ディランも言っているとおり、歌いたい曲を歌っただけと、私には感じられる。
人によっては、どうしても「ボブ・ディランは、こういうボブ・ディランであってほしい」という欲求から抜けきれないのだろう。自分たちが望んだとおりの行動をしないディランに失望し、裏切られたと感じるのだろうが、ディランにしてみれば迷惑な話だろう。
実際、彼は60年代すでにその迷惑を被り、それに立ち向かったり、逃げたり、だんまりを決め込んだり、さんざんやり合ってきている。いまや21世紀。それでもなお、ディランに夢と理想を託し、その通りに行動することを望んでいる人も、少なからず居るのだという事実に、60,70年代を知らない私は、あらためて驚いてしまった。
それほどまでに、ディランは偉大であり、影響力があるのだと言うこともまた、真実だ。ディランがディランとして歌い続ける以上、同様のやりとりは、繰り返されるのかも知れない。
私にとっては、正直言って今回の論争はどうでも良いし、特に誰がどうしなきゃいけなかったという意見を持っていない。ただただ、ディランとその音楽が好きなだけで、論争とは距離をとって、こんな曲に浸っていたいと思うのだ。
Figaro, Figaro, Figaro... ― 2011/05/20 23:29
オリックス・バファローズの新外国人投手は、名前をアルフレッド・フィガロと言う。実在人物で「フィガロ」という人を、初めて知った。
「フィガロ」と言えば、新聞や雑誌、車の名前に使われているが、なんと言っても元ネタはボーマルシェ(フランス,1732-1799)の戯曲の登場人物で、モーツァルトがオペラ「フィガロの結婚」を作曲したことで有名になった。
このフィガロは、庶民型のヒーローで、豊かでは無くとも知恵と勇気と行動力で、貴族や金持ちたちを手玉に取る痛快な男として活躍する。バリトン(もしくはリリックバス)が担当するこの役柄は、恋をする以外は大方役立たずが多いオペラの主役男性たちの中では、際だった存在だ。私は特にオペラが好きなわけでは無いが、このフィガロのキャラクターが好きで、一時期はまったことがある。
モーツァルトの代表的なオペラでは、テノールではなくバス,バリトンに口八丁手八丁、頭の良い役を持ってくる。テノールが苦手な私には、その点も合っていたのだろう。
まず最初に、フィガロと言えばこれ。「フィガロの結婚」第一幕から、「もう飛ぶまいぞこの蝶々」アメリカ人歌手、サミュエル・レイミー。
若く可愛い男の子に迫っているように見えるが、実際はケルビーノという、恋愛ごっこにうつつを抜かす小姓が、主人の怒りに触れて出征することになり、「もう着飾って蝶々のように遊び飛び回ることも出来ないぞ」と、からかっている場面である。
レイミーと言えば、ドン・ジョヴァンニやエスカミーリョ役が印象的だが、このフィガロも、歯切れが良くて好きだ。演出的には、スザンナがただ座っているだけなのがヘンテコ。
お次は、同じく「フィガロの結婚」第一幕から、「伯爵様、もし踊りたいのなら」。イタリア人、フェルッチョ・フルラネット。
埋め込みが無いので、このリンクでどうぞ。
フィガロが結婚を目前にして、主人アルマヴィーヴァ伯爵の良からぬもくろみを察知し、「そうはさせませんよ」と、貴族相手に戦ってやる決心を歌うシーン。手に定規を持っているのは、ついさっきまで、この定規で新婚夫婦の部屋の広さを測っていたから。
フルラネットは、フィガロが当たり役だと思うのだが、どうだろう。「ドン・ジョヴァンニ」のレポレッロも良いので、オペラ・ブッファ(モーツァルトが得意な、軽妙な喜劇オペラ)が向いているのだろう。
ボーマルシェの戯曲は三部作になっており、「フィガロの結婚」はその二作目にあたる。一作目が「セヴィリアの理髪師」で、モーツァルトが「結婚」を発表する数年前に、パイジェッロがオペラにしている。しかし「理髪師」は、なんと言ってもモーツァルトらの約30年後に、ロッシーニが作曲したバージョンが有名だ。
「理髪師」とは、実はフィガロのこと。フィガロはセヴィリアでは名の知れた存在で、町の何でも屋を兼ねている。独身時代のアルマヴィーヴァ伯爵が、一目惚れしたロジーナと結婚したいがために、フィガロに協力を求め、あの手この手を尽くすのが、「理髪師」のあらすじである。
無事にロジーナと結婚した伯爵が、フィガロを家来として雇ってからの物語が「結婚」というわけだ。ロッシーニ版の「理髪師」には、「フィガロの娘に…」という台詞があり、すわ「フィガロの重婚?!」…という突っ込みが必ず入るのだが、これはもちろん、脚本作家のミスである。
と、言うわけで「セヴィリアの理髪師」から、第一幕フィガロのアリア「私は町の何でも屋」。カナダのジーノ・キリコ。
自分を褒めまくる早口のフィガロ。ジーノ・キリコは、「ラ・ボエーム」のマルチェッロや、「チェネレントラ」のダンディーニが印象的だが、このフィガロもはまっている。
この舞台は、たぶんヴォルフガング・サヴァリッシュの指揮だったと思うが、音楽教師バジリオは、フルラネットが務めていた。
オペラの映像をよく見ていたのは学生時代なので、私が選ぶ歌手はやや古い。最近はどんな歌手が活躍しているのだろうか。
「フィガロ」と言えば、新聞や雑誌、車の名前に使われているが、なんと言っても元ネタはボーマルシェ(フランス,1732-1799)の戯曲の登場人物で、モーツァルトがオペラ「フィガロの結婚」を作曲したことで有名になった。
このフィガロは、庶民型のヒーローで、豊かでは無くとも知恵と勇気と行動力で、貴族や金持ちたちを手玉に取る痛快な男として活躍する。バリトン(もしくはリリックバス)が担当するこの役柄は、恋をする以外は大方役立たずが多いオペラの主役男性たちの中では、際だった存在だ。私は特にオペラが好きなわけでは無いが、このフィガロのキャラクターが好きで、一時期はまったことがある。
モーツァルトの代表的なオペラでは、テノールではなくバス,バリトンに口八丁手八丁、頭の良い役を持ってくる。テノールが苦手な私には、その点も合っていたのだろう。
まず最初に、フィガロと言えばこれ。「フィガロの結婚」第一幕から、「もう飛ぶまいぞこの蝶々」アメリカ人歌手、サミュエル・レイミー。
若く可愛い男の子に迫っているように見えるが、実際はケルビーノという、恋愛ごっこにうつつを抜かす小姓が、主人の怒りに触れて出征することになり、「もう着飾って蝶々のように遊び飛び回ることも出来ないぞ」と、からかっている場面である。
レイミーと言えば、ドン・ジョヴァンニやエスカミーリョ役が印象的だが、このフィガロも、歯切れが良くて好きだ。演出的には、スザンナがただ座っているだけなのがヘンテコ。
お次は、同じく「フィガロの結婚」第一幕から、「伯爵様、もし踊りたいのなら」。イタリア人、フェルッチョ・フルラネット。
埋め込みが無いので、このリンクでどうぞ。
フィガロが結婚を目前にして、主人アルマヴィーヴァ伯爵の良からぬもくろみを察知し、「そうはさせませんよ」と、貴族相手に戦ってやる決心を歌うシーン。手に定規を持っているのは、ついさっきまで、この定規で新婚夫婦の部屋の広さを測っていたから。
フルラネットは、フィガロが当たり役だと思うのだが、どうだろう。「ドン・ジョヴァンニ」のレポレッロも良いので、オペラ・ブッファ(モーツァルトが得意な、軽妙な喜劇オペラ)が向いているのだろう。
ボーマルシェの戯曲は三部作になっており、「フィガロの結婚」はその二作目にあたる。一作目が「セヴィリアの理髪師」で、モーツァルトが「結婚」を発表する数年前に、パイジェッロがオペラにしている。しかし「理髪師」は、なんと言ってもモーツァルトらの約30年後に、ロッシーニが作曲したバージョンが有名だ。
「理髪師」とは、実はフィガロのこと。フィガロはセヴィリアでは名の知れた存在で、町の何でも屋を兼ねている。独身時代のアルマヴィーヴァ伯爵が、一目惚れしたロジーナと結婚したいがために、フィガロに協力を求め、あの手この手を尽くすのが、「理髪師」のあらすじである。
無事にロジーナと結婚した伯爵が、フィガロを家来として雇ってからの物語が「結婚」というわけだ。ロッシーニ版の「理髪師」には、「フィガロの娘に…」という台詞があり、すわ「フィガロの重婚?!」…という突っ込みが必ず入るのだが、これはもちろん、脚本作家のミスである。
と、言うわけで「セヴィリアの理髪師」から、第一幕フィガロのアリア「私は町の何でも屋」。カナダのジーノ・キリコ。
自分を褒めまくる早口のフィガロ。ジーノ・キリコは、「ラ・ボエーム」のマルチェッロや、「チェネレントラ」のダンディーニが印象的だが、このフィガロもはまっている。
この舞台は、たぶんヴォルフガング・サヴァリッシュの指揮だったと思うが、音楽教師バジリオは、フルラネットが務めていた。
オペラの映像をよく見ていたのは学生時代なので、私が選ぶ歌手はやや古い。最近はどんな歌手が活躍しているのだろうか。
ウィルダネスからスポットシルヴァニア ― 2011/05/23 21:59
北軍ポトマック軍の司令官はジョージ・ミードのままだったが、実情としてはその上にいるグラントが、リー率いる南軍と対決することになった。
いよいよ、本格的な対決が始まったのが、1864年5月4日である。北軍はラピダン川を渡り、対岸のウィルダネスへと100000もの大軍で押し進んだ。このWildanessという土地だが、「荒野」とも、「樹海」とも訳されている。要するに下草の豊富な森である。南軍60000の編成は、第一軍ロングストリート,第二軍ユーエル,第三軍A.P.ヒル、およびスチュアートの大規模な騎兵団。まず、森の中でユーエルとヒルが北軍と衝突した。
リーとしては、できうる限り戦闘を森の中で行いたかった。環境の悪さのため、北軍は数の優位性を活かすことが出来ないだろうという目論見だが、さすがに倍近い軍勢には押される一方だった。森の中の戦闘は、火災も起こって負傷者が焼死するという惨状だった。翌5月5日も引き続き北軍は南軍を押し続け、ハンコック指揮下の第二軍は、リーの司令部まであと僅かというところまで迫った。
そこに、遅れてウィルダネスに到着したロングストリートの第一軍が現れて、形勢が逆転した。ハンコックの軍は攻勢に疲労しており、ロングストリートの勢いに瞬く間に押し戻された。さらに、間近にまで敵が迫ったことが影響したのか、リーが自ら前線へと体を向けて戦闘指揮を行おうとしたのである。さすがに総大将を守るべく兵たちはリーを押しとどめ、前へと出て行った。
北軍ハンコックが決定的な損害を受けなかったのは、ロングストリートが混乱の中で自軍の銃弾に当たり、指揮不能に陥ったためである。1年前、ストーンウォール・ジャクソンが死んだのと同じ状況ではあったが、ロングストリートの場合は致命傷にはならなかった。ともあれ、彼は護送され、第一軍の指揮はアンダーソン少将にゆだねられた。
このウィルダネスの戦いで、北軍の損害は17600だったのに対し、南軍は8000だった。勝敗で言えば、南軍の勝利と言うべきだが、かと言って北軍もワシントンへ撤退したわけでも無かった。グラントはいったん力を抜いて、戦場を変えることにしたのである。このためウィルダネスの戦いは引き分けというのが、大方の見方のようだ。
グラントは、森の中で負けたとしてもワシントンへ逃げ帰る気は毛頭無かった。彼はポトマック軍を南東方向へ動かした。すなわち、少しずつ南軍首都のリッチモンドへ近づいていくという動きである。北軍は、辻街道沿いの町スポットシルヴァニア・コートハウスへ向かった。
リーも北軍のこの動きは察知しており、機動性に優れるスチュアートの騎兵を先行させ、5月9日には先にスポットシルヴァニア・コートハウスに達した。
北軍第六軍を指揮するのは、ジョン・セジウィック少将だった。セジウィックは南軍に対する防御線を築き、大砲を配置していたのだが、この時珍事が起こった。
セジウィックの防御・斥候ラインに対する南軍の狙撃が激しかったため、北軍兵たちは物陰に隠れてそれを避けていた。それを見たセジウィックは大胆にも出てきて、「弾ひとつかわすのに、なんだそれは。みっともない。この距離では、象にだって当たらないぞ。」と、部下たちを励ました。
セジウィックがそう言った直後、顔面に狙撃兵の弾が当たり、彼はほぼ即死してしまった。
その報を聞いたグラントは、「本当に死んだのか?本当に死んだのか?」と、何度も聞き返したと言う。
小説などでは、兵士たちを勇気づける優秀で剛胆な将官は、銃弾など恐れずに陣頭に立ち、実際かすり傷一つも負わないものだが(参照:司馬遼太郎,「燃えよ剣」の土方歳三 / 「坂の上の雲」の秋山好古)、どうもセジウィックにはその格好良さは許されなかったようだ。
ともあれ、戦闘は完全にスポットシルヴァニアに移動した。本格的な衝突が始まると同時に、南北双方の騎兵団が戦場を変えて戦うことになったが、このことは後述する。
スポットシルヴァニアでは、北軍が南軍の弱点を見つけては突き、その都度南軍の猛攻に跳ね返されるという繰り返しになった。リーはまた自ら戦闘指揮を執って出ようとしたが、南軍の兵士たちは彼らの大事な将軍を守るために、「リー将軍を後方へ!」と合い言葉に奮戦を繰り返した。
この局面での戦闘は長く続き、5月20日にやっと一段落した。グラントはリーに対してまともな攻撃を続けることは,消耗し続けるだけだと悟ったのである。グラントは5月21日にスポットシルヴァニアを放棄し、再び南東へと戦場を変えるべく、移動を開始した。
このスポットシルヴァニア・コートハウスでは、北軍の損害36000。南軍はその約半分だったが、今回もまた引き分けという見方が体勢を占めている。重要なのは南北双方とも消耗したということだった。リーの辛さは、戦闘での損害比較上は勝っても、その損害を補強することが出来なかったことである。南部連合の体力は、もうほとんど尽きようとしていた。
一方、恐ろしいほどの損害を出し続ける北軍には、豊富な補強力があった。ニューヨークにやってきたヨーロッパからの移民が、そのまま戦場に送られるという凄まじさであった。
いよいよ、本格的な対決が始まったのが、1864年5月4日である。北軍はラピダン川を渡り、対岸のウィルダネスへと100000もの大軍で押し進んだ。このWildanessという土地だが、「荒野」とも、「樹海」とも訳されている。要するに下草の豊富な森である。南軍60000の編成は、第一軍ロングストリート,第二軍ユーエル,第三軍A.P.ヒル、およびスチュアートの大規模な騎兵団。まず、森の中でユーエルとヒルが北軍と衝突した。
リーとしては、できうる限り戦闘を森の中で行いたかった。環境の悪さのため、北軍は数の優位性を活かすことが出来ないだろうという目論見だが、さすがに倍近い軍勢には押される一方だった。森の中の戦闘は、火災も起こって負傷者が焼死するという惨状だった。翌5月5日も引き続き北軍は南軍を押し続け、ハンコック指揮下の第二軍は、リーの司令部まであと僅かというところまで迫った。
そこに、遅れてウィルダネスに到着したロングストリートの第一軍が現れて、形勢が逆転した。ハンコックの軍は攻勢に疲労しており、ロングストリートの勢いに瞬く間に押し戻された。さらに、間近にまで敵が迫ったことが影響したのか、リーが自ら前線へと体を向けて戦闘指揮を行おうとしたのである。さすがに総大将を守るべく兵たちはリーを押しとどめ、前へと出て行った。
北軍ハンコックが決定的な損害を受けなかったのは、ロングストリートが混乱の中で自軍の銃弾に当たり、指揮不能に陥ったためである。1年前、ストーンウォール・ジャクソンが死んだのと同じ状況ではあったが、ロングストリートの場合は致命傷にはならなかった。ともあれ、彼は護送され、第一軍の指揮はアンダーソン少将にゆだねられた。
このウィルダネスの戦いで、北軍の損害は17600だったのに対し、南軍は8000だった。勝敗で言えば、南軍の勝利と言うべきだが、かと言って北軍もワシントンへ撤退したわけでも無かった。グラントはいったん力を抜いて、戦場を変えることにしたのである。このためウィルダネスの戦いは引き分けというのが、大方の見方のようだ。
グラントは、森の中で負けたとしてもワシントンへ逃げ帰る気は毛頭無かった。彼はポトマック軍を南東方向へ動かした。すなわち、少しずつ南軍首都のリッチモンドへ近づいていくという動きである。北軍は、辻街道沿いの町スポットシルヴァニア・コートハウスへ向かった。
リーも北軍のこの動きは察知しており、機動性に優れるスチュアートの騎兵を先行させ、5月9日には先にスポットシルヴァニア・コートハウスに達した。
北軍第六軍を指揮するのは、ジョン・セジウィック少将だった。セジウィックは南軍に対する防御線を築き、大砲を配置していたのだが、この時珍事が起こった。
セジウィックの防御・斥候ラインに対する南軍の狙撃が激しかったため、北軍兵たちは物陰に隠れてそれを避けていた。それを見たセジウィックは大胆にも出てきて、「弾ひとつかわすのに、なんだそれは。みっともない。この距離では、象にだって当たらないぞ。」と、部下たちを励ました。
セジウィックがそう言った直後、顔面に狙撃兵の弾が当たり、彼はほぼ即死してしまった。
その報を聞いたグラントは、「本当に死んだのか?本当に死んだのか?」と、何度も聞き返したと言う。
小説などでは、兵士たちを勇気づける優秀で剛胆な将官は、銃弾など恐れずに陣頭に立ち、実際かすり傷一つも負わないものだが(参照:司馬遼太郎,「燃えよ剣」の土方歳三 / 「坂の上の雲」の秋山好古)、どうもセジウィックにはその格好良さは許されなかったようだ。
ともあれ、戦闘は完全にスポットシルヴァニアに移動した。本格的な衝突が始まると同時に、南北双方の騎兵団が戦場を変えて戦うことになったが、このことは後述する。
スポットシルヴァニアでは、北軍が南軍の弱点を見つけては突き、その都度南軍の猛攻に跳ね返されるという繰り返しになった。リーはまた自ら戦闘指揮を執って出ようとしたが、南軍の兵士たちは彼らの大事な将軍を守るために、「リー将軍を後方へ!」と合い言葉に奮戦を繰り返した。
この局面での戦闘は長く続き、5月20日にやっと一段落した。グラントはリーに対してまともな攻撃を続けることは,消耗し続けるだけだと悟ったのである。グラントは5月21日にスポットシルヴァニアを放棄し、再び南東へと戦場を変えるべく、移動を開始した。
このスポットシルヴァニア・コートハウスでは、北軍の損害36000。南軍はその約半分だったが、今回もまた引き分けという見方が体勢を占めている。重要なのは南北双方とも消耗したということだった。リーの辛さは、戦闘での損害比較上は勝っても、その損害を補強することが出来なかったことである。南部連合の体力は、もうほとんど尽きようとしていた。
一方、恐ろしいほどの損害を出し続ける北軍には、豊富な補強力があった。ニューヨークにやってきたヨーロッパからの移民が、そのまま戦場に送られるという凄まじさであった。
Ringo !! ― 2011/05/26 22:30
人間だれしも、時々「リンゴー!!」と、叫びたくなるものだ。
デイリーメールのインタビューで、リンゴ・スターが、「ザ・ビートルズは僕を加入させることができてラッキーだった」と語ったそうだ。
確かにそうだろう。ジョン,ポール,ジョージはいくらか必然性をもってつるみ、バンドを組んでいたが、ぎりぎりのタイミングでリンゴを入れるに致る経緯は、多分にラッキーと言えるだろう。どんなにリンゴより音楽的才能に優れたドラマーが居たとしても、ビートルズにとってリンゴ以上の人材は無い。
などと言っておいてどうかとも思うが、リンゴをネタにした動画が色々面白い。
Ringo Wants to Sing More
ごめん、リンゴ。面白い。あからさまにかったるそうな3人をよそに、やる気満々で歌わせろ!…なリンゴ。最後に車にひかれるかとヒヤヒヤした。
もっとヒドいのはアメリカのアニメ「ファミリー・ガイ」。クールでニヒルな犬のブライアンが容赦ない。
「そりゃ時間の無駄だ。リンゴ・スターのソングライティングみたいにな。」
「曲を書いたよ!」
「凄ーい!冷蔵庫に貼っとけば毎日見えるよ!」
そりゃ、ひどいよブライアン!でも笑えるから許す!
可愛い動画もある。
色々なリンゴが次から次へと。お好みのリンゴはどれ?
ついでに、素敵なアビーロード。
ビクビクするジョージが可愛い。一体何におびえているのかと思ったら…わぁ、地味に怖いわぁ…
デイリーメールのインタビューで、リンゴ・スターが、「ザ・ビートルズは僕を加入させることができてラッキーだった」と語ったそうだ。
確かにそうだろう。ジョン,ポール,ジョージはいくらか必然性をもってつるみ、バンドを組んでいたが、ぎりぎりのタイミングでリンゴを入れるに致る経緯は、多分にラッキーと言えるだろう。どんなにリンゴより音楽的才能に優れたドラマーが居たとしても、ビートルズにとってリンゴ以上の人材は無い。
などと言っておいてどうかとも思うが、リンゴをネタにした動画が色々面白い。
Ringo Wants to Sing More
ごめん、リンゴ。面白い。あからさまにかったるそうな3人をよそに、やる気満々で歌わせろ!…なリンゴ。最後に車にひかれるかとヒヤヒヤした。
もっとヒドいのはアメリカのアニメ「ファミリー・ガイ」。クールでニヒルな犬のブライアンが容赦ない。
「そりゃ時間の無駄だ。リンゴ・スターのソングライティングみたいにな。」
「曲を書いたよ!」
「凄ーい!冷蔵庫に貼っとけば毎日見えるよ!」
そりゃ、ひどいよブライアン!でも笑えるから許す!
可愛い動画もある。
色々なリンゴが次から次へと。お好みのリンゴはどれ?
ついでに、素敵なアビーロード。
ビクビクするジョージが可愛い。一体何におびえているのかと思ったら…わぁ、地味に怖いわぁ…
Wild Mountain Thyme ― 2011/05/29 22:50
7月に、某カルチャーセンターで「アイリッシュケルトを奏でる」というレクチャーコンサートが開かれる。その告知チラシには、こうあった。
アイルランド音楽の世界。「ダニーボーイ」「庭の千草」、ボブ・ディランもカバーしたという「ワイルド・マウンテン・タイム」など時代ごとに影響を与えた音楽の魅力を紹介します。
私はとっさに、「"Wild Mountain Thyme" をカバーしているのは、ディランじゃなくて、ザ・バーズ」と指摘してしまった。
とは言ったものの、ディランのことだ。どこでどんな曲を歌っているか分かったものでは無い。ゲーテなら大抵の事は言っているだろう。ディランなら大抵の曲は歌っているだろう…
ウィキペディアで実際に調べてみると、なるほどディランも歌っているらしい。しかし、その録音はブートレグ(公式ブートレグシリーズではない)のもので、やはり「カバーした」と表現されるにふさわしいのは、ザ・バーズの方だろう。彼らの録音は、アルバム [Fifthe Dimension] に収録されている。
1966年にしてすでに、ロックからフォークの原点に立ち戻っているあたり、さすがにバーズは突き抜けている。私はこの録音の "Wild Mountain Thyme" が一番好きだ。
"Wild Mountain Thyme" は18世紀末から19世紀初頭に生きたスコットランドの詩人,ロバート・タナヒルの作品をアレンジした物らしく、タイトルはほかに "Purple Heather" や "Will You Go Lassie, Go" などのバリエーションが存在する。タナヒルの国籍からすれば、この曲は厳密な意味でアイルランド音楽とは言えないかも知れない。しかし、20世紀になっておもにアイルランドのミュージシャンたちよって盛んに演奏,録音されてたため、代表的なアイルランド楽曲の一つになっている。
アイルランド音楽がアメリカ大陸に渡り、変容しただけあって、カントリーミュージシャンにも歌われている。
これは、カントリーの大物,ドン・ウィリアムズと、アイリッシュ・トラッド・ミュージックの雄,ザ・チーフテンズによる演奏。さすがに貫禄があって格好良い。ティン・ホイッスラーの私にとっては、背後で高音から舞い降りてくるホイッスルの音が、グっとくる。
最後に、アイルランド出身,アメリカに移住して活躍した、ザ・クランシー・ブラザーズの演奏。タイトルは、"Will ye go lassie go" を採用している。
ややカントリー向きに傾斜している編曲で、私の好みではないが ― やはりチーフテンズの方が胸に迫るし、バーズも軽さよりも深さを追求しているようで好きだ。
ともあれ、このクランシー・ブラザーズの楽天的な演奏にも、アイリッシュ独特の暗さが秘められている。クランシー・ブラザーズがディランの友人であり、彼に大きな影響を与えたことは有名だが、私がディランの好きなところの一つとしている、深い暗さ、哀切のようなものは、アイリッシュ・ミュージックから来ているのだとしたら、納得がいく。
アイルランド音楽の世界。「ダニーボーイ」「庭の千草」、ボブ・ディランもカバーしたという「ワイルド・マウンテン・タイム」など時代ごとに影響を与えた音楽の魅力を紹介します。
私はとっさに、「"Wild Mountain Thyme" をカバーしているのは、ディランじゃなくて、ザ・バーズ」と指摘してしまった。
とは言ったものの、ディランのことだ。どこでどんな曲を歌っているか分かったものでは無い。ゲーテなら大抵の事は言っているだろう。ディランなら大抵の曲は歌っているだろう…
ウィキペディアで実際に調べてみると、なるほどディランも歌っているらしい。しかし、その録音はブートレグ(公式ブートレグシリーズではない)のもので、やはり「カバーした」と表現されるにふさわしいのは、ザ・バーズの方だろう。彼らの録音は、アルバム [Fifthe Dimension] に収録されている。
1966年にしてすでに、ロックからフォークの原点に立ち戻っているあたり、さすがにバーズは突き抜けている。私はこの録音の "Wild Mountain Thyme" が一番好きだ。
"Wild Mountain Thyme" は18世紀末から19世紀初頭に生きたスコットランドの詩人,ロバート・タナヒルの作品をアレンジした物らしく、タイトルはほかに "Purple Heather" や "Will You Go Lassie, Go" などのバリエーションが存在する。タナヒルの国籍からすれば、この曲は厳密な意味でアイルランド音楽とは言えないかも知れない。しかし、20世紀になっておもにアイルランドのミュージシャンたちよって盛んに演奏,録音されてたため、代表的なアイルランド楽曲の一つになっている。
アイルランド音楽がアメリカ大陸に渡り、変容しただけあって、カントリーミュージシャンにも歌われている。
これは、カントリーの大物,ドン・ウィリアムズと、アイリッシュ・トラッド・ミュージックの雄,ザ・チーフテンズによる演奏。さすがに貫禄があって格好良い。ティン・ホイッスラーの私にとっては、背後で高音から舞い降りてくるホイッスルの音が、グっとくる。
最後に、アイルランド出身,アメリカに移住して活躍した、ザ・クランシー・ブラザーズの演奏。タイトルは、"Will ye go lassie go" を採用している。
ややカントリー向きに傾斜している編曲で、私の好みではないが ― やはりチーフテンズの方が胸に迫るし、バーズも軽さよりも深さを追求しているようで好きだ。
ともあれ、このクランシー・ブラザーズの楽天的な演奏にも、アイリッシュ独特の暗さが秘められている。クランシー・ブラザーズがディランの友人であり、彼に大きな影響を与えたことは有名だが、私がディランの好きなところの一つとしている、深い暗さ、哀切のようなものは、アイリッシュ・ミュージックから来ているのだとしたら、納得がいく。
最近のコメント