伶倫楽遊:祝賀の雅楽 ― 2018/05/27 21:15
5月25日、いつもの四谷区民ホールへ、伶楽舎の雅楽コンサートへ行った。
今回のテーマは、「祝賀の音楽」。お祝いの場で演じられる雅楽曲の特集だ。何かといちいち祝うのが平安貴族の世。つまり、祝わないではいられないほど、困難も多い時代だったということだろう。
それはさておき、この「祝賀の音楽」と聞いて、私もピンと来た一人だった。伶楽舎の音楽監督であり、私が音大で雅楽を習っていた芝祐靖先生が、去年文化勲章を受章されたことを祝うという意図のある会だったのだ。
お祝いの方法については色々話があったらしいが、結局、伶楽舎は伶楽舎らしく、お祝いの音楽を奏でることで、その気持ちを表し、雅楽ファンと共有することになった。素晴らしい選択だと思う。
そのようなわけで、今回は芝先生も観客席で観賞されていた。
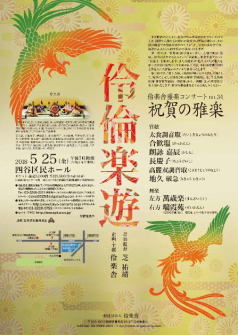
演目はまず、太食調の「合歓塩」「嘉辰」(朗詠)「長慶子」。学生のころ、お世話になった曲たちだ。朗詠を聞けたのも良かった
そして高麗双調の「地久」。高麗楽なので、笙が入らない。淡々と ― やや寂しい曲が進む感じが、なんだか不思議だった。
後半は舞楽。
まず左方の「萬歳楽」。4人の舞いで、華やか、かつ厳粛。これはお馴染み。
今回の演奏会の白眉は、何と言っても右方の「瑞霞苑」だろう。芝先生による新作雅楽で、オリジナルは1965年。伶楽舎が演奏するにあたって改訂がほどこされ、右方の舞いが加わった。
これが圧倒的に良かった。舞人は女性二人、緑の爽やかな装束も颯爽と、きびきびと舞う姿の美しさ、凛々しさが際立っていた。曲も明るく、晴れやかで軽やか。祝いの厳粛さよりも、心の軽さ、明るさ、活力に満ちて、希望を抱かせる。
この「瑞霞苑」が良すぎて、「萬歳楽」がかすんだほどだ。思わず、私は楽屋で楽員をつかまえ、そっと「後半は瑞霞苑だけで、一具をやったほうが良くなかった?」と囁いたほどだ。
客席にいらっしゃる芝先生の周りには、神社のように列ができて、挨拶が連綿と続いていた。先生もお疲れになるだろうから、どうしようか ― とも思ったが、我が楽しき音大時代と、先生と楽しく過ごした学生代表として、素通りはできなかった。
短い間だが、ご挨拶をして、お話をした。先生は私の同級生の名と共に、当時を懐かしむように、明るくわっていらした。
とても良い演奏会だった。雅楽初心者にもお勧めだった。
今回のテーマは、「祝賀の音楽」。お祝いの場で演じられる雅楽曲の特集だ。何かといちいち祝うのが平安貴族の世。つまり、祝わないではいられないほど、困難も多い時代だったということだろう。
それはさておき、この「祝賀の音楽」と聞いて、私もピンと来た一人だった。伶楽舎の音楽監督であり、私が音大で雅楽を習っていた芝祐靖先生が、去年文化勲章を受章されたことを祝うという意図のある会だったのだ。
お祝いの方法については色々話があったらしいが、結局、伶楽舎は伶楽舎らしく、お祝いの音楽を奏でることで、その気持ちを表し、雅楽ファンと共有することになった。素晴らしい選択だと思う。
そのようなわけで、今回は芝先生も観客席で観賞されていた。
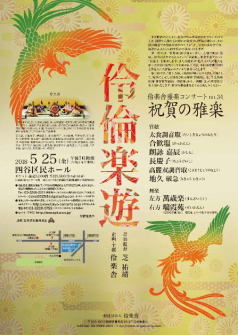
演目はまず、太食調の「合歓塩」「嘉辰」(朗詠)「長慶子」。学生のころ、お世話になった曲たちだ。朗詠を聞けたのも良かった
そして高麗双調の「地久」。高麗楽なので、笙が入らない。淡々と ― やや寂しい曲が進む感じが、なんだか不思議だった。
後半は舞楽。
まず左方の「萬歳楽」。4人の舞いで、華やか、かつ厳粛。これはお馴染み。
今回の演奏会の白眉は、何と言っても右方の「瑞霞苑」だろう。芝先生による新作雅楽で、オリジナルは1965年。伶楽舎が演奏するにあたって改訂がほどこされ、右方の舞いが加わった。
これが圧倒的に良かった。舞人は女性二人、緑の爽やかな装束も颯爽と、きびきびと舞う姿の美しさ、凛々しさが際立っていた。曲も明るく、晴れやかで軽やか。祝いの厳粛さよりも、心の軽さ、明るさ、活力に満ちて、希望を抱かせる。
この「瑞霞苑」が良すぎて、「萬歳楽」がかすんだほどだ。思わず、私は楽屋で楽員をつかまえ、そっと「後半は瑞霞苑だけで、一具をやったほうが良くなかった?」と囁いたほどだ。
客席にいらっしゃる芝先生の周りには、神社のように列ができて、挨拶が連綿と続いていた。先生もお疲れになるだろうから、どうしようか ― とも思ったが、我が楽しき音大時代と、先生と楽しく過ごした学生代表として、素通りはできなかった。
短い間だが、ご挨拶をして、お話をした。先生は私の同級生の名と共に、当時を懐かしむように、明るくわっていらした。
とても良い演奏会だった。雅楽初心者にもお勧めだった。
最近のコメント